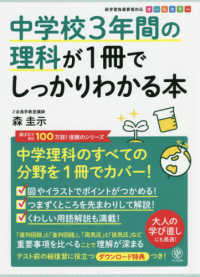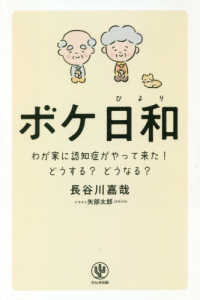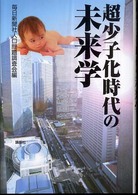出版社内容情報
地名は大地に刻まれた人間の過去の遺跡である。人間が住み、生活するところには地名がある。それは、貴重な無形の文化財である。
一方、日本と朝鮮半島のあいだには、古代より文物、人間の密接な交流がった。しかしながら、言語学では明治時代以来、日本や欧米の研究者たちが盛んに日本語と朝鮮語の比較研究を試みてきたものの、いまだ決定的な結論は出されていない。朝鮮語が日本語のなかに混在し、また日本各地に朝鮮語起源と考えられる地名があるのも事実である。
本資料セットは、日本と密接な関係をもっていた朝鮮半島の文化の痕跡である朝鮮語地名を研究するための基本資料であり、言語学、歴史学、地理学、文化人類学などをはじめとして多方面に裨益するところが大きい。
【スイセン者】
伊藤亜人(東京大学)地方行政の変遷とともに
金達寿(作家)歴史の化石として
田代和生(慶應大学)地方研究の基本資料
1.新旧対照朝鮮全道府郡面里洞名称一覧
2.大東輿地図
3.朝鮮地名研究集成
4.日韓古地名の研究
地図と論文収めた朝鮮地名資料集成
李朝から現代まで、朝鮮の地名の移り変わりがわかる資料集「朝鮮地名資料集成」が、草風館から出た。監修は、吉田光男・東大助教授。
1936年に刊行された『大東輿地図』の復刻版と、1917年当時の約3万の字(あざ)を収録した『朝鮮全道府郡面里洞名称一覧』、明治から戦前にかけての論文を集めた『朝鮮地名研究集成』、明治時代の研究者の金沢庄三郎による論文『日韓古地名の研究』の4点セットにしている。
(1994.9.25 朝日新聞)