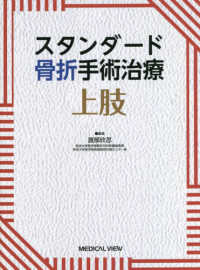出版社内容情報
東北・アイヌ語地名の研究
地名は、その土地で生活した人々の言語の痕跡であり、土地の歴史を刻み込んだ文化遺産でもある。古くからの地名変更に多くの抵抗が起きるのも、こうした認識が浸透していることの証明と言えるであろう。
本書は、40年以上にわたってアイヌ語地名の研究を続けてきた著者が、ここ10年の成果をまとめた。田子、山内、三内、長内、米内、比立内など、東北に残るアイヌ語地名と思われる例について、詳しい検証がなされている。
「仙台から秋田・山形県境付近にかけての線から北方に、一段と濃く分布するアイヌ語地名こそ、蝦夷(えみし)が残した足跡であり、北東北の蝦夷はアイヌ語を常用していた」。これが著者の結論だ。
著者は仙台鉱山監督局長、軍需省化学局長などを歴任した後、北海道曹達社長、会長を務めた。昨年7月、93歳で死去しており、本書が遺稿集となった。
(1993.9.12 河北新報)
第一編 アイヌ語地名遊記
初山別の楽しかった調査紀行
一、調査に出かけるまで 二、調査紀行 三、高橋基 さんの現地調査
石狩川筋のカムイコタソ
前書き 一、旭川の神居古潭 二、空知川のカムイコ タン 三、夕張川のカムイコタン 四、ポロカムイコ タン 五、ボンカムイコタソ 六、ボンカムイコタン
(付)カムイコタソ
トマム遊記-トマム、狩勝峠、然別の地名
手稲諸川のアイヌ語川名-特に札幌の友人方のために
一、札幌西北郊の地形と推移 二、手稲諾川の各川名 等
石狩当別の静かな川筋
一、当別の名の由来 二、当別市街付近の地名 三、 当別川上流のピクニック 四、上流の山々
山城屋の蝦夷地古図の話-古い、珍しい民間の北毎道全 図
一、図が私の書架に残ったいきさつ 二、山城屋図を 読んで
登別の知里家のこと-語る金成まつさんの姿の写生
第二編 東北地方北半のアイヌ語地名
柳(シュシュ)の地名
サンナイ地名の謎ーー東北地名で北毎道のアイヌ語地名を読んだ話
前書き 現地調査記 結論
姓となったアイヌ語地名
一、蝦夷に与えられた姓 二、北海道の新しい姓 平尾鳥
第三編 東北地方南部、関東地方北辺、新潟県を訪ね て
タブコプ(たんこぶ山)物語ーー関東北辺まで続いてあるか?
北海道のタブコプ略説 一、達子森 二、田子 三、田子 四、達居森と女達居山 五、立子山
六、辰子山 七、竜子山
インカラ(眺める)地名物語ーー新潟県にまであったら しい?
サッ地名物語ーー関東北辺まで続いてあるか?
一、北海道の三つのサッ地名 二、東北地方北三県の サッ地名 三、東北の南部諸県 四、関東地方の北辺
エんルム(岬)の話ーー江流末(十三地方)と出雲岬(新潟県)の疑義
『常陸風土記』の異族と地名
一、風土記の中の異族記事 二、異族のいた時代 三、アイヌ語地名かあったろうか
おわりに
著者略歴と業績
1993.8.23 秋田さきがけ
県内の地名も考察
著者は、在野の研究者として50年以上にわたって北海道や東北地方のアイヌ語地名の研究を続け、ことし7月に93歳で亡くなった。本書はその遺稿集。
地名は、その土地にかつて生活した人々の文化遺産であり、その土地の歴史を刻み込んでいる。古代の東北地方で大和朝廷に対抗した蝦夷(えみし)の記録は、記紀をはじめ続日本紀などの史書に登場する。その蝦夷がどのような人々だったのかは、明治以来、論争が続いているが決着はついていない。著者は「蝦夷が生活していた土地に、大和言葉ではない地名があり、それこそが蝦夷語の傷痕といえるのではないか」と述べ、「仙台から秋田・山形県境にかける線から北方にアイヌ語地名が濃く分布する。蝦夷はアイヌ語族だった」と結論づける。
本県の阿仁は、アイヌ型の内(ナイ)地名が特に濃く残っている土地だという。ナイはベツ(ペッ)とともに北海道にはどこにでもある「川・沢」の意味のアイヌ語地名だが、阿仁川筋ではどの沢をとってもナイ地名で埋まっている。
米内沢はイ・オ・ナイ(蛇・多い・川)、笑内はオ・カシ・ナイ(川口に・仮小屋ある・川)、浦志内はウラシ・ナイ(笹
内容説明
古太蝦夷(アイヌ語族)の足跡。山田秀三遺稿集。
目次
第1編 アイヌ語地名遊記
第2編 東北地方北半のアイヌ語地名
第3章 東北地方南部、関東地方北辺、新潟県を訪ねて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
a43
なん
yoneyama