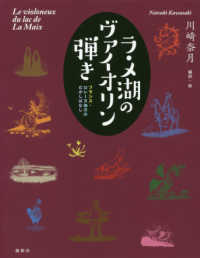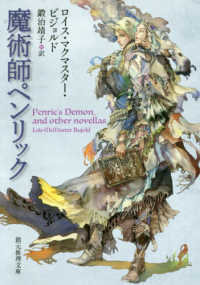内容説明
なぜ、書写・書道を学ぶのか―。学校教育から成人教育まで、書写・書道の指導にたずさわる一一名が、「言葉」「書くこと」「造形」をめぐって展開する「書」の実践集。学習者と指導者双方の学びが円環をなすことで、書における学びが、いわゆる「お習字」の枠を超え、国語、社会、美術、そして生涯にわたる学びへと連鎖していく―学びのあり方「学び観」を提示する。「書って、なんだかよくわからない」への手がかりとなる一冊。
目次
序章 書を通しての「学びの還流」
第1部 定番題材の可能性(「意」を捉えて「生きる力」につながる学びへ―“顔氏家廟碑”;生涯にわたる継続的な書の学びへ―“初唐の三大家”;古典を「真似ぶ」と生徒は「学び」に出会るのか―“蘭亭序”;「本気」に出会い「人間力」につなぐ―“蘭亭序”;子どもの「もっと知りたい」が学びをつなぐ―“高野切”;書文化のミステリーに出会わせたい―“高野切”)
第2部 新しい題材の発掘(未来へつながる学びのサイクル―仙〓“一円相画賛”・榊莫山“東大寺 世界遺産登録記念碑”;古典文学と書道パフォーマンスで時空をつなぐ―“枕草子・大鏡”;「書くレポ」を通じて自分と向き合う―青木香流“ゆき”;書と画で浮かび上がる多様な気づき―仙〓“花見画賛”;印を刻さない学びから広がる篆刻学習の可能性―“描印”)
結「学びの還流」