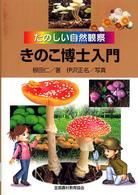出版社内容情報
言語・コミュニケーション教育を社会的な文脈、とりまく環境から切り離さず、教育実践の中で問い直しいかに実践していくかを問う。現在の言語・コミュニケーション教育に欠けているのは、それ自身が対象言語や文化に関するさまざまなビリーフの維持、再生産に大きく関わっていることへの教育関係者自身の(批判的)意識である。本書は言語、文化、学習といった言語・コミュニケーション研究にとって重要な概念を、社会的な文脈、埋め込まれた状況から切り離さずに取り扱い、日々の教育実践の中で問い直し続ける姿勢をいかに実践していくかを問うている。
はじめに iii
第1部 人類学・社会学的アプローチの意義 001
第1章 言語・コミュニケーション教育における人類学・社会学的アプローチの意義
佐藤慎司(プリンストン大学)/村田晶子(法政大学) 003
1.はじめに 003
2.言語コミュニケーション教育における人類学・社会学的アプローチの意義 004
2-1.言語人類学におけるコミュニケーション研究 005/2-2.言語イデオロギー・言語教育イデオロギー 007/2-3.アイデンティティと状況的学習論 009/2-4.社会言語学 011/2-5.教育社会学:不平等の再生産 012/2-6.質的調査法とエスノグラフィー 013/2-7.新しいフィールドワークの手法 016
3.人類学・社会学的アプローチ研究や実践の社会的貢献 018
4.言語コミュニケーション教育研究・実践へ 019
5.本書について 021
参考文献 022
第2部 ことばの教育の人類学・社会学 025
第2章 言語教育/学習の知識社会学
グローバル化における「バベルの塔」と日本列島上をおおう言語イデオロギー ましこひでのり(中京大学) 027
1.はじめに 027
2.自明視される言語学習と言語政策 028
2-1.義務教育と就学状況・識字実態 028/2-2.「国語」の自明性再考 031/2-3.自明視される英語教育神話 035
3.洗脳としての日本語/「外国語」学習:“meme”の発信・受容がかかえる政治性 041
3-1.日本語教育関係者/国語教育関係者が無自覚な実態:洗脳装置としての言語教育 041/3-2.神話=共同幻想としての「外国語」教育 044/3-3.言語学習者の姿勢と実態 048/3-4.神話の伝道師=洗脳装置の末端としての言語教員たち 050
4.おわりに 055
参考文献 056
第3章 学習者の社会階層と日本語学習 岡野 かおり(ラトローブ大学) 059
要旨 059
1.はじめに 060
2.教育と社会的不平等 060
3.オーストラリアにおける日本語学習 063
4.カリキュラムの階層性:オーストラリアの場合 065
5.学習者を取り巻く社会的・制度的外的条件と、学習者の行動の相互作用 069
参考文献 071
第4章 教員のライフヒストリーから何を学べるのか:北米の継承語教育・国際バカロレア教育の実践者の周辺的参加と変容 津田 和男(国連国際学校)・村田 晶子(法政大学) 074
1.教員のライフヒストリーを分析する意義 074
1-1.ライフヒストリー作成の動機 076/1-2.ライフヒストリーの構成 077
2.津田のライフヒストリー 078
2-1.津田の生い立ち:「日本の教育に対する反面教師との対抗と対話」 078/2-2.渡米のいきさつ:「自立した表現教育としての日本語教育の実践」 079/2-3.北米での窮乏:「輝く移民的初期状況」 081/2-4.70年代末―「教育(国際バカロレア)の未来との出会い」 081/2-5.転機:80年代末のバブル期と日本語ブームによる変化:「米国における中等日本語教育の胎動」 083/2-6.90年代 標準化の波:「中等日本語教育の概念化のカリキュラム・デザインの底流」 084/2-7.標準化のパラドックス 087/2-8.学生の共同体(自助集団)の構築と探求型の教育:「国際教育の国際バカロレア教育の批判的・自立的な実践」 087
3.考察 089
参考文献 093
第5章 社会言語学からみたこれからの言語・コミュニケーション教育の課題 山下 仁(大阪大学) 094
1.はじめに 094
2.社会言語学と言語・コミュニケーション教育 095
3.マクロ社会言語学と複言語主義 099
4.ミクロ社会言語学的観点 104
4-1.呼称表現 105/4-2.ポライトネス研究 106/4-3.リテラシー 108/4-4.ウェルフェア・リングイスティクス 111/4-5.ヘイトスピーチと構造的な暴力 114
5.おわりに 116
参考文献 117
第6章 コミュニケーションスキルを問う: 生きづらさを抱える人のためのコミュニケーションワークショップのエスノグラフィー
照山 絢子(筑波大学)・堀口佐知子(テンプル大学日本校) 120
1.はじめに 120
2.R会のワークショップ 122
3.R会の参加者たち 128
3-1.川田さん 128/3-2.楠さん 131/3-3.大澤さん 135
4.R会の思想 137
5.おわりに 141
参考文献 145
第7章 教室における「授業」と「英語」の非自明性から考える:「英語教育」の再帰的批判と「ことばの教育」の再興 榎本 剛士(大阪大学) 146
1.はじめに 146
2.実際に使われることばの流動性とコミュニケーションの多層性を見据える 148
2-1.「ジャンル」概念を通じた「授業」と「授業時間中に起きていること」の区別 148/2-2.「脱/再コンテクスト化」と「スケール」 151/
3.教室を巡る「英語」:その動態と可能性 154
3-1.せめぎ合う「スケール」、変容する「指導」 154/3-2.同じ言及指示的テクスト、異なる現実? 157/3-3.スケールを跨いだ「コンテクスト批判」の萌芽 160/3-4.「今・ここ」で展開するメタ・コミュニケーション、「英語教育」の再帰的批判、そして「ことばの教育」の再興 163
4.おわりに 166
参考文献 168
第3部 人類学・社会学的視点を生かしたことばの教育 171
第8章 大学における多文化協働フィールドワークを通じたことば・文化の学び 村田 晶子(法政大学) 173
1.文化人類学のエスノグラフィー 173
2.フィールドワーク科目の概要 176
2-1.協働グループの構成 176/2-2.フィールドワークの流れ 179
3.フィールドワークを通じた言語コミュニケーションの学び 181
3-1.留学生のフィールドワーク中のことばの使用 181/3-2.学部生にとってのフィールドワーク中のことばの使用 183/3-3.フィールドワークを通じた他者、社会との関わり 183
4.ケーススタディー:刺青のフィールドワークの分析 184
4-1.協働作業のプロセス分析 184/4-2.調査協力者との関わり 186
5.エスノグラフィー作成のもたらす可能性と振り返りの重要性 187
6.おわりに 189
参考文献 191
第9章 ミニ・エスノグラフィーと言語文化教育:個人の役割に焦点を当てて 川村 宏明(米国オハイオ州フィンドレー大学) 183
1.はじめに 193
2.超短期プログラムの運営、指導を通じて 193
3.エスノグラフィック・アプローチの言語学習への応用実践例 202
3-1.留学オリエンテーションへのミニ・エスノグラフィーの応用 202/3-2.海外研修旅行中の活動へのエスノグラフィーの応用 204/3-3.留学中のミニ・エスノグラフィー 206
4.結び 209
参考文献 210
第10章 拡張現実(AR)を活用した英語での学習:学習者の日常を拡げ母語と指導言語の溝を埋める 青山 玲二郎(香港理工大学) 211
1.新技術の教育利用は必要か 211
2.多言語社会・香港とエリート英語教育 213
3.指導言語を巡る政府と現地の人々の衝突 216
4.英語を指導言語とする講義の観察調査 218
5.英語で人文学を学ぶ時に学習者が抱える課題 221
6.ARを用いて状況的学習を促し経験と知識の断絶を越える 224
7.ARを用いて学習者の日常を拡張する実践 230
8.学習者への聞き取り調査とその結果 236
9.ARの英語学習への活用と今後の課題 239
10.人類学・社会学的視点からみた新技術の活用 241
参考文献 243
第11章 ことばにならない経験をことばにすること:多文化チーム・エスノグラフィーの実践をふりかえる 井本 由紀(慶應大学)・徳永 智子(群馬県立女子大学) 246
1.はじめに 246
2.「ふりかえり」とは 247
3.多層的なエスノグラフィー 251
4.チーム・エスノグラフィーの教育実践をふりかえる 253
4-1.ことばを使うことの難しさ 253/4-2.情動・感覚に意識を向ける:異文化体験の先へ 258/4-3.フィールドワークを行う暴力性・危険性 262
5.おわりに 264
参考文献 265
執筆者紹介 267
佐藤慎司[サトウシンジ]
著・文・その他/編集
村田晶子[ムラタアキコ]
著・文・その他/編集
内容説明
現在の言語・コミュニケーション教育に欠けているのは、それ自身が対象言語や文化に関するさまざまなビリーフの維持、再生産に大きく関わっていることへの教育関係者自身の(批判的)意識である。本書は言語、文化、学習といった言語・コミュニケーション研究にとって重要な概念を、社会的な文脈、埋め込まれた状況から切り離さずに取り扱い、日々の教育実践の中で問い直し続ける姿勢をいかに実践していくかを問うている。
目次
第1部 人類学・社会学的アプローチの意義(言語・コミュニケーション教育における人類学・社会学的アプローチの意義)
第2部 ことばの教育の人類学・社会学(言語教育/学習の知識社会学;学習者の社会階層と日本語学習;教員のライフヒストリーから何を学べるのか―北米の継承語教育・国際バカロレア教育の実践者の周辺的参加と変容 ほか)
第3部 人類学・社会学的視点を生かしたことばの教育(大学における多文化協働フィールドワークを通じたことば・文化の学び;ミニ・エスノグラフィーと言語文化教育―個人の役割に焦点を当てて;拡張現実(AR)を活用した英語での学習―学習者の日常を拡げ母語と指導言語の溝を埋める ほか)
著者等紹介
佐藤慎司[サトウシンジ]
現職、プリンストン大学・東アジア研究学部・日本語プログラムディレクター・主任講師。専門、教育人類学、日本語教育
村田晶子[ムラタアキコ]
現職、法政大学教授。専門、教育人類学、異文化間教育、日本語教育(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。