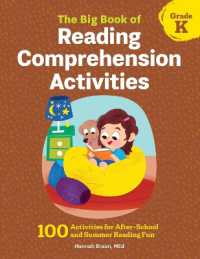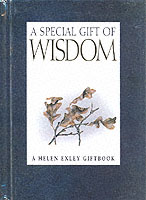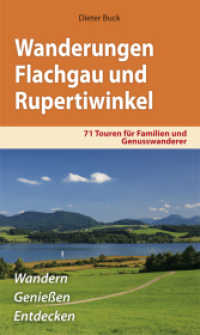内容説明
ことばや障害が原因となって社会的に排除される現象や、社会言語学として提示されているさまざまな記述を再検証し、さらに問題として認知すらされていない、ことばやコミュニケーションにかかわる諸問題を発見し、少数者/情報弱者にひらかれた新しい言語観を提示する。
目次
第1章 日本の社会言語学はなにをしてきたのか。どこへいこうとしているのか。―「戦後日本の社会言語学」小史
第2章 言語における「自然」と「人為」―説明用語から分析対象への転換
第3章 ことば・情報のユニバーサルデザイン―知的障害児・者と言語の関係を中心に
第4章 言語観教育序論―ことばのユニバーサルデザインへの架け橋
第5章 “コミュニケーション能力の育成”の前提を問う―強いられる“積極性/自発性”
第6章 原発と英語―日本における普及過程、問題構造および対策の共通性
第7章 「言語権的価値」からみたエスペラントとエスペラント運動
第8章 多言語化の多面性―言語表示から通訳ボランティアまで
第9章 障害をもつ身体が性暴力被害にあったとき―マイナー・マイノリティの「つたわらない」困難
第10章 左手書字をめぐる問題
第11章 だれのための「ビジネス日本語」か―言語教育教材としての「ビジネス日本語マナー教材」にみられる同化主義
著者等紹介
かどやひでのり[カドヤヒデノリ]
1970年生。現職:津山工業高等専門学校准教授。専門:歴史学・社会言語学
ましこひでのり[マシコヒデノリ]
1960年生。現職:中京大学国際教養学部教授。専門:社会学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。