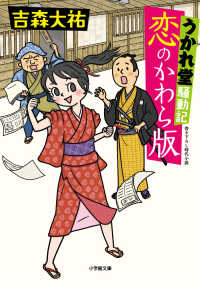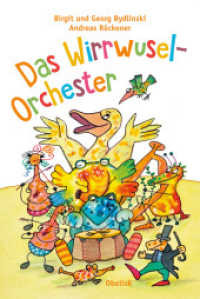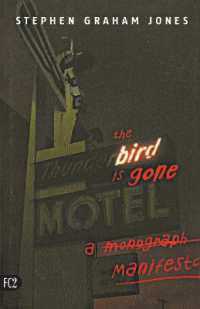内容説明
謹厳だった父が残した十三体の仏像と一冊の古い和本。スペイン語で綴られたその本を読んだぼくは、十一世紀に日本に渡来して大江山の鬼・酒顛童子と恐れられたスペイン人が、自分の祖先であったことを知る!自らの身体に流れる恐ろしい「鬼の血」とは?(表題作)他に、エチオピアに棲むという桃色の珍獣に取り憑かれた男の半生を描く「怪獣YUME」、四年前に自宅の便所から忽然と消えた男が再び姿を現す「湯河原奇遊」など、単行本未収録作品2篇を含む全19篇。
著者等紹介
三橋一夫[ミツハシカズオ]
1908(明治41)年、神戸に生まれる。本名・敏夫。慶應義塾大学経済学部卒。在学中にヨーロッパ留学の経験がある。1940年ごろから「三田文学」「文芸世紀」などに創作を発表。終戦後の48年、林房雄の紹介で「新青年」に「腹話術師」が掲載されてデビュー。不思議小説と銘打った奇妙な作風で好評を博し、同誌の常連執筆者となる。49年6月号から同誌が休刊する50年7月号まで、横溝正史の命名による「まぼろし部落」のタイトルで不思議小説を毎号連載。52年には自伝的長篇『天国は盃の中に』が直木賞候補となる。不思議小説を断続的に発表する一方、五〇年代の半ばからは明朗小説を数多く手がけたが、66年に創作の筆を折り、以後は自論に基づいた健康法の著作に専念した。95(平成7)年12月没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ワッピー
3
著者が自分の作品を私小説だと語ったそうですが、わかるような気もします。何度か共通のモチーフが出てきたり(達磨型のあざ)、死者と生者の創造的交流(特に子供との死別)、ハイソな奥様が逆境や貧困に耐え、困難を乗り越えるなどはきっとわかりやすい体験があるのではないでしょうか。そんなことを詮索しなくても、シュールなもの、歴史もの、戦後混乱期ものの短篇として楽しめます。ワッピーは「白鷺魔女」の気さくな如来様が特に好きです。「歯型」はハーディー「呪われた腕」と共通の題材を扱っていますが、三橋流の温かさを感じます。2017/01/02
makersat
2
「殺されるのは嫌だ」「鬼の末裔」「三井寺の鐘つき男」「沈黙の塔」「帰って来た男」が特に気に入った。全て「不思議小説」でいいかと思うが、野暮を承知で敢えて分類するならば、殺されるのは嫌だと鬼の末裔が恐怖小説、三井寺の鐘つき男と帰って来た男が人情小説(少し違うか?)、沈黙の塔が冒険小説といったところだろう。人情小説に分類した二篇は、どこか心が温かくなりつつ、結末には涙せざるを得ない。恐怖小説二篇は、恐怖に焦点が当たるわけでなく、やはり「不思議」なのが魅力か。沈黙の塔は印度近辺を巡る冒険にハラハラドキドキした。2016/05/09
パット長月
2
集成①に多い、生のはかなさというか「おい、どうしてそんなに簡単に死んでしまうんだ」と叫びたくなるような哀れな物語はほとんどない。収録作品が古くて1949年、新しいものは60年ということで、終戦から遠ざかるにつれて、著者の心情に変化があったのだろうか。代わりに、何だったんだろうこれ、という読後感のものがかなりある。長めのものが特にそうだが、読後感だけでなく、読んでいる途中でも、作者は何でこんなものを大真面目に書いているのか不思議なものがいくつかある。これは出来不出来よりも、著者独自の小説観によるのだろうか。2013/08/24
黒とかげ
1
うーん 全ての短編が一定の基準以上ではあるものの、しかし突き抜けるようなものはなかったなぁ…2018/01/18