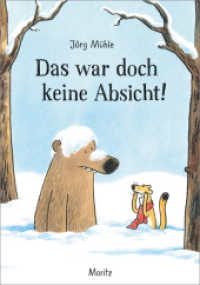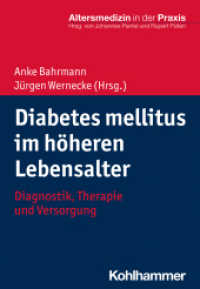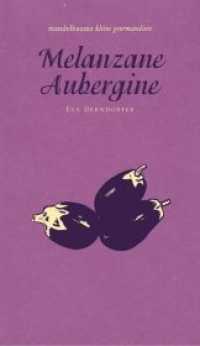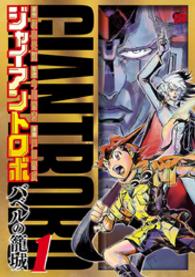- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 図書館・博物館
- > 図書館・博物館学その他
内容説明
京・大阪・江戸に集中していた書肆も、明治になって地方に広がり、学制改革・国会開設・日清日露の緊張・大正デモクラシー・円本洪水・出版統制を経て、今日の諸様態に至る。その百年の歩みを、概説するのではなく、実際に現場で携わっていた書店・出版人の諸先輩にじかに話を伺い、全体をまとめた。本書は出版販売百年の貴重な証言です。
目次
北海道・東北(冨貴堂;金森系の書店;今泉本店;成田本店;八文字屋;仙台金港堂;岩瀬書店)
関東(川又書店;うちやま;煥乎堂;須原屋;多田屋;松田屋;有隣堂)
東京(丸善;春陽堂;三省堂書店;東京堂書店;北隆館;明正堂;湘南堂;大平堂;紀伊国屋書店)
東海・北陸(谷島屋;戸田書店;星野書店;覚張書店;中田書店;西沢書店;博信堂;品川書店;うつのみや)
近畿(文泉堂;旭屋書店;大喜書店;日東館書林;別所書店)
中国・四国・九州(今井書店;吉田書店;啓文社;片桐開成社;福岡金文堂;金龍堂;金海堂)
三冊で10践!ポンポン蒸気の中で本を売る
「大川文庫」300点の歴史
お得意さんは化粧品・小間物・玩具屋さん。
地方卸の苦心談
夜店・古本屋相手から満州・台湾へ残品の大卸
江戸の名残りがむしろ仇、苦心の多かった大阪出版物
薬と本は兼業だった明治半ばまでの大阪のしきたり
「立川文庫」を生んだ人々
書店の成立から寡占化の時代まで