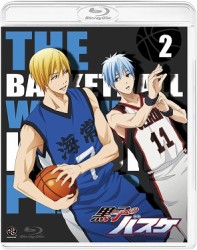出版社内容情報
(2000年『フッ素系生理活性物質の進歩と応用展開 』普及版)
--------------------------------------------------------------------------------
1990年に石川延男先生の監修による『90年代のフッ素系生理活性物質』が発行されてから10年が経過した。この間の医薬品,農薬をはじめとする生理活性物質の分野におけるフッ素化合物の利用はますます発展を見せている。本書は先の叢書の後継書として,医薬品と農薬の各分野におけるこの10年間の開発の動向を中心にまとめたものである。さらに,本書では有機フッ素化合物の合成に関する最近の進歩も併せてまとめた。実験用試薬のカタログ誌を見ても,ここ数年のあいだにフッ素系試薬の種類が非常に増加してきており,これまであまりフッ素に馴染みがなかった研究者にも有機フッ素化合物の利用を一層容易なものとしていることが窺える。と同時に,多くの分野で研究が進んでフッ素の利用に関する知見の深化と,新しい局面が開拓されることを期待したい。
最近(1998年)の世界の医薬品売上げ高の上位25位までに含フッ素医薬品は7品目あり,フッ素導入の意義はともかくこの分野でのフッ素の重要性をあらためて感じる。1950年代にモノフルオロ酢酸の毒性発現機構が分子レベルで提唱され,その直後に含フッ素ステロイド系抗炎症剤,さらにフルオロウラシル系制癌剤の発見を機に,この分野でのフッ素の利用とフッ素導入の意義の解明への関心がもたれはじめた。そして,多くの含フッ素医薬品や農薬が実用化されるに至っている。
一方で分子生物学,薬理学さらには病態生理学などの目覚ましい発展は,受容体や酵素反応に基づく医薬品,農薬など生理活性物質の分子設計に画期的な寄与をもたらした。有機フッ素化合物についてもこれまでの知見の集積により,有機フッ素化合物の特異的な性質を基盤とする薬理効果の発現や増強,薬物動態の改善さらには阻害剤などの分子設計の考え方が部分的には確立されてきたと考えられる。しかしながら,フッ素導入の意義のより明確な解明は今後への継続的な課題として残されており,計算化学手法を含めた基礎的研究と実用化を目指す応用研究の密な連携の中からこれまでの知見をブレークスルーするような進展を期待したい。
本書は日ごろそれぞれの分野で関わりをもっている方々に執筆をお願いして,実用的な立場で現在までに開発され,上市されたものや臨床段階のものを含めたこれまでの流れをここ10年の動向を中心として,フッ素系生理活性物質のこの間の進歩と応用展開の概略を紹介するものである。
本書が,多くの読者,研究者に有意義な情報を提供するものであることを願っている。 2000年6月 田口武夫
普及版の刊行にあたって
本書は2000年6月に『フッ素系生理活性物質の進歩と応用展開』として刊行されました。このたび普及版を刊行するにあたり,内容は当時のまま何ら手を加えておりませんが,ご了承願います。 2005年7月 (株)シーエムシー出版 編集部
--------------------------------------------------------------------------------
田口武夫 東京薬科大学 薬学部 教授
伊関克彦 ダイキン工業(株) 化学事業部 第2研究開発部 主任研究員;(現)東レ(株) 医薬研究所 リサーチフェロー,室長
河田恒佐 エフテック(株) 研究所 研究開発グループ リーダー;(現)東ソー・エフテック(株) 研究所 所長
淵上寿雄 東京工業大学 大学院総合理工学研究科 物質電子化学専攻 教授
米田徳彦 北海道大学大学院 工学研究科 分子化学専攻 教授
西山竜夫 (株)トーケムプロダクツ 取締役 開発本部長
木村芳一 イハラケミカル工業(株) 研究所 主任研究員;(現)イハラケミカル工業(株) 取締役 研究開発部長
沢田英夫 奈良工業高等専門学校 物質化学工学科 教授;(現)弘前大学 理工学部 物質理工学科 教授
高橋寿 第一製薬(株) 東京研究開発センター 創薬第一研究所 主任研究員
竹村真 第一製薬(株) 東京研究開発センター 創薬第一研究所 主幹研究員
早川勇夫 第一製薬(株) 理事 東京研究開発センター 創薬第一研究所 所長
石田史明 万有製薬(株) つくば研究所 運営部 研究推進課 課長
亀井敏夫 万有製薬(株) 研究開発業務審査室 室長; (現)万有製薬(株) 臨床医薬研究所 メディカルライティング部長
喜多田好 三菱東京製薬(株) 横浜研究所 創薬第一研究所 薬理1Cグループ グループマネジャー;(現)三菱ウェルファーマ(株) 創薬第二研究所 研究所長
森澤義富 旭硝子(株) 技術本部 中央研究所 主幹研究員
山本武志 日本オルガノン(株) 医薬研究所 化学研究室;(現)武田薬品工業(株) 化学研究所 主任研究員
黒木保久 (株)大塚製薬工場 栄養研究所 医薬化学研究室;(現)Director, Medical Product Development Cambridge Isotope Laboratories, Inc.
田村隆 丸石製薬(株) 中央研究所 所長
平井憲次 (財)相模中央化学研究所 有機合成第2グループ 主席研究員
波多野連平 日本曹達(株) 小田原研究所 生物研究部 主席研究員;(現)日本曹達(株) 小田原研究所 生物研究一部 部長
濱村洋 日本曹達(株) 小田原研究所 生物研究部 主席研究員
(執筆者の所属は,注記以外は2000年当時のものです。)
--------------------------------------------------------------------------------
序章 フッ素系生理活性物質の最近の動向と今後の展望(田口武夫)
1. はじめに
2. 有機フッ素化合物の性質と生理活性
2.1 フッ素原子とC-F結合
2.2 疎水性の変化
2.3 バイオイソスター
2.4 フッ素置換反応活性種と化学的反応性
3. 含フッ素酵素阻害剤
3.1 脱プロトン化過程の阻害
3.2 自殺型酵素阻害剤
3.3 遷移状態ミミック(プロテアーゼ阻害剤を中心として)
4. 今後の展望
第1編 フッ素系生理活性物質の合成
第1章 ビルディングブロック(伊関克彦)
1. はじめに
2. フルオロアルカン
2.1 求電子的炭素ー炭素結合形成反応
2.2 求核的炭素ー炭素結合形成反応
2.3 ヘテロ原子への反応
2.4 フルオロシクロプロパン化反応
3. 含フッ素オレフィン
3.1 ビニルアニオン種を用いる反応
3.2 含フッ素オレフィンへの求核的付加反応
3.3 含フッ素オレフィンへの求電子的付加反応
3.4 3,3,3-トリフルオロプロぺンおよび類縁化合物の反応
4. 含フッ素カルボニル化合物
4.1 含フッ素アルデヒドおよびケトンの反応
4.2 含フッ素エステルおよび関連化合物への求核的反応
4.3 含フッ素エノレートおよび関連化合物の反応
4.4 含フッ素カルボニル化合物による他の反応
5. その他
6. 触媒的不斉合成によるキラルなフッ素化合物の合成
第2章 フッ素化法
1. 脂肪族(河田恒佐)
1.1 はじめに
1.2 求電子的フッ素化法
1.3 求核的フッ素化法
2. 電解フッ素化法(淵上寿雄)
2.1 はじめに
2.2 芳香族化合物の電解フッ素化
2.3 オレフィンの電解フッ素化
2.4 カルボニル化合物の電解フッ素化
2.5 カルコゲノ化合物の電解フッ素化
2.6 その他のヘテロ原子化合物の電解フッ素化
2.7 複素環化合物の電解フッ素化
2.8 電解gem-ジフッ素化
2.9 間接電解フッ素化
2.10 おわりに
3. 芳香族
3.1 光照射脱アミノフッ素化法(米田徳彦,西山竜夫)
3.1.1 はじめに
3.1.2 脱アミノフッ素化反応の問題点
3.1.3 光照射脱アミノフッ素化反応の開発
(1) HF中でのArNH2 のジアゾ化反応機構
(2) HF-ピリジン溶融塩を用いるArNH2 の脱アミノフッ素化反応
(3) HF-ピリジン溶融塩を用いるArNH2の光照射・脱アミノフッ素化反応
(4) 光脱アミノフッ素化反応の工業的展開
(5) 工業的光脱アミノフッ素化反応装置によるArFの合成例
3.1.4 おわりに
3.2 フルオリドアニオンによる芳香族のフッ素化(木村芳一)
3.2.1 はじめに
3.2.2 KFの活性化
3.2.3 溶媒
3.2.4 触媒
(1) Ph4PBr,Ph4PCl
(2) 耐熱性ピリジニウム塩
(3) その他の触媒
3.2.4 脱ニトロフッ素化
4. 含フッ素オリゴマー類の合成と性質(沢田英夫)
4.1 はじめに
4.2 フルオロアルキル基含有アクリル酸オリゴマー類
4.3 フルオロアルキル基含有スルホン酸オリゴマー類
4.4 カチオンセグメントを有するフルオロアルキル基含有オリゴマー類
4.5 フルオロアルキル基含有5-クロロキノリルアクリレートオリゴマー類
4.6 フルオロアルキル基含有ベタインオリゴマー類
4.7 イソシアナトセグメントを有するフルオロアルキル基含有オリゴマー類
4.8 おわりに
第2編 フッ素系医薬
第1章 総論(田口武夫)
第2章 合成抗菌薬(高橋寿,竹村真,早川勇夫)
1. はじめに
2. ニューキノロン薬の6位フッ素の役割
3. 1位側鎖へのフッ素の導入
3.1 2-フルオロエチル基
3.2 フッ素置換tert-ブチル基
3.3 フルオロアリール基
3.4 (1R,2S)-2-フルオロシクロプロピル基
4. 7位置換基へのフッ素の導入
5. キノロン骨格部位へのフッ素の導入
6. 従来とは異なる構造を特徴とする化合物
6.1 7位des-aza誘導体
6.2 6位des-フルオロ体
6.3 2-ピリドン誘導体
7. おわりに
第3章 抗高脂血症薬(石田史明,亀井敏夫)
1. はじめに
2. 現在市販中または開発中のフッ素含有スタチン類
3. スタチン以外のフッ素含有抗高脂血症薬
第4章 循環器系作用薬(喜多田好)
1. 緒言
2. イオンチャンネルをターゲットとした薬剤
2.1 Caチャンネル拮抗薬
2.1.1 ミベフラジル
2.1.2 フルナリジン
2.2 Naチャンネル拮抗薬/活性化薬
2.3 Kチャンネル拮抗薬/活性化薬
3. 受容体をターゲットとした薬剤
3.1 AT1受容体拮抗薬
3.2 5-HT2受容体拮抗薬
3.3 βノルアドレナリン受容体拮抗薬
4. 酵素をターゲットとした薬剤
4.1 抗心不全薬としてのホスホジエステラーゼ阻害薬及びドーパミンβハイドロキシラーゼ阻害薬
4.1.1 血管拡張性強心薬
4.1.2 DBH阻害薬
4.2 ピルベートデヒドロゲナーゼカイネース(PDHK)阻害薬
5. おわりに
第5章 制癌剤(森澤義富)
1. はじめに
2. 核酸系抗癌剤
3. 非核酸系抗癌剤
第6章 抗感染症剤(森澤義富)
1. はじめに
2. 抗ウイルス剤
3. 抗マラリア原虫剤
第7章 中枢神経系作用薬(山本武志)
1. はじめに
2. 抗不安薬
3. 抗うつ薬
4. 抗てんかん薬
5. 片頭痛薬
6. 抗精神病薬
7. おわりに
第8章 抗糖尿病薬(黒木保久)
1. PTP 1B阻害剤
2. PDHキナーゼ阻害剤
3. PPAR-γアゴニスト
4. 腎臓での糖再吸収阻害剤
5. その他の糖尿病薬
第9章 抗炎症・アレルギー治療薬(山本武志)
1. はじめに
2. 抗炎症薬
3. 抗アレルギー薬
4. おわりに
第10章 麻酔剤(田村隆)
1. はじめに
2. 臨床で使用されている吸入麻酔薬
3. 吸入麻酔薬に要求される物理化学的性質
3.1 分配係数
3.2 ソーダライムとの反応性
3.3 燃焼性・爆発性
3.4 環境に与える影響
4. 薬理学的問題
4.1 代謝
4.2 カテコラミン感受性
4.3 心血管系の生理学的諸機能
5. 化学
第3編 フッ素系農薬
第1章 総論(平井憲次)
第2章 除草剤(平井憲次)
1. アセチルCoAカルボキシラーゼ(ACCase)阻害剤
2. アセト乳酸合成酵素(ALS)阻害剤
2.1 含フッ素SU系ALS阻害剤
2.2 含フッ素トリアゾロピリミジン系ALS阻害剤
2.3 含フッ素トリアゾリノン系ALS阻害剤
3. プロトポルフィリノーゲン-Ⅸオキシダーゼ(PPO)阻害剤
4. カロチノイド生合成阻害剤
4.1 フィトエン脱水素酵素(PDS)阻害剤
4.2 4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素(4-HPPD)阻害剤
5. その他の阻害剤
5.1 細胞分裂阻害剤
5.2 細胞壁(セルロース)生合成阻害剤
5.3 ホルモン型除草剤
5.4 その他
6. おわりに
第3章 殺虫剤(波多野連平)
1. ピレスロイド系
2. フェニルピロール系
3. フェニルピラゾール系
4. ジヒドロピラゾール系
5. ジフロロシクロプロパンおよびジフロロオレフィン係
6. ベンゾイルウレア系(IGR)など
7. 殺ダニ剤
第4章 殺菌剤(濱村洋)
1. アゾール系
2. メトキシアクリレート系
3. フェニルピロール系
4. カルボキシアニリド系
5. その他
内容説明
本書は日ごろそれぞれの分野で関わりをもっている方々に執筆をお願いして、実用的な立場で現在までに開発され、上市されたものや臨床段階のものを含めたこれまでの流れをここ10年の動向を中心として、フッ素生理活性物質のこの間の進歩と応用展開の概略を紹介するものである。
目次
フッ素系生理活性物質の最近の動向と今後の展望
第1編 フッ素系生理活性物質の合成(ビルディングブロック;フッ素化法)
第2編 フッ素系医薬(総論;合成抗菌薬;抗高脂血症薬 ほか)
第3編 フッ素系農薬(総論;除草剤;殺虫剤 ほか)
著者等紹介
田口武夫[タグチタケオ]
東京薬科大学薬学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。