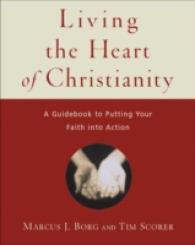出版社内容情報
長命の儒者が、自分はどう生きたか、その間に健康についてどれだけの配慮をしたかを書いた肉体的自伝。
内容説明
長寿の儒者が最後まで大事にしたのは自然治癒の感覚だった。
目次
養生訓
楽訓
和俗童子訓
著者等紹介
貝原益軒[カイバラエキケン]
1630~1714。江戸前期から中期にかけての儒学者、博物学者、教育家。名は篤信、号は損軒、晩年に益軒と改めた。筑前福岡藩主黒田家に仕えた。藩費で10年間京都に遊学する間に、朱子学者、博物学者と交際し、上方に興りつつあった経験・実証主義思潮に触れたのが、その後の学風に生かされた。膨大な編著は各方面にわたり、儒学では『大疑録』、博物学では『大和本草』『花譜』『菜譜』などがよく知られる。晩年には『養生訓』『大和俗訓』など多くの教訓書を書いた
松田道雄[マツダミチオ]
医師、育児評論家。1908年(明治41年)茨城県生まれ。京都帝国大学医学部卒業。戦後、京都で小児科医を開業するかたわら医療、育児、教育、社会・政治など万般にわたる評論活動を行う。1998年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。