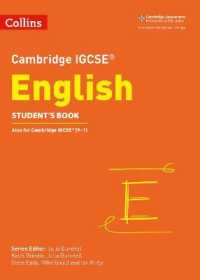出版社内容情報
(1997年3月『高分子安定化の総合技術 』普及版)
近年高分子材料の質的発展は目覚ましいものがあり,その高機能化・高性能化が計られるようになってきた。しかし昨今では環境保全の立場から,プラスチックリサイクルという観点からの新しい課題が高分子材料に課せられるようになった。プラスチックリサイクルは環境的にも,エネルギー的にもかなりマイナスの要素を含んでおり,その遂行はゴミとして廃棄されるプラスチックの量を単に減らすためのものであるかのようにみえる。このような視点で高分子材料を再考するならば,その廃棄量を軽減するためにも,高分子材料の更なる長寿命化を模索することが一層重要になってくる気がしてならない。
高分子材料の長寿命化は,その高機能化・高性能化を支える基本的な技術であり,この分野においても高分子材料の関連技術は著しく発展した。この様子はシーエムシー出版が刊行した『高分子材料の長寿命化と環境対策』(初版1990年発行,普及版2000年8月発行),『高分子添加剤の開発技術』(初版1992年発行,普及版1998年6月発行)などによく反映されており,これらの書籍がその時々の高分子材料の分野で先導的役割を果たしてきたことは周知のとおりである。しかしながら,高分子材料の安定化技術は多くの化学的・物理的基礎学問を基盤とした集大成である。したがってその技術を十分に理解しかつその分野の発展に貢献するのに,基礎学問の参考書を別に参照する必要があった。すなわち高分子材料の現状を考えると,応用面に焦点を合わせ過ぎた知識だけでは時代の進歩についていけなくなってきたし,応用面を支える基礎理論抜きでは新しい技術開発が不能になってきたと言っても過言ではない。
そこで本書は,高分子材料の安定化に関する基礎理論を解説し,それが応用面でどのように活かされているか,また技術開発にどのようにつなげられるかを平易に記述した。言い換えると,高分子材料の安定化技術がこの1冊で理解できるような構成とした。内容は,第1章「高分子の劣化機構」,第2章「高分子の安定化機構と安定剤」,第3章「高分子の安定化・各論」,第4章「高分子の安定性評価技術・促進法」からなり,どちらかというと前半が基礎的側面,後半が応用的側面から書かれている。これらの基礎と応用を有機的に結びつけるために,本書には索引をつけた。これも本書の特徴である。目次だけで本書の更なる大きな特徴を理解するのは少々難しいかもしれないが,担当の先生方には本書の企画の意図を十分ご理解いただき,ご執筆賜った。執筆者は,ご自分の研究や少なからぬ講演の経験から,その技術分野でひっかかる問題点を熟知した先生であり,そのような点をかなり詳細にかつ平易に書いていただいた。ここに先生方のご協力とご尽力に心より感謝したい。
本書は,1997年に『高分子安定化の総合技術』―メカニズムと応用展開―として刊行された。
現在高分子安定剤の分野は,しばらくの停滞期を終え,新しい方向へ進む転換期に入った。しかしこの流れをよく理解しかつ流れに乗るには,安定剤の過去の動向を十分理解しておくことが必要である。そのような点から考えて,本普及版の出版はタイムリーのものであり,これが高分子材料の分野で仕事をする研究者や技術者の座右の書となりうるものとして確信している。
平成17年3月 大勝靖一
--------------------------------------------------------------------------------
大勝靖一 工学院大学 応用化学科
黒木健 (有)高分子分解研究所
角岡正弘 大阪府立大学 工学部 応用化学科
(現)大阪府立大学 名誉教授
太智重光 大内新興化学工業(株) 中央研究所
(現)大内新興化学工業(株) 本社・企画室
西本清一 京都大学 大学院 工学研究科
春名徹 旭電化工業(株) 研究開発本部 樹脂添加剤開発研究所
山口哲夫 住友化学工業(株) 精密化学品研究所 (現・住友化学(株))
福田加奈子 住友化学工業(株) 精密化学品研究所
(現)住友化学(株) 化成品事業部
佐々木万治 住友化学工業(株) 精密化学品研究所 (現・住友化学(株))
沢村孝司 日本油脂(株) 油化学研究所
飛田悦男 旭電化工業(株) 樹脂添加剤開発研究所
谷本重夫 シプロ化成(株)
大手良之 チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株) 添加剤事業部
中沢健二 旭電化工業(株) 研究開発本部 樹脂添加剤開発研究所
吉川和美 旭電化工業(株) 研究開発本部 樹脂添加剤開発研究所
東泰 出光石油化学(株) 樹脂技術部 応用研究所
(現)カルプ工業(株) 複合材料研究所
丹淳二 三井石油化学工業(株) 高分子研究所
(現)三井化学(株) マテリアルサイエンス研究所
西原一 旭化成工業(株) スチレン樹脂技術開発部
(現)旭化成ケミカルズ(株) 技術戦略・新事業開発センター
秋山一 三洋化成工業(株) 研究本部
(現)三洋化成工業(株) 監査本部
田中丈之 東北電子産業(株)
(現)(有)かきとう
大西章義 三菱化学(株) 四日市総合研究所
木嶋芳雄 ダイプラ・ウィンテス(株)
高山森 (株)アクトリサーチ
(現)(株)ダイヤ分析センター 技術本部
(執筆者の所属は,注記以外は1997年当時のものです。)
--------------------------------------------------------------------------------
第1章 高分子の劣化機構
1. 劣化概論と自動酸化(大勝靖一)
1. 高分子材料の熱的性質
2. 高分子材料の劣化因子
2.1 内在因子
2.1.1 重合開始剤
2.1.2 立体規則性
2.1.3 高分子種
2.2 外来因子
2.2.1 非晶性と結晶性
2.2.2 安定剤・充填剤
2.2.3 その他の要因
3. 劣化機構と自動酸化
3.1 劣化機構
3.1.1 酸素劣化-自動酸化
3.1.2 無酸素劣化
3.2 劣化素反応
3.2.1 連鎖開始反応
3.2.2 連鎖移動反応
3.2.3 連鎖分岐反応
3.2.4 連鎖停止反応
3.3 自動酸化と生成物
2. 熱劣化機構(黒木健)
1. はじめに
2. 熱劣化プロセス
2.1 低温劣化
2.2 高温熱劣化
3. 接触劣化
4. おわりに
3. 光劣化機構(角岡正弘)
1. 有機光化学の基礎
1.1 光化学の基礎知識
1.2 励起状態
2. ポリマーの光劣化
3. 光劣化反応
4. 光酸化劣化の開始機構
5. ポリマー固体の光劣化
5.1 反応の不均一性
5.2 反応基の運動
4. オゾン劣化機構(太智重光)
1. 大気中でのオゾンの生成機構と分布状況
2. オゾンの化学反応性と劣化の特徴
3. オゾン劣化の実例
5. 劣化とモルホロジー(西本清一)
1. はじめに
2. 高分子モルホロジー
3. 高分子加工条件とモルホロジーの多様化
4. 高分子モルホロジーのキャラクタリゼーション
5. 高分子モルホロジーと力学的性質
6. 劣化とモルホロジー(その1):力学的特性の劣化に及ぼす一次モルホロジーの影響
7. 劣化とモルホロジー(その2):化学変化によるモルホロジーの転成
8. おわりに
第2章 高分子の安定化機構と安定剤
1. 安定化と安定剤(春名徹)
1. 安定剤の役割
2. 安定剤の配合技術
3. 安定剤の種類
3.1 一般樹脂用安定剤の種類
(1) ラジカル連鎖開始阻害剤
(2) ラジカル捕捉剤
(3) 過酸化物分解剤
3.2 塩ビ用安定剤の種類
(1) 熱安定剤
(2) 安定化助剤
2. フェノール系安定剤(山口哲夫,福田加奈子,佐々木万治)
1. はじめに
2. フェノール系酸化防止剤の開発の歴史
3. 安定化機構
4. 高性能酸化防止剤の開発
5. フェノール系アルキルラジカル捕捉剤
5.1 安定化のメカニズム
5.2 熱劣化防止機能
5.3 熱劣化防止効果の応用例
6. 非着色性フェノール系安定剤の開発
6.1 酸化着色のメカニズムと改良方法
6.2 耐NOX着色性
7. おわりに
3. チオエーテル系酸化防止剤(沢村孝司)
1. はじめに
2. チオエーテル系酸化防止剤の作用機構
3. チオエーテル系酸化防止剤の性能
4. チオエーテル系酸化防止剤の問題点
5. 新しいチオエーテル系酸化防止剤
6. おわりに
4. リン系酸化防止剤(飛田悦男)
1. 一般的な合成法
2. 作用機構と特徴
2.1 作用機構
2.2 フェノール系酸化防止剤の役割
2.3 リン系酸化防止剤の消費挙動
2.4 イオウ系酸化防止剤との比較
2.5 ハイドロパーオキサイド分解能
3. 構造と特徴
4. 実用例
5. おわりに
5. 紫外線吸収剤(谷本重夫)
1. はじめに
2. 高分子の光安定化に使用される紫外線吸収剤
3. 紫外線吸収剤の作用機構
4. 紫外線吸収剤の実用例
5. 今後の課題
6. 光安定剤の最新技術について(HALSを中心に)(大手良之)
1. はじめに
2. 光安定剤の種類とその特徴
2.1 紫外線吸収剤(UVA)
2.2 励起エネルギー吸収剤(Quencher)
2.3 紫外線遮蔽材
2.4 ヒンダードアミン系光安定剤(HALS)
3. 樹脂の劣化メカニズム
4. ポリオレフィン系樹脂におけるUVAの位置づけ
5. 光安定剤としてのHALS
5.1 HALSの安定化メカニズム
5.2 HALSの各種用途への応用例
(1) Fiberグレード
(2) 厚物成形品
(3) フィルム用途
5.3 HALS使用上の注意点
5.4 静的熱安定剤としてのHALS
6. おわりに
7. 塩ビ用熱安定剤(中沢健二)
1. 塩ビの劣化と安定化機構
2. 安定剤の構造と作用機構(金属種と効果)
2.1 Pb系安定剤
2.2 Sn系安定剤とその作用
2.3 金属せっけん系安定剤のその作用
2.4 安定化助剤とその作用
(1) ホスファイト
(2) β-ジケトン化合物
(3)そ の他
3. 安定剤の脱重金属化
8. 安定剤間,および安定剤と充填材間の相互作用(吉川和美)
1. はじめに
2. 安定剤間の相互作用
2.1 相乗作用
2.1.1 同じ作用機構を持つ安定剤の作用(Heterosynergism)
2.1.2 異なった作用機構を持つ安定剤の併用(Heterosynergism)
2.2 拮抗作用
2.2.1 フェノール系AOとHALSの併用
2.2.2 HALSと過酸化物分解剤併用
3. 安定剤と充填剤の相互作用
4. おわりに
第3章 高分子の安定化・各論
1. ポリプロピレン(東泰)
1. はじめに
2. 添加剤処方開発
2.1 添加剤処方開発の3次元モデル
2.2 添加剤選定のリスク・ベネフィット(R/B)の概念
2.3 評価技術の3要素
2.4 添加剤処方開発の体系
3. これまでの開発事例
3.1 高分子材料開発からの視点
(1) ポリプロピレン樹脂特性からのニーズ
(2) 製造技術からのニーズ
(3) 改質技術からのニーズ
(4) その他
3.2 材料市場からの視点
(1) 使用環境条件からのニーズ
(2) 添加剤使用リスクからのニーズ
(3) 添加剤の相互作用からのニーズ
4. 今後の安定化技術
4.1 環境認識
4.2 今後の方向性
5. おわりに
2. ポリエチレン(丹淳二)
1. はじめに
2. ポリエチレンの劣化
3. ポリエチレンの安定化
4. ポリエチレン用安定剤の問題点
5. おわりに
3. スチレン系樹脂の安定化(西原一)
1. はじめに
2. 高分子の構造と安定性
2.1 熱分解パターン
2.1.1 ランダム分解
2.1.2 解重合
2.1.3 測鎖の反応と橋かけ・炭化
2.2 熱安定性と難燃性
2.3 各種高分子の劣化機構(各論)
2.3.1 ポリスチレンの熱分解機構
2.3.2 ポリスチレンの光劣化機構
2.3.3 ポリスチレンの環境応力亀裂機構
2.3.4 ポリフェニレンエーテル(PPE)の熱分解機構
2.3.5 ポリフェニレンエーテル(PPE)の光劣化機構
2.3.6 ポリカーボネート(PC)の熱分解機構
2.3.7 ポリカーボネート(PC)の光劣化機構
3. 高分子の構造と安定化技術
3.1 熱安定性向上技術
3.2 耐光性向上技術
3.3 耐環境応力亀裂特性(ESCR)向上技術
4. 安定剤の構造と安定化技術
4.1 熱安定剤の構造と熱安定性
4.1.1 酸化防止剤
4.1.2 ハロゲン捕捉剤
4.2 耐光剤の構造と耐光性
4.2.1 紫外線吸収剤
4.2.2 ヒンダードアミン系光安定剤
4.2.3 酸化防止剤
4.2.4 ハロゲン捕捉剤
4.2.5 遮光剤
4.2.6 金属不活性剤
4.2.7 消光剤
4.3 安定剤の添加効率の向上
5. 難燃スチレン系樹脂の安定化
5.1 ハロゲン系難燃剤の構造と安定化技術
5.1.1 熱安定剤
5.1.2 耐光性
5.1.3 物性安定性
5.2 リン系難燃剤の構造と安定化技術
5.2.1 熱安定性
5.3 トリアジン系難燃剤の構造と熱安定化技術
5.4 難燃スチレン系樹脂の安定化技術のまとめ
4. ゴム(太智重光)
1. ゴムの耐熱性の向上
1.1 加硫用薬剤による耐熱性の向上
1.2 老化防止剤による耐熱性の向上
2. ゴムの耐オゾン性の向上
5. ポリウレタン(秋山一)
1. ポリウレタンの構造と劣化
(1) ポリウレタンの熱劣化
2. 紫外線による黄変の機構
(1) キノンイミド(着色物質)の生成
(2) アゾ化合物の生成
3. 加水分解
4. その他の劣化
(1) 石灰化
(2) 酸化
(3) 加水分解防止剤
(4) その他,医療用途での殺菌による劣化など
5. ポリウレタンの安定化
(1) 酸化防止
(2) 光安定剤
(3) 加水分解防止剤
(4) 微生物劣化の防止策
(5) 熱分解防止法
6. 塗膜(田中丈之)
1. はじめに
2. 塗膜の構成と環境
3. 塗膜の劣化要因
4. 塗膜の劣化現象
4.1 白亜化
4.2 変退色
4.3 塗膜のワレ
4.4 酸性雨劣化
5. 塗膜の安定化
6. おわりに
第4章 高分子の安定性評価技術・促進法
1. 評価の基礎技術と加工安定性評価法・耐熱性評価法(大西章義)
1. 評価の基礎技術と加工安定性評価法・耐熱性評価法
1.1 序
1.1.1 寿命という概念の的確な把握
1.1.2 ユーザーが要求する寿命の的確な把握
1.1.3 ユーザーにおける製品使用環境因子の定量的・有機的把握
1.1.4 高分子の劣化・安定化機構に関する豊富・正確な知識修得
1.1.5 高分子構造の把握
1.1.6 形成加工条件の把握
1.1.7 高分子添加剤の熟知
1.1.8 製品デザインの正確な把握
1.1.9 劣化挙動・寿命の予測に有用なデータの豊富な蓄積
1.1.10 安定性評価に関する豊富・正確な知識修得
1.2 最近の文献にみる加工安定性・耐熱性評価法
1.2.1 評価法基礎
1.2.2 高分子製品の用途分野別熱劣化
1.3 加工安定性・耐熱性評価法実用技術の要点
1.3.1 加工安定性
1.3.2 耐熱(耐熱老化)性
2. 耐候性評価方法(木嶋芳雄)
1. はじめに
2. 耐候性およびその評価に関する一般概念
3. 耐候性の変化に影響する要因
(1) 材料因子
(2) エネルギー因子
(3) 環境因子
4. 耐候性試験の種類と方法
4.1 太陽を光源とした試験
4.2 人工光源を利用した試験
4.3 人工促進試験器の概要
(1) カーボンアーク灯式耐(光)候性試験機
(2) キセノンアークランプ式耐(光)候性試験機
(3) 紫外蛍光ランプ式耐候性試験機
(4) メタルハライドランプ式耐候性試験機
5. 耐候性評価項目と方法
6. おわりに
3. プラスチック中の安定剤の分析法(高山森)
1. 序
2. 未知試料中の安定剤の定性分析法の指針
2.1 概要
2.2 添加剤のポリマーからの分離濃縮法
(1) 溶剤抽出法
(2) 超臨界流体抽出(SFE)
(3) 再沈法
2.3 添加剤相互の分離法
(1) HPLC
(2) TCL
2.4 分離した成分の定性
(1) HPLCの各ピークの定性法
(2) TCLの各スポットの定性法
3. 既知試料中の安定剤の定性分析法の指針
3.1 概要
(1) ポリマーから分離せずに測定する方法
(2) ポリマーから分離して測定する方法
3.2 安定剤の定量に関する最近の進歩
(1) ガスクロマトグラフィーの進歩
3.3 製造プラントにおけるオンライン定量法の進歩
4. 主要安定剤別分析法
4.1 酸化防止剤
(1) フェノール系酸化防止剤
(2) イオウ系(チオエーテル系)酸化防止剤
(3) リン系酸化防止剤
4.2 紫外線吸収剤・光安定剤
(1) ベンゾトリアゾール系などの紫外線吸収剤
(2) ヒンダートアミン系光安定剤(HALS)
4.3 安定剤(ポリ塩化ビニルの脱塩酸防止剤)
(1) 金属石けん
(2) 有機すず化合物
索引
目次
第1章 高分子の劣化機構(劣化概論と自動酸化;熱劣化機構 ほか)
第2章 高分子の安定化機構と安定剤(安定化と安定剤;フェノール系安定剤 ほか)
第3章 高分子の安定化・各論(ポリプロピレン;ポリエチレン ほか)
第4章 高分子の安定性評価技術・促進法(評価の基礎技術と加工安定性評価法・耐熱性評価法;耐候性評価方法;プラスチック中の安定剤の分析法;主要安定剤分析法)
著者等紹介
大勝靖一[オオカツヤスカズ]
工学院大学応用化学科
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。