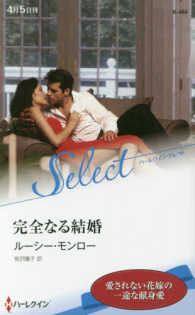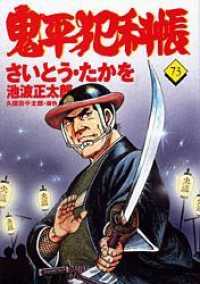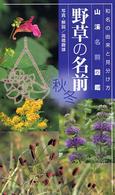出版社内容情報
【執筆者一覧(執筆順)】
古瀬一磨 エーザイ(株) 研究開発本部
戸田 浄 東京逓信病院 皮膚科
(現)戸田皮膚科クリニック 院長
阿部 進 (株)週刊粧業
(現)アーテックス(株) 相談役
依田晶男 厚生省 薬務局
垣原高志 明治薬科大学
室谷 勲 (株)資生堂 研究所
駒崎久幸 (株)資生堂 研究所
春沢文則 (株)資生堂 研究所
中野幹清 (株)資生堂 研究所
小石眞純 東京理科大学 薬学部
渡辺 靖 中央鉄道病院 皮膚科
永島敬士 中央鉄道病院 皮膚科
小川秀興 順天堂大学 医学部
服部道廣 順天堂大学 医学部
今井龍介 順天堂大学 医学部
(旧姓・有田伸吾)(株)津村順天堂 開発研究部
谷野伸吾 (現)(株)ツムラ LS商品開発研究所
江口泰輝 花王石鹸(株) 栃木第一研究所
(現)花王(株) 研究開発部門
鈴木 守 ポーラ化成工業(株) 横浜研究所
廣田 博 (株)伊勢半 生産本部研究所
(現)廣田技術士事務所 所長
松井建次 一丸ファルコス(株) 研究開発部
川崎通昭 高砂香料工業(株) 東京研究所
(現)日本香料協会 参与
中野 博 味の素(株) 中央研究所
佐川幸一郎 味の素(株) 中央研究所
(現)味の素(株) アミノサイイエンス研究所
伊吹忠之 旭化成工業(株) 医療事業部
(現)旭化成(株) 研究開発本部
松本宏一 日光ケミカルズ(株) 営業部
荻本賢治 三菱化成食品(株) SE販売本部
結城明文 三菱化成食品(株) SE販売本部
松下和男 阪本薬品工業(株) 研究所
塩山 浩 阪本薬品工業(株) 研究所
奥田 治 香料・生薬コンサルタント
高橋雅夫 日本化粧品科学研究会
(現)ビューティーサイイエンス学会 理事長
藤田泰宏 三井石油化学工業(株) 生物工学研究所
赤坂日出男 (株)資生堂 研究所
遠藤 寛 (株)ヤクルト本社 中央研究所
村尾澤夫 大阪府立大学 農学部
小西宏明 日本メナード化粧品(株) 研究本部
小田耕平 大阪府立大学 農学部
(現)東京工芸繊維大学 繊維学部
宮田暉夫 日本医用高分子材料研究所
(現)(株)高研 代表取締役社長
(執筆者の所属は,注記以外は1985年当時のものです)
【構成および内容】
<総論編>
第1章 いわゆる自然化粧品の考え方 古瀬一磨
1.はじめに
2.自然ブームの台頭
3.化粧品は天然物の利用から始まった
4.天然・自然を訴求する素材
5.天然・自然化粧品をめぐる論議
6.おわりに
第2章 皮膚と化粧品の関わりをどう考えるか 戸田 浄
1.化粧品をどのように定義するか
2.医薬部外品,大衆薬,民間薬など
3.安全な化粧品へのあまえ
4.化粧品の志向性
5.情報の公開
6.新しい皮膚生理学のすすめ
7.化粧品の効用
第3章 ハイテク時代の化粧品産業 阿部 進
1.はじめに
2.化粧品の産業規模と業界勢力等について
2.1 化粧品の産業規模
2.2 流通別勢力と製品別動向
3.化粧品産業におけるハイテクの現況
3.1 スキンケア
3.2 メークアップ
3.3 ヘアケア
3.4 フレグランスその他
4.流通,販促活動とハイテク
5.化粧品開発の今後の方向性(現場の見方)
6.化粧品産業とハイテクの関わり
第4章 産業政策懇談会の提言をどう生かすか 依田晶男
1.はじめに
2.化粧品産業の振興方策に関する提言の内容
2.1 許認可制度の改善
2.1.1 審査の必要性に応じた合理的な取り扱い
2.1.2 使用実績のある原料の公開措置
2.2 安定性の確保
2.2.1 安全性審査に必要なガイドラインの設定
2.2.2 消費者への情報提供
2.3 効能の評価
2.4 情報の提供
2.4.1 業界としての情報収集,提供体制の整備
2.4.2 指定成分表示制度における指定成分の見通し
2.4.3 広告表現規制の見直し
2.5 化粧品に関する科学の振興
2.6 国際的強調の推進
2.6.1 業界における国際的強調の推進
2.6.2 規制に関する国際的ハーモナイゼーション
3.提言への対応
3.1 許認可制度の改善
3.1.1 シリーズ化粧品における包括許可制の導入
3.1.2 一般的包括許可制の導入
3.1.3 化粧品原料基準の追加収載等
3.2 安全性の確保
3.3 効能の評価
3.4 情報の提供
3.5 化粧品に関する科学の振興
3.6 国際的強調の推進
4.おわりに
第5章 化粧品統計(指定統計大11号)の見方と読み方 阿部 進
1.はじめに
2.化粧品統計実施の経緯と調査内容
3.化粧品統計の読み方
第6章 化粧品と薬事法および関連法規 垣原高志
1.化粧品とは
1.1 使用対象
1.2 使用目的
1.3 使用方法
1.4 安全性
2.化粧品をつくるには
2.1 申請者の欠格事項
2.2 製造所の構造設備
2.3 責任技術者
2.4 製造する化粧品について
2.4.1 類別
2.4.2 販売名
2.4.3 成分分量または本質
2.4.4 製造方法
2.4.5 用法用量
3.新製品を製造する時
4.許可申請書の窓口
5.不良化粧品と不正表示化粧品
6.輸入化粧品
7.化粧品の委受託製造
8.再び,化粧品とは
9.関連法規
<製品編>
第7章 スキンケア用自然化粧品の動向 室谷 勲,駒崎久幸
1.はじめに
2.自然・天然化粧品とは
3.最近の市場における自然化粧品の動向
4.自然・天然化粧品に用いられる成分
4.1 自然・天然化粧品に用いられる成分
4.2 自然・天然化粧品に用いられる生薬
4.2.1 効能別に見た主な生薬のリスト
4.2.2 生薬の有用性
5.生薬の精製と有効性の確認
5.1 生薬の精製
5.1.1 抽出エキス
5.1.2 抽出エキスの分画精製
5.2 生薬の有効性とその成分について
5.2.1 ヘチマ
5.2.2 高麗人参
6.おわりに
第8章 スキンケア用化粧品の新しい乳化技術 春沢文則
1.はじめに
2.乳化の基礎
2.1 エマルジョンの転相温度(PIT)
2.2 油と水への界面活性剤の分配と乳化型
2.3 油-水-界面活性剤の相平衡
2.4 混合ミセルとHLBの加成性
2.5 エマルジョンの安定性
3.微粒子の精製方法
4.エマルジョンの形態
4.1 O/W型エマルジョン
4.2 W/O型エマルジョン
4.3 W/O/W型エマルジョン
4.4 マイクロエマルジョン
4.5 その他
第9章 メーキャップ用化粧品の新しい動向 中野幹清
1.はじめに
2.ツーウェイファンデーションの流行
2.1 白粉の機能を持ったファンデーション
2.2 シリコンで被覆処理した機能性粉体
2.2.1 反応性シリコンの種類
2.2.2 架橋重合開始触媒
2.2.3 反応温度および反応時間
2.2.4 粘体に対する被覆量
2.2.5 固形化に必要な結合油剤量
2.2.6 代表的な実施例
3.口紅とアイシャドーの多色化・ミニ化
3.1 有機色素の精製技術
3.2 アイカラーへの有機色素使用
4.メーキャップの色表示とコンピューター戦略
4.1 ファンデーションの色表示
4.2 ポイントメーキャップの号数表示
4.3 メーキャップシュミレーターの活用
5.おわりに
第10章 メーキャップ用化粧品に配合される新素材 小石眞純
1.はじめに
2.配合に期待される新素材のチェックポイント
2.1 顔料の新素材としてのポイント
2.2 新素材としての微小球と花粉
3.おわりに
第11章 養毛剤・育毛剤の動向 渡辺 靖,永島敬士
1.はじめに
2.対象疾患
3.養毛剤の評価について
3.1 ビタミン剤,栄養剤
3.2 血管拡張剤
3.3 代謝改善,毛根機能賦活剤
3.4 抗アンドロジェン作用物質
4.男性型脱毛症に対する養毛・育毛剤のFDA基準
5.わが国における養毛剤の評価方法について
第12章 養毛・育毛剤の評価法 小川秀興,服部道廣,今井龍介
1.はじめに
2.被検動物(材料)とその評価
2.1 in vivo 実験系による評価
2.1.1 動物を用いた評価法
2.1.2 人による評価法
2.2 in vitro による評価
2.2.1 細胞培養系による評価
2.2.2 組織培養系での評価
2.3 Hair growth の機序をふまえた生化学的検討
3.養毛剤・育毛剤の対象疾患
4.発毛・毛の発育等に関与する諸因子
5.マウス(C3H)背部毛による養毛・育毛剤の評価
第13章 浴用剤の動向 有田伸吾
1.浴用剤とは
2.浴用剤の発生
3.浴用剤の種類と機能
3.1 無機塩類浴剤
3.1.1 粉末状バスソルト
3.1.2 バスクリスタル
3.1.3 発泡性バスソルト
3.1.4 バスキューブ
3.2 薬用植物浴用剤
3.3 バブルバス・フォーミングバス
3.4 バスオイル
3.5 バスカプセル
3.6 バスリキッド
3.7 バスパフューム
3.8 酵素浴剤
4.おわりに
第14章 効能追求型浴剤の動向(炭酸ガス浴剤) 江口泰輝
1.温泉研究の新しい動き
2.炭酸ガス浴剤の効能
2.1 炭酸ガス浴剤の調製
2.2 炭酸ガスの血管拡張作用
2.3 入浴時の熱の移動
2.4 炭酸ガス浴剤の血流増加作用
2.5 炭酸ガス浴剤;血行促進作用がもたらす薬理効果について
3.炭酸ガス浴剤の市場動向
第15章 薬用化粧品 鈴木 守
1.はじめに
2.薬理化粧品開発の現状
2.1 法規定の概要
2.2 薬用化粧品の剤型と配合成分
2.2.1 薬用化粧品の剤型
2.2.2 薬用化粧品成分の配合事例
2.3 薬用化粧品の開発
2.3.1 新規成分を配合しない場合
2.3.2 新規成分を配合する場合
3.薬用化粧品の方向性と開発の問題点
3.1 効能,効果の範囲の拡大
3.2 新規成分の開発
3.2.1 チシロナーゼ阻害剤
3.2.2 保湿成分
3.2.3 朝鮮人参抽出成分
3.2.4 ニンニク抽出成分
3.2.5 紫根エキス
3.2.6 今後の薬用成分開発
<原料編 ?T>
第16章 新しい動植物性油脂 廣田 博
1.はじめに
2.化粧品原料としての油脂の有用性
3.動植物性油脂の特性とその有用性
3.1 油脂の粘度と展延性
3.2 油脂の紫外線吸収特性
3.3 油脂と水の混和性
3.4 植物性油脂とトコフェニロール
3.5 油脂類のエモリエント効果
4.新しい油脂,見直される油脂
4.1 アボカド類
4.2 月見草油
4.3 コメ胚芽油
4.4 カロブ胚芽油
4.5 ホホバ油
4.6 ヒマシ油
4.7 卵黄油
4.8 ミンク油
4.9 マムシ油
5.油脂のモディフィケーション
6.おわりに
第17章 新しい動植物抽出エキス 松井建次
1.はじめに
2.動植物エキス配合化粧品の動向
3.抗炎症作用
4.抗菌作用
5.抗チロシナーゼ作用
6.保湿作用および皮膚保護作用
6.1 コラーゲン
6.1.1 サクシニール化コラーゲン
6.1.2 ディスアミドコラーゲン
6.2 エラスチン
6.3 ケラチン
6.4 シルク
6.5 酸性ムコ多糖体(とくにヒアルロン酸)
7.その他
7.1 牛胎仔皮膚抽出物
7.2 仔牛血清抽出物
7.3 仔牛血清抽出物の限外濾過物
7.4 牛の乳腺抽出物
8.おわりに
第18章 においの人体に及ぼす影響 川崎通昭
1.はじめに
2.においによる情報伝達
3.他感物質(Allelo chemic)
4.森のにおいの効用
5.においの人体生理に及ぼす影響
6.いわゆるアロマテラピーについて
7.おわりに
第19章 アミノ酸系界面活性剤 中野 博,佐川幸一郎
1.はじめに
2.アミノ酸系界面活性剤
2.1 グルタミン酸系界面活性剤
2.1.1 N-アシルグルタミン酸塩
2.1.2 N-アシルグルタミン酸ジエステル類
2.1.3 ピロリドンカルボン酸系界面活性剤
2.2 リジン系界面活性剤
2.2.1 Nε-アシル-L-リジン
2.2.2 Nα-ジメチル-Nε-アシルリジン
2.3 その他のアミノ酸系界面活性剤
2.3.1 Nα-アシルアルギニンエステル塩
2.3.2 N-アシルザルコシン塩
2.3.3 アセチルアスパラギン酸-モノグリセリドエステル酸
2.3.4 N-アシル-Nメチル-β-アラニン塩
3.おわりに
第20章 卵黄レシチン 伊吹忠之
1.はじめに
2.卵黄レシチンと大豆レシチン
2.1 リン脂質組成
2.2 脂肪酸組成
3.卵黄レシチンの組成と製法
4.卵黄レシチンの特性と化粧品への利用
4.1 界面活性作用
4.2 リン脂質二分子膜形成能
4.3 抗酸化作用
5.レシチンの化粧品への応用特許
6.水素添加卵黄レシチン
7.水素添加卵黄レシチンの化粧品への利用
8.おわりに
第21章 大豆レシチン 松本宏一
1.はじめに
2.大豆レシチンの組成
3.大豆レシチンの特性
4.おわりに
第22章 ショ糖脂肪酸エステルの化粧品関係への応用について 荻本賢治,結城明文
1.はじめに
2.ショ糖エステル
3.ショ糖エステルの性質について
3.1 水溶性,油溶性
3.2 融点および安定性
3.3 ショ糖エステルのHLB値と乳化力
3.4 起泡性,浸透力
3.5 ショ糖エステルの機能
4.ショ糖エステルの安全性
5.化粧品への応用
5.1 クリーム類,ローション類への応用
5.1.1 乳化剤としての利用
5.1.2 基材としての利用
5.2 油性原料そのもの,あるいは油性原料のゲル化剤としての利用
5.2.1 棒状化粧品への応用
5.2.2 油脂類のゲル化剤としての利用
5.3 その他の化粧品への応用
5.3.1 シャンプー
5.3.2 その他の化粧品への応用
6.オーラルケアー製品への応用
7.おわりに
第23章 ポリグリセリン脂肪酸エステル 松下和男,塩山 浩
1.はじめに
2.ポリグリセリン
3.ポリグリセリン脂肪酸エステル
3.1 製法
3.2 組成
3.3 特性
4.おわりに
第24章 自然化粧品に多用される生薬とその有効性 奥田 治
1.多用される生薬
1.1 バーチ
1.2 ハマメリス
1.3 カモミル
1.4 ミルフォイル
1.5 ローズマリー
1.6 タイム
1.7 メリッサ
1.8 アルニカ
1.9 アロエ
1.10 むらさき
1.11 海藻
1.12 植物性油料および動物性油料,その他
1.12.1 ホホバ油
1.12.2 アボカド油
1.12.3 マーモット油,ミンク油
1.12.4 魚類の油脂
1.12.5 その他の基材
2.生薬の利用方法
2.1 素材の採算と保存処理
2.2 抽出作業
2.3 加工と製剤化
3.生薬の有効性
3.1 生薬成分の性状と機能
3.2 皮膚,毛髪に対する生薬の効果
3.3 生薬成分の有害性
<原料編 ?U>
第25章 バイオテクノロジー応用の化粧品原料-概説 高橋雅夫
1.はじめに
2.ニューバイオ
3.化粧品業界とバイオテクノロジー
4.バイテク応用の化粧品原料
4.1 色素
4.1.1 シコニン
4.1.2 アントシアニン
4.1.3 その他の植物性色素
4.2 香料
4.2.1 ニオイゼラニウム
4.2.2 たばこ香料
4.3 保湿剤
4.3.1 ヒアルロン酸
4.3.2 発酵代謝物
4.4 その他
5.おわりに
第26章 色 素 藤田泰宏
1.はじめに
2.植物細胞培養の概要
3.色素生産の研究例
3.1 アントシアニン類
3.2 フラボノイド類
3.3 カロチノイド類
3.4 キノン類
4.植物細胞培養の実用化例
4.1 液内細胞培養
4.2 生産性の向上
4.3 生産物の品質
5.おわりに
第27章 保湿剤(ヒアルロン酸) 赤坂日出男
1.はじめに
2.ストレプトコッカス属によるHAの生産
2.1 使用菌株の選択および分離同定
2.2 HAの生合成経路
押ィ魁ゞ欒?
2.4 培養
2.5 精製
2.6 発酵HAの構造,組成および物理化学的性質
3.HAの用途
3.1 化粧品への配合
3.2 眼料用薬品
3.3 その他の医薬品としての用途
4.おわりに
第28章 乳酸菌培養濾液(SE) 遠藤 寛
1.はじめに
2.SE液の調製
3.SEの皮膚保湿作用
3.1 角層水分に及ぼすSEの影響
3.2 SEの保湿因子
3.3 SEの皮膜形成因子
4.SEの抗酸化作用
4.1 SEによる過酸化脂質生成の抑制
4.2 SEの抗酸化性因子
4.3 SEの光防御効果
4.3.1 紫外線防御効果
4.3.2 光毒性反応抑制作用
5.皮表のpHに及ぼすSEの影響
6.皮膚細菌に及ぼすSEの影響
7.おわりに
第29章 プロテアーゼ 村尾澤夫,小西宏明,小田耕平
1.プロテアーゼとは
1.1 はじめに
1.2 エンドペプチターゼ(プロティナーゼ)
1.2.1 セリンプロティナーゼ
1.2.2 システィン(チオール)プロティナーゼ
1.2.3 アスパルティック(カルボキシル)プロティナーゼ
1.2.4 金属プロティナーゼ
1.3 エキソペプチダーゼ(ペプチダーゼ)
1.4 プロテアーゼの利用
2.プロテアーゼの化粧品への応用
2.1 配合目的
2.2 配合上の問題
2.3 処方例
第30章 天然高分子材料 宮田暉夫
1.はじめに
2.コラーゲン
3.エラスチン
4.ケラチン
5.おわりに
内容説明
本書は1985年に当時の自然回帰、天然物指向という消費者ニーズを受けて、医学、薬学、化粧品科学、原材料化学などの最高権威者に執筆を依頼して出来た論文集といえるものです。
目次
総論編(いわゆる自然化粧品の考え方;皮膚と化粧品の関わりをどう考えるか ほか)
製品編(スキンケア用自然化粧品の動向;スキンケア用化粧品の新しい乳化技術 ほか)
原料編1(新しい動植物性油脂;新しい動植物抽出エキス ほか)
原料編2(バイオテクノロジー応用の化粧品原料―概説;色素 ほか)
著者等紹介
高橋雅夫[タカハシマサオ]
日本化粧品科学研究会。(現)ビューティーサイエンス学会理事長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。