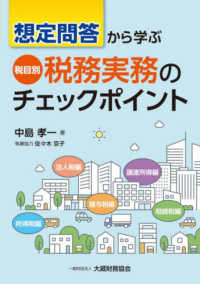出版社内容情報
執筆者一覧(執筆順)
大石道夫 東京大学 応用微生物研究所
(現) (財)かずさDNA研究所
岡本祐之 大阪大学 微生物病研究所
(現) おかもと医院
羽倉 明 大阪大学 微生物病研究所
矢野間俊介 横浜市立大学 医学部
奥田研爾 横浜市立大学 医学部
難波正義 川崎医科大学
(現) 新見公立短期大学
三村精男 大阪大学 工学部
(現) 山梨大学 工学部
草野友延 大正製薬(株) 総合研究所
(現) 東北大学大学院 生命科学研究所
村上浩紀 九州大学 農学部
源 良樹 味の素(株) 中央研究所
(現) (社)バイオ産業情報化コンソーシアム 生物情報解析研究センター
佐藤征二 協和発酵工業(株) 東京研究所
(現) 協和メデックス(株) 研究開発部
佐藤 裕 東洋醸造(株) 生化学研究所
石川陽一 (株)石川製作所
(現) エイブル(株)
横林康之 (株)林原生物化学研究所
(現) University of Jordan Hamdi Mango Center for Scientific Research
辻阪好夫 (株)林原生物化学研究所
飯島信司 名古屋大学 工学部
(現) 名古屋大学大学院 工学研究科
小林 猛 名古屋大学 工学部
(現) 名古屋大学大学院 工学研究科
山崎晶次郎 東レ(株) 基礎研究所
小林茂保 東レ(株) 基礎研究所
有村博文 (株)ミドリ十字 中央研究所
(現) インビトロテック(株)
John R.Birch Celltech Limited
小出 恬 住友製薬(株) 研究所
佐野恵海子 東レ(株) 基礎研究所
(現) プロティオス研究所
安井義晶 丸菱石油バイオケミカル(株)
(現) (株)堀場製作所&(株)バイオ・アプライド・システムズ
野崎周英 (現) (財)化学及び血清療法研究所 第一研究部
水野喬介 (現) (財)化学及び血清療法研究所 第一研究部
折田薫三 岡山大学 医学部
(現) (株)林原生物化学研究所 藤崎細胞センター
尾野雅義 中外製薬(株) 新薬研究所
野村 仁 中外製薬(株) 新薬研究所
(現) 中外製薬(株) 創薬研究担当
新津洋司郎 札幌医科大学
渡辺直樹 札幌医科大学
山本清高 東京都老人総合研究所 生物学部
(現) 東京都老人総合研究所 増殖分化制御
(執筆者の所属は,注記以外は1986年当時のものです。)
構成および内容
第1章 培養動物細胞による物質生産の現状と将来
1.微生物による有用物質生産の現状と問題点
2.動物細胞による有用生理活性物質の生産
3.おわりに
第2章 動物培養細胞の育種技術
1.細胞の株化(クローン化)技術
1.1 細胞株化の各種技術 岡本祐之・羽倉 明
1.1.1 はじめに
1.1.2 自然発生的な細胞の株化
1.1.3 ウィルスによる株化
1.1.4 癌遺伝子のどうにゅうによる株化
1.1.5 雑種(hybrid)形成を用いた株化
1.2 細胞融合による株化(ハイブリドーマ法)
1.2.1 はじめに
1.2.2 ハイブリドーマ作製の原理
1.2.3 細胞融合法の準備
1.2.4 実際の方法
1.2.5 T細胞ハイブリドーマ
1.2.6 モノクローナル抗体の応用
1.2.7 おわりに
1.3 ヒト細胞の株化技術 難波正義
1.3.1 はじめに
1.3.2 ヒト正常細胞の株化
1.3.3 ヒト腫瘍細胞の株化
1.3.4 ヒト腫瘍細胞培養の問題点-培養を成功させるために-
1.3.5 おわりに
2.細胞の物質生産能増強技術
2.1 分化誘導培養法による物質の生産 三村精男
2.1.1 はじめに
2.1.2 分化誘導培養法
2.1.3 分化誘導培養法の考え方による物質生産
2.1.4 分化誘導培養法によるマクロファージの大量調整と有用物質生産
2.1.5 単球性白血病細胞株(THP-1)の分化誘導培養法
2.1.6 ホルボールエステルによる物質生産増強
2.2 遺伝子操作による物質生産増強 草野友延
2.2.1 はじめに
2.2.2 動物細胞の遺伝子操作
2.2.3 プロモーター,エンハンサーと宿主の関係
2.2.4 DNAの細胞内導入法
2.2.5 選択系(Selection system)
2.2.6 おわりに
第3章 動物細胞の大量培養技術
1.動物細胞培養技術の現在の問題点 村上浩紀
1.1 はじめに
1.2 細胞に関するもの
1.3 培地に関するもの
1.3.1 無血清培地の利用
1.3.2 細胞増殖用培地と物質生産用培地
1.4 培養システムに関するもの
1.4.1 高密度培養の有用性
1.4.2 高密度培養の問題点
1.4.3 細胞の増殖と機能分化
1.5 細胞生産物の分離・精製に関するもの
2.無血清培養法 源 良樹
2.1 はじめに
2.2 無血清培地の意義
2.3 血清の細胞増殖能
2.4 無血清培地の研究
2.5 市販無血清培地
2.6 無血清培地研究の今後の展開
2.6.1 無血清培地の汎用性と特殊性
2.6.2 加熱殺菌可能培地の開発
2.6.3 異種動物由来増殖因子の代替
2.7 おわりに
3.細胞大量培養法
3.1 細胞大量培養法と培養装置の概要 佐藤征二
3.1.1 はじめに
3.1.2 動物細胞大量培養の特徴
3.1.3 培養器および培養法
3.1.4 大量培養の一般的プロセス
3.1.5 最適条件の設定
3.1.6 新しい培養法と培養装置の開発
3.1.7 おわりに
3.2 高密度培養法 佐藤 裕
3.2.1 はじめに
3.2.2 動物細胞の高密度生育環境条件
3.2.3 高密度培養の阻害要因
3.2.4 高密度培養の方法および装置
3.2.5 おわりに
3.3 培養槽内の改良とコンピュータ制御 石川陽一
3.3.1 培養装置
3.3.2 動物細胞培養のコンピュータ制御
3.3.3 おわりに
4.”ハムスター法”による大量培養技術と生理活性物質の生産 横林康之・辻坂好夫
4.1 はじめに
4.2 動物による有用生理活性物質の生産
4.3 ハムスターによるヒト細胞の大量増殖
4.4 ヒト細胞による有用物質の生産
4.4.1 誘発
4.4.2 分離精製
4.5 ”ハムスター法”の問題点と課題
4.6 おわりに
5.動物細胞培養関連機器 飯島信司・小林 猛
5.1 はじめに
5.2 機器類
5.2.1 クリーンベンチ
5.2.2 ふらん器
5.2.3 乾熱滅菌器と高圧滅菌器
5.2.4 蒸留水製造装置
5.2.5 遠心機
5.2.6 その他
5.3 培養に必要な器具
5.4 大量培養装置
5.4.1 浮遊性細胞の培養
5.4.2 高濃度培養
5.4.3 付着性細胞の培養
第4章 動物細胞生産有用物質の分離精製における問題点 山崎晶次郎・小林茂保
1.はじめに
2.分離精製技術
2.1 アフィニティークロマト法
2.2 HPLC(高速液体クロマト法)
3.有用物質の分離精製における問題点
3.1 分離精製工程上の問題点
3.1.1 細胞培養条件がおよぼす分離精製への影響
3.1.2 大量処理技術
3.1.3 カラムクロマト操作上の問題点
3.2 分離精製される物質の性状に基づく問題点
3.2.1 物質の追跡
3.2.2 物質の不均一性
3.2.3 高い疎水性のおよぼす影響
3.3 分離精製される物質の使用目的上の問題点
3.3.1 培地および培養細胞などの構成成分の混入
3.3.2 分離精製中の汚染物混入防止
3.4 遺伝子組換えを目的とした有用物質の精製
4.おわりに
第5章 動物細胞大量培養による有用物質生産の現状 有村博文
1.ウロキナーゼ 有村博文
1.1 はじめに
1.2 ヒト腎細胞を用いてのウロキナーゼ産生
1.2.1 培養方法
1.2.2 細胞
1.2.3 ヒト腎細胞の培養で得られたPAの性状
1.3 遺伝子組換えによるウロキナーゼ産生
1.3.1 大腸菌を用いてのウロキナーゼ産生
1.3.2 組換え動物細胞を用いてのウロキナーゼ産生
2.モノクローナル抗体 Jhon.R.Birch
2.1 はじめに
2.2 モノクローナル抗体の製造方法
2.3 均一懸濁培養システム
2.4 エアーリフトリアクター
2.4.1 エアーリフトリアクター
2.4.2 エアーリフト培養法による抗体産生
2.5 連続培養
2.6 細胞フィードバックによる連続培養
2.7 抗体の回収と精製
2.8 血清無添加の培養培地
2.9 おわりに
3.α型インターフェロン 小出 恬
3.1 インターフェロンの分類
3.2 α型インターフェロン
3.3 医薬品としてIFN製剤が満たすべき条件
3.4 α型インターフェロンの培養生産
3.4.1 白血球インターフェロン(Hu-IFN-α(Le))
3.4.2 リンパ芽球インターフェロン(Hu-IFN-α(Ly))
3.5 リンパ芽球インターフェロン製造の実際
3.6 おわりに
4.β型インターフェロン 佐野恵海子・小林茂保
4.1 はじめに
4.2 β型IFNの性状
4.3 β型IFNの一般的産生方法
4.3.1 プライミング処理
4.3.2 超誘発法(Superinduction)
4.3.3 紫外線照射法(UV法)
4.4 臨床用β型IFNの量産法
4.4.1 使用細胞
4.4.2 培養装置
4.5 β型IFNの生産の現状と問題点
4.5.1 動物細胞培養による生産の現状と問題点
4.5.2 遺伝子組換え微生物による生産の現状と問題点
4.6 今後への展望
5.γ型インターフェロン 有村博文
5.1 はじめに
5.2 ヒト白血球を用いてのγ型インターフェロンの産生
5.2.1 産生方法
5.2.2 ヒト白血球由来IFN-γの性状
5.3 遺伝子組換えによるIFN-γ産生
5.3.1 遺伝子組換え大腸菌によるIFN-γ産生
5.3.2 遺伝子組換え動物細胞によるIFN-γ産生
6.インターロイキン2(IL-2) 安井義晶
6.1 はじめに
6.2 IL-2の性状と生物活性
6.3 IL-2の遺伝子
6.4 IL-2の量産
6.4.1 動物細胞大量培養による量産
6.4.2 遺伝子組換え微生物による生産
6.4.3 IL-2量産の現状と将来
6.5 IL-2の精製と活性測定
6.6 IL-2量産の現状と将来
6.7 おわりに
7.B型肝炎ワクチン 野崎周英・水野喬介
7.1 はじめに
7.2 HBV
7.3 宿主染色体にHBV,DNAを組み込む方法
7.4 SV40を利用する方法
7.5 ウシパピローマウィルスを利用する方法
7.6 ワクシニアウィルスを利用する方法
7.7 ヒト肝ガン細胞を利用する方法
7.8 おわりに
8.OH-1(CBF) 折田薫三
8.1 はじめに
8.2 OH-1の産生
8.3 細胞障害性活性およびIFN活性の測定
8.4 OH-1の分離,精製および各種OH-1標品の調製
8.5 OH-1の物性
8.6 各種OH-1標品のヒト細胞株に対する細胞障害効果
8.7 OH-1の in vivo での抗腫瘍効果
8.7.1 移植腫瘍に対する抗腫瘍効果
8.7.2 OH-1の転移抑制効果
9.CSF 尾野雅義・野村 仁
9.1 はじめに
9.2 産生細胞(T3M-5)について
9.3 細胞培養条件-特に血清について-
9.4 ローラーボトル方式によるT3M-5の培養
9.4.1 凍結保存細胞から大量培養への展開
9.4.2 ローラーボトル培養法でのCSF生産
9.5 培養液からのCSFの精製
9.6 おわりに
10.TNF 新津洋司郎・渡辺直樹
10.1 はじめに
10.2 ヒトTNFの作製
10.3 ヒトTNFの genomic gene structure
10.4 ヒトTNFの一次構造と物性
10.5 ヒトTNFの抗腫瘍作用
10.5.1 in vitro cytotxicity
10.5.2 in vivo の抗腫瘍効果
10.6 抗腫瘍効果の作用機序
10.6.1 receptor
10.6.2 壊死
10.6.3 免疫系
10.7 副作用
10.8 臨床応用への展望
10.9 おわりに
第6章 動物細胞株入手・保存法とセルバンク 山本清高
1.はじめに
2.動物細胞株の入手法
2.1 他の機関からの入手
2.2 購入
2.3 研究室内での調製
3.細胞凍結保存法
3.1 機材
3.1.1 凍結装置
3.1.2 凍結保存容器
3.1.3 アンプルシーラー
3.2 準備
3.2.1 器具
3.2.2 試薬
3.3 手順
3.3.1 細胞の凍結手順
3.3.2 凍結保存細胞の融解手順
3.4 改良法の結果
3.4.1 凍結,融解後の生存率,付着率
3.4.2 改良法の長所
3.4.3 凍結細胞の増殖能および分裂寿命(life span)への影響
3.5 凍結回数の影響
3.6 血管内皮細胞の凍結保存
3.7 各種細胞の凍結条件
3.8 生存率と付着率の関係
4.セルバンク(細胞銀行)
内容説明
最先端技術といえる“動物細胞大量培養技術”の現状と展望および各種有用物質生産へのアプローチの現状を、各分野の研究・開発の第一人者が解説。
目次
第1章 培養動物細胞による物質生産の現状と将来
第2章 動物培養細胞の育種技術
第3章 動物細胞の大量培養技術
第4章 動物細胞生産有用物質の分離精製における問題点
第5章 動物細胞大量培養による有用物質生産の現状
第6章 動物細胞株入手・保存法とセルバンク
著者等紹介
大石道夫[オオイシミチオ]
東京大学応用微生物研究所を経て、現、(財)かずさDNA研究所
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。