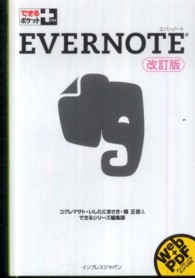出版社内容情報
★近い将来の実用化を念頭に置き,第一線の研究内容を一挙紹介!
★基礎理論,作成技術,応用展開を明快に解説した「有機薄膜太陽電池」の集大成!
★有機EL素子との相違とアナロジーおよび将来性豊かな有機分子エレクトロニクスへの展開を詳述!
--------------------------------------------------------------------------------
「まえがき」より抜粋
クリーンで無尽蔵の太陽光発電の拡大が待望まれているが,現行のシリコン太陽電池は他の電源コストに比べ太刀打ちできない高価格がネックになっている。独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が昨年6月に発表した2030年に向けた太陽光発電ロードマップ(PV2030)によると,2030年までに7円/kWhに発電コストを下げ,家庭用電力の1/2(全電力の10%)を太陽光発電でまかなう計画である。これに対応できる有力候補の一つが有機薄膜太陽電池である。
有機薄膜太陽電池の特長は,シリコン太陽電池や色素増感太陽電池(グレッツェルセル)よりもはるかに軽量で低コスト,しかも加工性が良く,いかなる形状や用途にも対応可能である。資源的制約もなく材料的にもエネルギー的にも環境調和型となりうる。
本書は,学問的な基礎を光合成の初期過程の理論におき,メカニズム的に全く逆のプロセスでありながら材料面と素子構造面で共通の基盤を持つ有機EL素子と対比しつつ,光電変換効率と応用研究の面で先行しているグレッツェルセルと,将来の実用化に備えて材料合成と大量生産プロセスにも配慮し,未来の情報デバイスや宇宙太陽光発電への展開も視野に入れた現時点での有機薄膜太陽電池の最新技術の集大成である。
変換効率5%を越えた有機薄膜太陽電池は,すでに実用化段階に入っている有機EL素子の10年前の状況に似ているといわれ,今後,指数関数的な発展を前に,本書がmile stoneとしての役割を果たし,有機薄膜太陽電池の基礎理論の理解,最新の研究開発動向の把握,そして新技術の開発と新ビジネスの開拓の一助となれば誠に幸いである。
2005年10月 監修者を代表して 上原赫
--------------------------------------------------------------------------------
上原赫 京都大学 エネルギー理工学研究所 客員教授;大阪府立大学名誉教授
吉川暹 京都大学 エネルギー理工学研究所 教授
三室守 京都大学 大学院地球環境学堂/大学院人間・環境学研究科 教授
内藤裕義 大阪府立大学大学院 工学研究科 電子・数物系専攻 教授
藤枝卓也 フジエダ電子出版(有) 代表取締役;京都大学 エネルギー理工学研究所 分子集合体設計研究室 非常勤職員
小夫家芳明 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授
柴田麗子 立命館大学 理工学部 助手
民秋均 立命館大学 理工学部 教授
永田衞男 名古屋工業大学 大学院VBL部門 研究員
南後守 名古屋工業大学 大学院工学研究科 教授
大佐々崇宏 大阪大学 太陽エネルギー化学研究センター
松村道雄 大阪大学 太陽エネルギー化学研究センター 教授
平本昌宏 大阪大学 大学院工学研究科 助教授
内田聡一 新日本石油(株) 研究開発本部 中央技術研究所 シニアスタッフ
錦谷禎範 新日本石油(株) 研究開発本部 中央技術研究所 副所長
高橋光信 金沢大学 大学院自然科学研究科 物質工学専攻 教授
村田和彦 (株)日本触媒 事業企画室 電子・情報材料開発グループ グループリーダー
中村潤一 (株)日本触媒 研究開発部 先端技術研究所 電子情報材料研究部 研究員
阪井淳 松下電工(株) 先行技術開発研究所 副参事
安達淳治 松下電工(株) 先行技術開発研究所 微細加工プロセス研究室
今堀博 京都大学 大学院工学研究科 分子工学専攻 教授
梅山有和 京都大学 大学院工学研究科 分子工学専攻 助手
八木繁幸 大阪府立大学大学院 工学研究科 物質・化学系専攻 応用化学分野 助教授
中澄博行 大阪府立大学大学院 工学研究科 物質・化学系専攻 応用化学分野 教授
上田裕清 神戸大学 工学部 応用化学科 教授
瀬川浩司 東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 助教授
山?ア康寛 オリヱント化学工業(株) 研究部 部長
大野敏信 大阪市立工業研究所 有機材料課 研究副主幹
中村洋介 群馬大学 大学院工学研究科 ナノ材料システム工学専攻 助教授
今野高志 群馬大学 大学院工学研究科 ナノ材料システム工学専攻
西村淳 群馬大学 大学院工学研究科 ナノ材料システム工学専攻 教授
荒木圭一 信州大学 繊維学部 機能高分子学科 谷口研究室 研究員
市川結 信州大学 繊維学部 機能高分子学科 谷口研究室 助手
谷口彬雄 信州大学 繊維学部 機能高分子学科 谷口研究室 教授
森竜雄 名古屋大学 工学研究科 電子情報システム専攻 助教授
小野田光宣 兵庫県立大学 大学院工学研究科 教授
福田猛 京都大学 化学研究所 教授
辻井敬亘 京都大学 化学研究所 助教授
伊?ア昌伸 大阪市立工業研究所 電子材料課 無機薄膜研究室 研究副主幹
城田靖彦 福井工業大学 環境・生命未来工学科 教授
大森裕 大阪大学 先端科学イノベーションセンター 教授
Mark Thompson University of Southern California Department of Chemistry
Biwu Ma University of Southern California Department of Chemistry
Peter Djurovich University of Southern California Department of Chemistry
Jian Li University of Southern California Department of Chemistry
Elizabeth Mayo University of Southern California Department of Chemistry
Sterphen Forrest Princeton University Department of Electrical Engineering
Barry Rand Princeton University Department of Electrical Engineering
Rhonda Salzman Princeton University Department of Electrical Engineering
近松真之 (独)産業技術総合研究所 光技術研究部門 分子薄膜グループ 研究員
坂口幸一 (独)産業技術総合研究所 光技術研究部門 分子薄膜グループ 特別研究員
吉田郵司 (独)産業技術総合研究所 光技術研究部門 分子薄膜グループ 主任研究員
阿澄玲子 (独)産業技術総合研究所 光技術研究部門 分子薄膜グループ グループリーダー
八瀬清志 (独)産業技術総合研究所 光技術研究部門 副研究部門長
中野谷一 千歳科学技術大学 大学院光科学研究科
安達千波矢 千歳科学技術大学 光科学部 物質光科学科 教授
横山正明 大阪大学 大学院工学研究科 生命先端工学専攻 教授
外岡和彦 (独)産業技術総合研究所 エレクトロニクス研究部門 主任研究員
吉田司 岐阜大学 大学院工学研究科 環境エネルギーシステム専攻 助教授
雉鳥優二郎 桐蔭横浜大学 大学院工学研究科
宮坂力 桐蔭横浜大学 大学院工学研究科 教授
村上拓郎 スイス連邦工科大学(EPFL) 博士研究員
手島健次郎 ペクセル・テクノロジーズ(株) 特任研究員
篠原真毅 京都大学 生存圏研究所 助教授
松本紘 京都大学 生存圏研究所 教授
--------------------------------------------------------------------------------
目次
序章 有機光電変換系の可能性と課題(吉川暹,上原赫)
1. はじめに
2. 有機光電変換系の可能性
2.1 有機薄膜太陽電池研究の進歩
2.2 色素増感太陽電池(Grätzelセル)の進展
2.3 有機EL素子における進歩
2.4 光合成系研究の進展
2.5 超高効率化への期待
3. おわりに
第1章 基礎理論と光合成
1. 光合成細菌における光電変換反応の機構とそれを支える反応場 (三室守)
1.1 はじめに
1.2 光合成細菌の誕生と種類
1.3 光化学反応中心複合体
1.4 紅色光合成細菌の光化学反応場
1.5 紅色光合成細菌の光電変換反応
1.6 アンテナ系の構造と機能
1.7 反応場の単一性と生物の多様性
2. バクテリアの光合成初期過程における励起子移動と電荷分離 (上原赫)
2.1 はじめに
2.2 励起子生成と移動
2.2.1 紅色光合成細菌のアンテナ色素系の励起子移動
2.2.2 カロテノイドによる励起三重項状態のBChlの消光
2.2.3 緑色イオウ光合成細菌のクロロゾーム
2.2.4 コヒーレントなエネルギーと反応中心への移動
2.3 電荷分離と再結合の速度
2.4 おわりに
3. 有機半導体の電荷輸送とその機構 (内藤裕義)
3.1 はじめに
3.2 有機結晶半導体
3.3 電荷移動度評価法
3.4 有機アモルファス半導体
3.5 まとめ
4. 有機薄膜太陽電池の基礎理論の概念 (藤枝卓也,吉川暹)
4.1 太陽電池セルの等価回路
4.2 分子性固体の電子構造
4.3 非局在化
4.4 バンド伝導
4.5 出力電圧と擬フェルミ準位
4.6 有機薄膜太陽電池の構造
4.7 おわりに
5. 人工光合成系の構築 (小夫家芳明)
5.1 はじめに
5.2 光合成を構成するシステム-光捕集アンテナと光合成反応中心
5.3 電荷分離中心機能体の構築
5.4 環状光捕集機能体
5.5 展開
6. アンテナ色素の合成とモデル系の構築 (柴田麗子,民秋均)
7. 光合成細菌の光電変換材料を用いたデバイスへの応用 (永田衞男,南後守)
7.1 はじめに
7.2 光合成膜での光電変換
7.3 アンテナ系タンパク質/色素複合体の光電変換能
7.3.1 LB膜法
7.3.2 SAM法
7.3.3 脂質二分子膜への組織化
7.3.4 モデルタンパク質を用いた光電変換機能
7.4 まとめ
第2章 有機薄膜太陽電池のコンセプトとアーキテクチャー
1. 有機薄膜太陽電池の原理と新アーキテクチャーの可能性 (上原赫,吉川暹)
1.1 はじめに
1.2 有機薄膜太陽電池の原理と光合成の初期過程
1.3 最近の有機薄膜太陽電池の素子構造と新アーキテクチャーの可能性
1.3.1 有機へテロ接合素子
1.3.2 バルクヘテロ接合型素子
1.3.3 カーボンナノチューブを用いたバルクヘテロ接合型素子
1.3.4 ナノコンポジット型素子
1.3.5 D-σ-A色素と酸化亜鉛ナノピラー電極を組み合わせた3次元素子
1.3.6 デュアルヘテロ接合(タンデム)型素子
1.3.7 電極の外部に色素増感層を持つ素子構造
1.4 おわりに
2. 有機ヘテロ接合型薄膜太陽電池 (大佐々崇宏,松村道雄)
2.1 はじめに
2.2 初期の有機薄膜太陽電池
2.3 有機へテロ接合型太陽電池
2.4 有機へテロ接合型素子における動作機構
2.5 有機/有機界面の微細構造制御
2.6 おわりに
3. p-i-n接合を持つ有機薄膜太陽電池 (平本昌宏)
3.1 はじめに
3.2 ナノ構造制御された共蒸着層をi層として持つp-i-n接合型セル
3.3 非常に厚い透明NTCDA保護層によるショート問題の解決
3.4 NTCDA蒸着膜のpn 制御とオーミック接合形成
3.5 長期安定性試験
3.6 おわりに
4. バルクヘテロ接合型有機薄膜太陽電池 (内田聡一,錦谷禎範)
4.1 はじめに
4.2 バルクヘテロ接合型太陽電池のしくみ
4.3 光電変換特性モデル
4.4 低分子系バルクヘテロ接合型太陽電池の実際
4.4.1 CuPc:C60の共蒸着膜をバルクヘテロ接合層とする太陽電池
4.4.2 CuPc:PTCBIの共蒸着膜をバルクヘテロ接合層とする太陽電池
4.5 共蒸着により得られる低分子系バルクヘテロ接合膜の構造
4.6 おわりに
5. 共役系ポリマーを用いた有機薄膜太陽電池 (高橋光信,村田和彦,中村潤一)
5.1 はじめに
5.2 仕事関数の異なる電極で有機物固体を挟んだ時の閉回路平衡状態における有機膜にかかる電位プロフィール
5.3 バルクヘテロジャンクション型太陽電池
5.3.1 低分子混合型太陽電池
5.3.2 共役系高分子混合型太陽電池
5.4 共役系高分子浸透構造型太陽電池
5.5 開放光電圧を支配する因子
6. ナノコンポジット型有機太陽電池及びスクリーン印刷法の適用 (阪井淳,安達淳治)
6.1 はじめに
6.2 ナノコンポジット型有機太陽電池の発電原理
6.3 化合物半導体ナノ結晶の生成
6.4 ナノコンポジット太陽電池の特徴
6.5 ナノコンポジット有機太陽電池の課題
6.6 有機薄膜太陽電池へのスクリーン印刷法の適用
6.7 おわりに
7. 分子素子型有機薄膜太陽電池 (今堀博,梅山有和)
7.1 はじめに
7.2 色素増感・バルクヘテロ接合型太陽電池
7.2.1 ポルフィリンデンドリマーとフラーレンを用いた有機太陽電池
7.2.2 ポルフィリン修飾金ナノ微粒子とフラーレンを用いた有機太陽電池
7.3 今後の展開
第3章 有機薄膜太陽電池:光電変換材料
1. 有機デバイス用色素の基本特性 (八木繁幸,中澄博行)
1.1 緒言
1.2 電子移動ドナー-アクセプター対の構築
1.3 ジアリール尿素骨格を連結部位とする亜鉛ポルフィリン二量体とビオロゲンとの錯形成を介した光誘起電子移動
1.4 亜鉛ポルフィリン上に収斂的な双極子配列を有するビオロゲン認識レセプターの開発
1.5 長寿命電荷分離を目指したポルフィリンへテロ二量体型ビオロゲン認識レセプター
1.6 結言
2. 有機色素の分子配向制御 (上田裕清)
2.1 はじめに
2.2 エピタキシャル成長とは
2.3 有機色素のエピタキシャル成長
2.4 高分子配向膜(PTFE摩擦転写膜)を基板とする有機色素の配向制御
3. ポルフィリンJ会合体のナノ構造制御と励起子物性 (瀬川浩司)
3.1 はじめに
3.2 ポルフィリンJ会合体の吸収スペクトル
3.3 非水溶性ポルフィリンJ会合体Langmuir-Blodgett膜の作成
3.4 非水溶性ポルフィリンJ会合体Langmuir-Blodgett膜の構造
3.5 非水溶性ポルフィリンJ会合体ヘテロLangmuir-Blodgett膜
3.6 自己組織化によるポルフィリンJ会合体単分子膜の酸化チタン上への形成と色素増感太陽電池への応用
3.7 まとめ
4. μ-オキソ架橋型フタロシアニン二量体の開発 (山?ア康寛)
4.1 機能性フタロシアニン色素
4.2 太陽電池で検討されるフタロシアニン色素
4.3 μ-オキソ架橋型フタロシアニン二量体
4.3.1 μ-オキソ架橋型ホモ金属(III)フタロシアニン二量体
4.3.2 μ-オキソ架橋型ヘテロ金属(III)フタロシアニン二量体
4.3.3 感光体一次電気特性評価
4.4 D-σ-A型色素モデル化合物としてのμ-オキソ架橋型フタロシアニン二量体
4.4.1 デバイス化
4.4.2 評価方法と結果
4.5 「D-σ-A」型フタロシアニン二量体の選択的合成
4.5.1 μ-オキソ架橋型ヘテロ金属フタロシアニン二量体
4.5.2 μ-オキソ架橋型ヘテロ金属ミクストダイマーへの応用
4.5.3 光電変換材料等の光機能性材料への応用
4.6 結語
5. 電子活性な有機フラーレンの合成と性質 (大野敏信)
5.1 はじめに
5.2 フラーレンの修飾
5.3 電子活性な有機フラーレン
5.3.1 C60-ドナー連結系:トリアリールアミンを有するメタノフラーレンの合成と性質
5.3.2 C60-アクセプター連結系
5.4 まとめ
6. フラーレン反応化学:材料設計に使うフラーレン修飾反応 (中村洋介,今野高志,西村淳)
6.1 はじめに:フラーレンの物性と反応性
6.2 フラーレンと機能要素材料(または材料表面)との結合形成に利用される反応
6.2.1 Prato反応
6.2.2 Bingel反応
6.2.3 Diels-Alder反応及び関連反応
6.2.4 その他
6.3 材料の機能化に用いるビルディングブロックとしてのフラーレン試薬
6.3.1 フラーレン部位と特定の官能基の間に起こり得る反応による制約
6.3.2 材料表面との反応を想定した官能基の導入
6.4 おわりに
第4章 有機薄膜太陽電池:キャリアー移動材料と電極
1. 1Dナノ材料の創製とエネルギー変換材料への応用 (吉川暹)
1.1 はじめに
1.2 1Dナノ材料の光電変換系における利用
1.3 1Dナノ材料の創製
1.4 TiO2ナノワイヤーの色素増感太陽電池への応用
1.5 部分ナノワイヤー化TiO2の色素増感太陽電池への応用
1.6 まとめ
2. キャリア輸送性有機材料の開発とその応用 (荒木圭一,市川結,谷口彬雄)
2.1 はじめに
2.2 高移動度電子輸送材料
2.3 Bpy-OXDの電子輸送性クラッド層への応用
2.4 高耐熱性ホール輸送材料とウェットプロセスへの応用
2.5 まとめ
3. ホールブロッキング材料の性能と積層効果 (森竜雄)
3.1 はじめに
3.2 ホールブロッキング材料の多結晶化現象
3.3 BAlqとBCPのホールブロッキング性の比較
3.4 BCPのホールブロッキング性
3.5 BAlqのホールブロッキング性の消失(再結合領域の移動)
3.6 まとめ
4. 導電性高分子・フラーレンの泳動電着 (小野田光宣)
4.1 はじめに
4.2 導電性高分子の溶液物性
4.3 導電性高分子コロイド懸濁液の調整
4.4 MEHPPVおよびC60懸濁液
4.5 MEHPPV- C60複合懸濁液
4.6 MEHPPV- C60複合膜
4.7 まとめ
5. 新しい表面:濃厚ポリマーブラシ (福田猛,辻井敬亘)
5.1 はじめに
5.2 ポリマーブラシの精密合成:表面開始リビングラジカル重合
5.3 濃厚ポリマーブラシの構造と物性
5.4 おわりに
6. 有機薄膜型ならびに酸化物ヘテロ接合型太陽電池への酸化亜鉛の応用 (伊?ア昌伸)
6.1 酸化亜鉛(ZnO)
6.2 ZnO層の電気化学的形成
6.3 硝酸還元反応を用いた半導体ZnO膜の陰極析出
6.4 室温紫外発光ZnO膜のヘテロエピタキシャル陰極析出
6.5 硝酸還元反応を用いた酸化亜鉛層の化学析出
6.6 有機薄膜型太陽電池用ZnOナノピラー電極
6.7 ZnOを用いた酸化物系ヘテロ接合型太陽電池
第5章 有機薄膜太陽電池:有機ELと有機薄膜太陽電池の周辺領域
1. アモルファス分子材料を用いる有機EL素子 (城田靖彦)
1.1 はじめに
1.2 有機EL素子用アモルファス分子材料
1.2.1 正孔注入材料
1.2.2 正孔輸送材料
1.2.3 電子輸送材料
1.2.4 正孔ブロッキング材料
1.2.5 発光材料
1.3 アモルファス分子材料を用いる有機EL素子の作製と性能
1.3.1 新しい正孔注入材料,正孔輸送材料を用いた緑色発光素子
1.3.2 青紫色発光有機EL素子
1.3.3 赤色発光有機EL素子
1.3.4 多色発光有機EL素子
1.4 おわりに
2. フレキシブル有機EL素子とその光集積デバイスへの応用 (大森裕)
2.1 はじめに
2.2 ウエットプロセスで作製した高輝度・高効率燐光素子
2.2.1 緑色燐光素子
2.2.2 赤色燐光素子
2.3 有機ELの光集積デバイスへの応用
2.4 まとめ
3. OLEDs and Solar Cells: Novel Device Structures and Materials Designed for Each Application
有機発光ダイオードと有機薄膜太陽電池:新素子構造と材料設計
(Mark Thompson, Biwu Ma, Peter Djurovich, Jian Li, Elizabeth Mayo, Stephen Forrest, Barry Rand, Rhonda Salzman,上原赫)
4. 有機ELから光電変換素子へ-発光層と受光層を有する有機複合素子の開発-
(近松真之,坂口幸一,吉田郵司,阿澄玲子,八瀬清志)
4.1 はじめに
4.2 光応答型有機EL素子
4.3 光応答型有機EL素子の高効率化
4.4 おわりに
5. ビススチリルベンゼン誘導体を活性層とする有機DFBレーザーの発振特性 (中野谷一,安達千波矢)
6. 有機薄膜における光・電気双方向変換を利用した光機能デバイス (横山正明)
6.1 はじめに
6.2 有機/金属界面現象としての光電流増倍現象
6.2.1 有機薄膜における光電流増倍現象
6.2.2 光電流増倍機構
6.3 光電流増倍現象を利用した新規光デバイス
6.3.1 光-光変換デバイス
6.3.2 光増幅デバイス
6.3.3 光スイッチング
6.3.4 光演算デバイス
6.4 おわりに
第6章 有機薄膜太陽電池:応用の可能性
1. 透明太陽電池の研究・開発 (外岡和彦)
1.1 太陽光エネルギーの利用
1.2 透明な太陽電池のための材料
1.3 透明な半導体pn接合から太陽電池へ
2. デザイン自在のカラフル太陽電池:電気自動車用太陽電池塗装をめざして (吉田司)
3. プラスチック色素増感太陽電池の高効率化とモジュール化 (雉鳥優二郎,宮坂力)
3.1 はじめに
3.2 プラスチック電極に用いる半導体の低温成膜法
3.3 エネルギー変換効率の改善
3.4 プラスチックDSCモジュールの製作
3.5 今後の開発に向けて
4. 色素増感半導体を用いる光キャパシタの開発 (宮坂力,村上拓郎,手島健次郎)
4.1 はじめに
4.2 光充電機能を持つキャパシタ“光キャパシタ”
4.3 光キャパシタの充放電性能
4.4 おわりに
5. 導電性ポリマーを用いたエネルギー貯蔵型色素増感太陽電池 (瀬川浩司)
5.1 色素増感太陽電池とエネルギー貯蔵
5.2 エネルギー貯蔵型色素増感太陽電池の構造
5.3 導電性高分子を用いたES-DSSC
5.4 セパレータの改良
5.5 電荷蓄積電極の改良
5.6 おわりに
6. 宇宙太陽光発電長期計画 (篠原真毅, 松本紘)
6.1 はじめに
6.2 宇宙太陽発電所SPS
6.3 SPSに必要な太陽電池
6.4 SPS長期計画
6.5 おわりに
付録
用語の解説
仕事関数
目次
序章 有機光電変換系の可能性と課題
第1章 基礎理論と光合成
第2章 有機薄膜太陽電池のコンセプトとアーキテクチャー
第3章 有機薄膜太陽電池:光電変換材料
第4章 有機薄幕太陽電池:キャリアー移動材料と電極
第5章 有機薄膜太陽電池:有機ELと有機薄膜太陽電池の周辺領域
第6章 有機薄膜太陽電池:応用の可能性
付録
著者等紹介
上原赫[ウエハラカク]
京都大学エネルギー理工学研究所客員教授。大阪府立大学名誉教授
吉川暹[ヨシカワススム]
京都大学エネルギー理工学研究所教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 中國倫理思想の研究