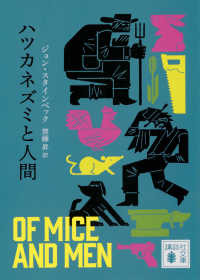出版社内容情報
★ 環境水浄化技術の基礎と実際の浄化に使われている材料・システムをまとめた1冊!
★ あらゆる浄化技術を網羅!
★ 第一線の研究・開発者が最新の情報を執筆!
【はじめに】
水環境の改善をはかる場合,その基準として水量が豊富であるかどうか,水質は清浄かどうか,生物にとって棲みやすいのか,といった視点が挙げられるが,現実の問題としては,とくに水質汚染が問題になることが多い。とりわけ都市域には,水量そのものは豊富にあるが,水質が人間にとっても生物にとっても好ましいものとはなっていないからである。環境省が毎年実施している全国調査によると,BOD,CODの環境基準の達成率という尺度でみても淡水域,海域ともに横ばい状態が何年も続いており,有機汚染問題は相変わらず未解決である。そればかりか,都市河川や湖沼・内湾の閉鎖性水域のなかには,かえって悪化しているところもある。水質改善を図るために,公共下水道・浄化槽など各種の処理施設の整備が進められているにもかかわらず顕著な水質改善効果が現れていない。根底にはこれらが万能ではなく,その機能には限界があるということである。たとえば,現在の下水道システムに起因する問題,すなわち,集水方式が合流式なのか分流式なのか,は水質環境と深く関わっている。汚濁発生源は,住宅,工場・事業場など個々に点源として明確に把握できるものだけでなく,路面,農地,山林など面源として存在するものもある。1970年代以降各種の整備事業によって点源負荷はかなりの程度改善されてきているが,残る面源負荷については,これを担当する部署自体が明確にされておらず等閑に付されてきたというのが実態であろう。このような背景のもとで河川・湖沼・海域などのいわゆる環境水を浄化することはいよいよ焦眉の課題となってきている。しかし,その際単に環境水の直接浄化技術にだけ目を向けるのではなく,周辺一帯の環境を水質管理という面から捉えようとする試みが必要であろう。たとえば,底質除去をはじめ排出水の量的・質的制御,浄化副産物の資源化・有効活用などを通じて環境水への効果的な負荷削減を図っていくことが今後重要である。したがって,本書では「環境水の浄化技術」という言葉の意味するところを今後への期待も込めてより幅広く考えている。
2004年11月 菅原正孝
【執筆者一覧(執筆順)】
菅原正孝 大阪産業大学 人間環境学部 教授
濱崎竜英 大阪産業大学 人間環境学部 都市環境学科 講師
笠井由紀 (株)海洋バイオテクノロジー研究所 微生物利用領域 研究員
渡辺一哉 (株)海洋バイオテクノロジー研究所 微生物利用領域 領域長 主任研究員
森 一博 山梨大学 大学院医学工学総合研究部 社会システム工学系 講師
藤田正憲 大阪大学 大学院工学研究科 環境工学専攻 教授
大谷英夫 大成建設(株) 技術センター 土木技術研究所 水域・生物環境研究室 主任研究員
蓑輪祐介 東洋建設(株) 大阪本店土木部 課長代理
榎本 孝 東洋建設(株) 大阪本店土木部 係長
橘田隆史 日本ミクニヤ(株) 大阪支店 環境防災部 企画課 課長
平澤浩宣 米山化学工業(株) 大阪営業所 名古屋営業所 営業所所長
藤川陽子 京都大学 原子炉実験所 助教授
前田義範 西日本エンジニアリング(株) 常務取締役
阿部公平 (株)イズコン 技術開発部
桑原智之 島根大学 生物資源科学部 研究員
佐藤周之 島根大学 生物資源科学部 研究員
馬場 圭 JFEエンジニアリング(株) 水エンジニアリング事業部 計画部 副課長
岡本昭三 (株)ビー・シー・オー 代表取締役
五十嵐武士 (株)イガデン 代表取締役
山磨敏夫 ナカシマプロペラ(株) 技術本部開発部開発グループ 係長
増本輝男 (株)ワイビーエム 取締役技術開発担当
中久喜康秀 (株)竹中工務店 技術研究所 先端研究開発部 エコエンジニアリング部門 研究主任
【構成および内容】
<理論編>
第1章 環境水浄化技術の現状と今後の展望 菅原正孝
1.はじめに
2.浄化技術の現状
3.今後の展望
第2章 土壌浸透浄化技術
1.土壌浸透浄化技術の原理 菅原正孝
1.1 水土の技術と土壌浸透浄化法
1.2 土壌の成因と構成
1.2.1 自然の土壌層
1.2.2 土壌の成分と形態
1.3 土壌層における水の浸透
1.3.1 水分移動現象
1.3.2 水の浸透能
1.4 土壌層における水の浄化
1.4.1 吸着による浄化
1.4.2 土壌微生物による浄化
1.5 土壌浸透浄化法の特徴とシステム
1.5.1 特徴
1.5.2 各種システムとその特性
2.土壌浸透浄化技術の実施例 菅原正孝
2.1 混合土を用いたトレンチ方式-「せせらぎ用水」等の多目的用水をつくる-
2.1.1 経緯と背景
2.1.2 せせらぎプラントの概要
(1)プラントの構成
(2)混合土
(3)通気層
2.1.3 せせらぎプラントの性能
(1)実験方法および測定項目
(2)実験結果および評価
2.2 混合土を用いた高速多段土壌層方式-河川敷を利用した河川水の直接浄化-
2.2.1 経緯と背景
2.2.2 遠賀川における実施例
第3章 微生物による水質浄化
1.微生物による水質浄化の原理 菅原正孝
1.1 はじめに
1.2 好気性微生物
1.3 嫌気性微生物
1.4 藻類や光合成細菌
1.5 おわりに
2.微生物による環境浄化の研究例・実施例 濱崎竜英
2.1 概要
2.2 接触曝気法(接触酸化法)
2.2.1 礫
2.2.2 サンゴ石, 石炭, 木炭
2.2.3 サルボウ貝殻
2.2.4 プラスチック(ボール状)
2.2.5 ポリプロピレン(リング状)
2.3 課題
2.3.1 発生汚泥対策
2.3.2 目詰まり対策(無機性SS対策)
2.3.3 難分解性有機物の除去
2.3.4 BOD測定の限界
3.石油汚染海洋環境浄化 笠井由紀, 渡辺一哉
3.1 はじめに
3.2 流出油の挙動
3.3 流出油への対応
3.4 微生物による石油成分の分解
3.5 流出油のバイオレメディエーション
3.6 バイオレメディエーションの課題
3.7 おわりに
第4章 植物による水質浄化 森 一博, 藤田正憲
1.植物による水質浄化の原理
1.1 はじめに
1.2 水生植物浄化法の背景
1.3 水生植物による水質浄化の原理
(1) 植物体による窒素・リンの吸収作用
(2) 根圏微生物による有機物分解と硝化・脱窒作用
(3) 植物体の接触材としての作用
(4) その他の作用
2.バイオマス利用
2.1 はじめに
2.2 バイオマスの有効利用法
(1) 食料, 飼料, 花卉
(2) 土壌還元
(3) 資源化
2.3 バイオマス利用の展望
3.水質浄化への遺伝子操作技術の応用
3.1 はじめに
3.2 植物の育種
3.3 根圏微生物の育種
4.植物による水質浄化の施設と実施例
4.1 植物を用いた水質浄化施設の分類
(1) 抽水植物や陸生植物による浄化
(2) 浮遊植物による浄化
(3) 沈水・浮葉植物による浄化法
4.2 植物を用いた水質浄化施設の計画
(1) 環境条件
(2) 植物の選定
(3) 植栽条件
(4) 維持管理条件
4.3 植物を用いた水質浄化の実施例
5.水質浄化植物データベース
5.1 はじめに
5.2 大阪大学が開発した水質浄化植物データベース
5.3 データベースの有用性
6.植物を用いた水質浄化の課題
第5章 底質改善による水質浄化
1.底泥置換覆砂工法 大谷英夫
1.1 はじめに
1.2 底泥置換覆砂工法の原理と特徴
1.2.1 概要
1.2.2 室内水理実験
1.3 施工事例
1.3.1 諏訪湖実証実験
1.3.2 宍道湖試験工事
1.4 底泥置換覆砂工法の効果
1.4.1 底泥浄化の結果
1.4.2 底生生物環境の再生効果
1.5 まとめ
2.高濃度薄層浚渫 蓑輪祐介, 榎本 孝
2.1 技術開発の経緯と目的
2.2 「カレン工法」の概要
2.3 「カレン工法」の技術的特徴
2.3.1 ロータリーシェーバー式集泥機
2.3.2 自動浚渫運転制御システム
2.3.3 施工管理システム
2.4 「カレン工法」琵琶湖における施工例
2.4.1 工事概要
2.4.2 施工の流れ
2.4.3 施工
2.4.4 施工実績
2.4.5 施工状況写真
3.底質改善剤(硝酸カルシウム錠剤) 橘田隆史, 平澤浩宣
3.1 はじめに
3.2 硝酸カルシウムによる底質改善の概要
3.2.1 技術の概要
3.2.2 開発の経緯
3.2.3 硝酸カルシウムの化学的特性
(1) 化学性状
(2) 毒性
(3) 製法
(4) 硝酸カルシウム錠剤の添加物
3.2.4 底質改善効果のメカニズムと事例紹介
(1) 酸化作用によるORPの上昇と,リン及び硫化物の固定
(2) 分離発生したCa2+イオンの吸着による効果(化学反応)
(3) 脱窒による有機物分解の促進(生物化学反応)
3.2.5 施工方法
3.3 技術的課題と今後の展開
<材料・システム編>
第6章 水質浄化材料
1.廃棄物利用の吸着材 藤川陽子
1.1 本節の概要
1.2 水処理における吸着の役割と廃棄物利用の吸着材の意義
1.3 廃棄物利用の吸着材の実例
1.3.1 金属イオンの吸着除去材
(1) 陽イオンの吸着材
(2) 陰イオンの吸着材
(3) 様々な金属イオンの吸着しやすさ
1.3.2 有機物の吸着除去材
(1) VOC, 油類および農薬の吸着
(2) フェノール・フェノールの化合物および染料の除去
1.3.3 リン酸及びCOD一般の吸着除去
(1) リン酸の吸着材
(2) COD一般の吸着材
1.4 廃棄物利用の吸着材の試験方法
1.4.1 吸着等温式取得の試験方法
1.4.2 吸着等温式
(1) ラングミュアの吸着等温式
(2) Temkinの式
(3) フロインドリッヒの吸着等温式
(4) 線形吸着等温式
(5) initial mass sorption isotherm
1.4.3 汚濁物質の吸着に影響する諸条件
(1) pHの影響
(2) イオン強度
(3) 温度
(4) 吸着速度
1.5 まとめ
2.ガラス発泡材 前田義範
2.1 はじめに
2.1.1 ガラスびんリサイクルの現状
2.1.2 ガラス発泡材の特性と水質浄化用途への応用
2.2 ガラス発泡材の基本的特性及び水質浄化機能
2.2.1 ガラス発泡材の基本的特性
2.2.2 ガラス発泡材の水質浄化機能
2.3 適用例
2.3.1 コンクリート表面への設置例
2.3.2 水質浄化ユニット
2.3.3 ガラス発泡材を利用した人工浮島工『水萌』
(1) ガラス発泡材を利用した人工浮島工『水萌』の水質浄化機能と特徴
(2) 水萌における水質浄化効果の定量化
2.4 おわりに
3.リン吸着コンクリート 阿部公平, 桑原智之, 佐藤周之
3.1 環境水中におけるリンの現状
3.2 リン吸着コンクリートの特徴
3.3 リン吸着コンクリートのリン吸着特性
3.4 リン吸着コンクリートの今後の展開
第7章 水質浄化システム
1.河川浄化システム 馬場 圭
1.1 はじめに
1.2 浮遊ろ材式生物膜ろ過の原理
1.3 特徴
1.4 処理性能
(1) BOD除去
(2) 溶解性BOD除去
(3) SS除去
(4) NH4-N
1.5 実施例
1.5.1 河川浄化
1.5.2 池の浄化
1.5.3 下水の修景用水利用
1.6 おわりに
2.循環型水質浄化システム「BCOハピネスクリーンウォーターシステム」 岡本昭三
2.1 池・湖沼の水質浄化の現状
2.2 池・湖沼の水質浄化設備に求められるポイント
2.3 循環型水質浄化システム「BCOハピネスクリーンウォーターシステム」
2.3.1 概要
2.3.2 浄化の仕組み
(1) 磁気活水処理
(2) ろ過処理(特殊ろ過材「ミラクルろくすけ」によるろ過)
(3) 逆洗浄水の還流
2.4 BCOハピネスクリーンウォーターシステムにより解決される水質浄化の問題点
(1) 水量の大きな池・湖沼の浄化が可能
(2) 季節の推移に伴い変化する水質悪化に対応できる
(3) 低コストでの浄化が可能(浄化コストの削減要因)
2.5 浄化実例【ゴルフ場内池水浄化(アオコ除去・透明度の向上)】
2.6 磁気活水処理の応用技術「BCOハピネスエジェクター」
3.電気分解法による環境汚染汚濁物質除去技術 五十嵐武士
3.1 はじめに
3.2 社会的環境規制の背景
3.3 マイクロウォーターシステムの研究開発経緯
3.4 システム構成例及び電気分解処理メカニズム
3.5 マイクロウォーターシステム省エネルギー型水環境浄化技術の応用範囲
3.6 20t/D処理に必要な設置面積
3.7 実施例
3.8 既存技術と比べて,どのような点が先進的なのか,何が優れているのか
3.9 おわりに
4.密度流拡散装置 山磨敏夫
4.1 はじめに
4.2 密度流拡散装置の特徴
4.3 密度流拡散装置の実施例
4.3.1 密度流拡散装置の概要
4.3.2 密度流拡散装置の設置場所
4.3.3 調査結果
4.3.4 まとめ
4.4 その他の実施例
4.5 おわりに
5.噴流層式水処理システム 増本輝男
5.1 はじめに
5.2 噴流層式水処理システムの原理
5.2.1 寄生虫の卵・プランクトンの破壊による水処理
(1) 養殖トラフグに寄生する寄生虫の卵の破壊
(2) 珪藻プランクトン(リゾソレニア)の破壊
5.2.2 オゾン・酸素を利用した水処理
(1) 養殖場における酸素溶解
(2) 淡水プランクトンのオゾン・酸素を利用した水処理
5.2.3 汚染地下水の水処理
(1) 原理
(2) 実績
5.4 まとめ
6.超高速海水浄化システム 中久喜康秀
6.1 はじめに
6.2 システムの概要
6.3 実証試験の概要
6.3.1 実証システムの概要
6.3.2実施内容
(1) 浄化対象水域に対する浄化効果の確認
(2) システムの稼働性能の確認
6.3.3 実証試験結果
(1) 浄化対象水域に対する浄化効果の確認
(2) システムの稼働性能の確認
6.4 まとめ
目次
理論編(環境水浄化技術の現状と今後の展望;土壌浸透浄化技術;微生物による水質浄化;植物による水質浄化;底質改善による水質浄化)
材料・システム編(水質浄化材料;水質浄化システム)
著者等紹介
菅原正孝[スガハラマサタカ]
大阪産業大学人間環境学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。