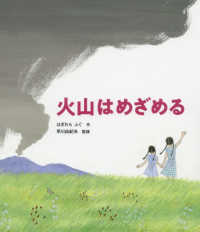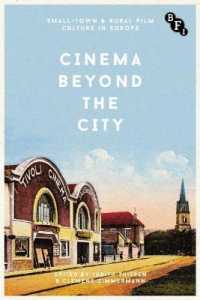出版社内容情報
★環境調和型溶媒として注目を集める超臨界流体の特性からナノテクノロジーへの応用技術まで網羅!
★材料製造・加工技術など多方面にわたる最先端の技術を解説!
★国内外の開発最前線の研究者が執筆!
【はじめに】
1 合成から構造制御,ファブリケーションの時代へ
最近の10年間で,新材料の開発の方向性は急激に変わりつつある。20世紀は,コモディティケミカルズを大量に合成する時代であった。しかし,先進諸国では,すでに製品の対象がスペシャルティケミカルズ,構造化材料,そしてデバイスへと移り,応用分野も電子材料,環境材料,健康・医療分野と多岐に渡っている。
一方,最近のナノテクノロジー開発も,このような材料開発の変化に拍車を掛けている。従来,製品に新しい機能を求める場合,新材料の創成に頼っていた。しかし,最近,ナノ材料のサイズ,形状,高次構造を制御することでも新たな物性が発現することがわかってきた。そのため,製品開発における構造制御の位置づけが極めて重要となりつつある。
すなわち,図1に示すように,20世紀が新物質創成の「合成」の時代であったのに対して,材料のサイズ,構造の制御が重要な「プロセッシング」「ファブリケーション」の時代に入ったということができる。
現在,経済産業省で進められているナノテクノロジープログラムにおける,ナノ金属,ナノガラス,ナノ高分子,ナノ粒子合成,ナノコーティングに関する各プロジェクトは,製品対象は異なるが,いずれも核発生・成長,あるいはスピノーダル分解過程を経て形成される相分離構造を制御するという視点で開発が進められている。1次構造,2次構造,3次構造を制御する研究が進められ,様々な新規構造制御材料が提案・開発されている。このような構造制御を行う上で重要な視点は,マクロなスケールでの伝熱や流動,物質移動の速度論であり,またその制御プロセスである。上記のナノテクノロジープログラム「材料技術の知識の構造化プロジェクト」では,材料系によらずに,「プロセス」と「構造形成」の関係を明らかにする研究を進めている。
ナノ材料を幅広い産業分野に応用していくことを考えれば,そのナノ材料を組み立て,ナノデバイスへと展開していく「アドレッシング(設計通りの配列)」技術が必要であることは明らかである。フラーレンやナノチューブ,あるいはCdSe,CdSのようなナノ材料に,特異な電気特性が現れることが見出されているが,それをデバイスに組みこんでいくためには,それらのナノ材料をデバイスチップ上にアドレッシングし,アセンブルしていく技術が必要である。AFMやSTMを使って,ナノ材料を並べることができるが,それでは工業的な技術にはなりえない。より高速に大面積のデバイス上にアドレッシングする技術が必要である。
ナノ粒子の規則正しい整列については,経済産業省ナノ粒子プロジェクトにおいて,大量に高速に大面積で配列をコーティングする(自己組織化)技術が開発されつつある。それが同じナノ材料の均質な配列(ホモアセンブリー)であったのに対し,異なるナノ材料を基板上に「アドレッシング・設計通りに配列」(ヘテロアセンブリー)する技術が必要となる。すなわちナノ構造の構築に,生体分子のもつアセンブリー技術(ナノバイオテクノロジー)が重要となる。
2 超臨界流体技術とナノテクノロジー
超臨界流体は,従来の気相,液相プロセスにはない新たな特性を引き出しうる場として,研究開発が進められている。超臨界流体の特性としては,相の制御性,溶解度の制御性そして反応の制御性があげられる。1980年代はカフェインや香料の超臨界CO2による抽出・分離プロセスの開発がさかんに進められた時代であった。しかし,現在は,超臨界CO2を利用した薬剤成型,クリーニング,有機合成,乾燥・成型,超臨界水を用いた廃棄物処理,有機合成,無機材料合成と広い分野で,新規方法,製品開発が進められている。今までにない新たなプロセスの特性も見出されている。今後も様々な分野で応用技術の開発が進められていくことと思う。ナノテクノロジーにおける構造制御,ファブリケーションの分野もその一つであろう。
ナノテクノロジーの開発において,従来のバルク材料製造,加工では経験しなかった技術課題に直面している。ナノ材料は表面エネルギーが極めて高く,それが原因で,ナノ材料の分散・安定化,配列・構造化,表面修飾,洗浄,乾燥等,多くのプロセスで従来技術では対応できない場合も出てきている。超臨界という新たな場を用いることは,従来の技術課題のブレークスルーやまったく新たな技術が生み出される高い潜在的可能性を秘めている。
本書で紹介する数々の技術はその例であるが,決してそこにとどまるものではない。超臨界流体技術が手法であるのに対し,ナノテクノロジーが対象技術領域であるという視点に立てば,ナノテクノロジーの技術が広がるほど,さらに新たな技術が生み出される可能性も広がっていくと考える。その意味で,本書では,手法である超臨界技術についても,あえて厳密な意味での「超臨界」に縛られることをさけ,亜臨界から超臨界にまで広げることとした。ナノテクノロジー分野についての説明も,新領域であるナノバイオテクノロジーにまで踏み込んで解説を行うこととした。
本書は,ナノテクノロジーと超臨界境界領域の技術に関するものであるから,読者をどちらの専門でもない人を想定することとした。したがって,超臨界の基礎もナノテクの概要についても説明を行っている。超臨界を用いたナノテクノロジーについての日本の研究・技術はかなりの広がりをもっているとは思うが,それでも個々の研究・技術の紹介だけですべての技術を網羅することは困難である。また,読者が超臨界,ナノテクの専門でないことを考えると,個別技術の商会では,技術の全体像や特徴を把握しにくいのではと考えた。そこで,技術分野ごとに総説をまとめていただき,その上で各研究者の独自の発想に基づく応用技術を紹介いただくこととした。
本書では,最後に,通常の索引だけでなく,用途別の索引も用意した。すなわち,超臨界あるいはナノテクノロジー分野に専門的に使われる用語を整理するとともに,ナノ粒子を作る,使う,ナノ構造を作る,使うといった観点からキーワードを整理した。少しでも超臨界やナノテクの専門でない読者の助けになればと思っている。
本書が,超臨界あるいはナノテクノロジーの分野で研究を進められておられる方々の新たな発想,新技術創出の一助となれば幸いである。
文 献
1)阿尻ら,化学工学,66(9),554-557(2002)
2)経済産業省「知識の構造化プロジェクト」14年度成果報告
2004年8月 阿尻雅文
【執筆者一覧(執筆順)】
阿尻 雅文 東北大学 多元物質科学研究所 教授
猪股 宏 東北大学 工学研究科 超臨界溶媒工学研究センター 教授
岩井 芳夫 九州大学 大学院工学研究院 化学工学部門 助教授
古屋 武 (独)産業技術総合研究所 ナノテクノロジー研究部門 主任研究員
松村 幸彦 広島大学 大学院工学研究科 機械システム工学専攻 助教授
神谷 秀博 東京農工大学 大学院共生科学技術研究部 教授
安田 英典 (株)三菱総合研究所 安全科学研究本部 主席研究員
Wuled Lenggoro 広島大学 大学院工学研究科 物質化学システム専攻 助手
奥山喜久夫 広島大学 大学院工学研究科 物質化学システム専攻 教授
大久保達也 東京大学 大学院工学系研究科 化学システム工学専攻 助教授
渡邉 英一 化学工業会 ナノマテリアルセンター 部長 ナノテクノロジープログラム
(ナノマテリアルプロセス技術)材料・技術の知識の構造化PJ 技術統括部長
内田 博久 大阪府立大学 大学院工学研究科 物質系専攻 化学工学分野 講師
福里 隆一 エスシーエフテクノリンク 代表
Michel Perrut Separex CEO
大竹 勝人 (独)産業技術総合研究所 ナノテクノロジー研究部門 主任研究員
鷺坂 将伸 弘前大学 理工学部 物質理工学科 機能素材工学講座 助手
井村 知弘 (独)産業技術総合研究所 環境化学技術研究部門 グリーンプロセスグループ 研究員
三島 健司 福岡大学 工学部 化学システム工学科 助教授
松山 清 福岡大学 工学部 化学システム工学科 併任講師
吉澤 秀和 岡山大学 環境理工学部 環境物質工学科 教授
有島 真史 化学技術戦略推進機構 研究開発事業部 研究員
伯田 幸也 (独)産業技術総合研究所 超臨界流体研究センター 研究員
高見 誠一 東北大学 多元物質科学研究所 助手
梅津 光央 東北大学 多元物質科学研究所 助手
大原 智 東北大学 多元物質科学研究所 講師
笠井 均 東北大学 多元物質科学研究所 助教授
宍戸 昌広 山形大学 工学部 物質化学工学科 助教授
岡本 浩一 名城大学 薬学部 製剤学研究室 助教授
佐藤 次雄 東北大学 多元物質科学研究所 教授
殷 シュウ 東北大学 多元物質科学研究所 講師
井奥 洪二 東北大学 大学院環境科学研究科 助教授
後藤 元信 熊本大学 工学部 物質生命化学科 教授
依田 智 (独)産業技術総合研究所 ナノテクノロジー研究部門 研究員
生津 英夫 NTT物性科学基礎研究所 量子電子物性研究部 ナノ加工研究グループ
グループリーダー 主幹研究員
大嶋 正裕 京都大学 大学院工学研究科 化学工学専攻 教授
若山 博昭 (株)豊田中央研究所 第2特別研究室 研究員
曽根 正人 東京農工大学 工学部 有機材料化学科 助手
宮田 清蔵 東京農工大学 学長
上宮 成之 岐阜大学 工学部 人間情報システム工学科 助教授
垣花 眞人 東北大学 多元物質科学研究所 教授
冨田 恒之 東北大学 多元物質科学研究所
Petrykin Valery 東北大学 多元物質科学研究所 助手
柳澤 和道 高知大学 理学部附属水熱化学実験所 所長 教授
渡辺 豊 東北大学 大学院工学研究科 技術社会システム専攻 助教授
塚田 隆夫 東北大学 多元物質科学研究所 助教授
【構成および内容】
第1章 超臨界流体技術
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 猪股 宏
2.超臨界流体とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 猪股 宏
2.1 はじめに
2.2 超臨界流体の特徴
3.超臨界流体の特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 岩井芳夫
3.1 2成分系の相挙動と相平衡
3.2 溶質の溶解度
3.3 エントレーナ効果
3.4 クラスター効果
3.5 超臨界水の物性
4.超臨界技術の原理と最近の動向 ・・・・・・・・・・・13
4.1 溶解度・相平衡と抽出・分離 古屋 武
4.1.1 溶解度・相平衡データの所在
4.1.2 溶解度・相平衡の測定法
4.1.3 最近の技術動向
4.2 反応 松村幸彦
4.2.1 超臨界流体の特性と化学反応
4.2.2 超臨界流体反応利用の事例
第2章 ナノテクノロジーの最近の動向
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 神谷秀博
2.ナノテクノロジーの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 安田英典
2.1 はじめに
2.2 ナノテクノロジー小史
2.3 21世紀ナノテクノロジー研究開発法
2.4 ナノテクノロジーのファンディングの底流
2.5 ナノテクノロジーと米国の国家安全保障
2.6 ナノテクノロジーの2面性
2.7 欧州およびアジア
2.8 ナノテクノロジーとバイオ
2.9 社会的受容性
3.ナノ粒子合成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 Wuled Lenggoro,奥山喜久夫
3.1 はじめに
3.2 液相法におけるナノ粒子の合成
3.2.1 化学的液相法
3.2.2 物理的液相法
3.3 マトリックスを利用したナノ粒子のin situ合成
3.3.1 ミクロンシリカ粒子を利用したナノ粒子の合成
3.3.2 ナノ粒子分散型蛍光性ポリマー電解質の合成
3.4 気相法によるナノ粒子合成
3.4.1 火炎法
3.4.2 CVD法によるナノ粒子の合成
3.5 固相反応法によるナノ粒子の合成
3.6 おわりに
4.ナノ構造制御 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 大久保達也
4.1 ナノ構造の特徴
4.2 ナノ構造の作製
4.3 ボトムアップによるナノ構造の制御
4.4 集積場としてのナノ構造
4.5 おわりに
5.ナノバイオテクノロジーの動向 ・・・・・・・・・・・・・・・55 神谷秀博,渡邉英一
5.1 全般的な研究開発動向
5.2 ナノテクノロジーの医療・健康,生活関連分野への応用
5.3 バイオテクノロジーの材料ナノテクノロジー,その他物質生産プロセス分野への応用
5.4 おわりに
第3章 ナノ粒子合成
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 阿尻雅文
2.超臨界流体を利用したナノ微粒子創製 ・・・・・・・64 内田博久
2.1 はじめに
2.2 超臨界流体を利用した微粒子創製技術
2.2.1 急速膨張法
2.2.2 貧溶媒添加法
2.2.3 反応晶析法
2.3 おわりに
3.超臨界流体による微粒子製造法 ・・・・・・・・・・・・73 福里隆一,Michel Perrut
3.1 はじめに
3.2 超臨界流体場における微粒子製造技術の熱力学的背景
3.3 微粒子製造技術の概要
3.3.1 急速膨張法
3.3.2 貧溶媒化法
3.3.3 ガス飽和溶液懸濁法
3.4 応用実施例
3.4.1 微粒子複合体製造
3.5 おわりに
4.超臨界水熱合成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94 阿尻雅文
4.1 はじめに
4.2 超臨界水の物性,相挙動および反応平衡・速度
4.2.1 超臨界水の物性
4.2.2 超臨界水中での相挙動
4.3 高温高圧水中での化学平衡と酸化物の溶解度
4.3.1 水熱合成反応
4.3.2 超臨界水中での溶媒効果と反応制御
4.3.3 高温高圧水中での反応平衡・溶解度の評価
4.4 急速昇温超臨界水熱合成装置
4.5 超臨界水熱合成の特性
4.5.1 ナノ粒子合成
4.5.2 粒子形状の制御
4.5.3 酸化還元場の制御
4.5.4 in situ熱処理と高結晶性
4.6 超臨界水中でのナノ粒子合成の機構
4.7 反応場の理解に基づく超臨界水熱合成装置の開発
4.8 おわりに
5.マイクロエマルションとナノマテリアル ・・・・・・・・・・・・108 大竹勝人,鷺坂将伸,井村知弘
5.1 はじめに
5.2 マイクロエマルションと超臨界流体
5.3 界面活性剤の分子設計
5.3.1 臨界充填パラメーター
5.3.2 親水基と親油基(疎水基)
5.3.3 親水性/親油性バランス
5.4 超臨界炭化水素中のマイクロエマルション
5.5 超臨界二酸化炭素中のマイクロエマルション
5.6 超臨界二酸化炭素中のマイクロエマルションを利用したナノマテリアルの調製
5.6.1 超微粒子の合成
5.6.2 その他のナノマテリアルの合成
5.6.3 洗浄
5.6.4 リポゾーム調製
5.7 おわりに
6.応用技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・126
6.1 マイクロカプセル・染色 三島健司,松山 清
6.1.1 超臨界二酸化炭素を用いた高分子微粒子・マイクロカプセル製造法
6.1.2 環境適応型染色システムの開発
6.2 複合材料 吉澤秀和,有島真史
6.2.1 はじめに
6.2.2 複合材料製造に用いられるプロセスと特徴
6.2.3 応用分野
6.2.4 今後の動向
6.3 ナノ無機粒子合成 伯田幸也
6.3.1 はじめに
6.3.2 光触媒ナノワイヤー合成
6.3.3 蛍光体ナノ粒子合成
6.3.4 おわりに
6.4 有機・無機・生体分子複合ナノ粒子 阿尻雅文,高見誠一,梅津光央,大原 智
6.5 サイズ制御された顔料系ナノ結晶の作製 笠井 均
6.6.1 はじめに
6.6.2 使用した化合物と実験系
6.6.3 フタロシアニンナノ結晶の作製
6.6.4 異なる結晶型を有するキナクリドンナノ結晶の作製
6.6.5 C60ナノ結晶の作製
6.6.6 おわりに
6.6 超臨界二酸化炭素中でのポリマーナノ粒子の調製 宍戸昌宏
6.6.1 はじめに
6.6.2 SC-CO2中での分散重合によるポリマー粒子の調製
6.6.3 SC-CO2中でのポリマー微粒子の構造制御の可能性
6.7 機能性医薬品微粒子 岡本浩一
6.7.1 はじめに
6.7.2 溶解速度の制御
6.7.3 結晶形の制御
6.7.4 薬物微粒子のコーティング
6.7.5 マイクロスフィア
6.7.6 リポゾーム
6.7.7 タンパク質医薬の微粒子化
6.7.8 遺伝子医薬の微粒子化
6.8 微粒子合成・乾燥 佐藤次雄,殷シュウ
6.8.1 はじめに
6.8.2 粉末の形態・凝集制御における超臨界溶媒の役割
6.8.3 超臨界溶媒中の非晶質ゲルの結晶化
6.8.4 超臨界溶媒処理粉末の焼結特性
6.8.5 超臨界溶媒処理粉末の光触媒特性
6.8.6 おわりに
6.9 生体ナノ材料 ^羆?親?
6.9.1 生体ナノ材料とは
6.9.2 アパタイト生体機能材料
6.9.3 おわりに
第4章 ナノ構造制御
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178 後藤元信
2.超臨界ナノ構造制御法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179 後藤元信
2.1 はじめに
2.2 超臨界乾燥
2.3 プレーティング
2.4 発砲ポリマー
2.5 超臨界洗浄
2.6 超臨界染色
3.応用技術 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・187
3.1 エアロゲル 依田 智
3.1.1 はじめに
3.1.2 エアロゲルの作成と超臨界乾燥
3.1.3 代表的なエアロゲル
3.1.4 おわりに
3.2 高アスペクト・超微細パターン形成法 生津英夫
3.2.1 パターン倒れとその原因
3.2.2 超臨界乾燥法
3.3 超臨界二酸化炭素を用いた洗浄技術について 猪股 宏
3.3.1 はじめに
3.3.2 超臨界二酸化炭素の洗浄溶媒としての可能性
3.3.3 超臨界流体洗浄の対象洗浄物
3.3.4 新規な洗浄効果発現機構
3.3.5 超臨界CO2ドライクリーニング
3.3.6 フィルター洗浄
3.3.7 おわりに
3.4 マイクロ発砲構造形成 大嶋正裕
3.4.1 超臨界二酸化炭素と発砲成形
3.4.2 超臨界二酸化炭素と発砲性
3.4.3 超臨界二酸化炭素とセル構造(気泡密度・気泡径)
3.4.4 今後の展望
3.5 ネガ構造 若山博昭
3.5.1 はじめに
3.5.2 Nanoscale Casting Process(NC法)
3.5.3 応用分野
3.6 超臨界ナノプレーティングシステム 曽根正人,宮田清蔵
3.6.1 はじめに
3.6.2 実用機の開発
3.6.3 実用機により得られるめっき皮膜
3.6.4 おわりに
3.7 ナノプレーティングによる燃料電池用材料の作製 上宮成之
3.7.1 はじめに
3.7.2 水素分離用パラジウム膜
3.7.3 超臨界パラジウム電気めっき
3.7.4 燃料電池用材料作製への応用
3.7.5 おわりに
3.8 水熱反応におけるプレカーサーとしてのゲル及び水溶性チタン化合物
垣花眞人,冨田恒之,Petrykin Valery
3.8.1 はじめに
3.8.2 錯体重合法と水熱法を組み合わせた六方アノーサイトの合成
3.8.3 ゾルゲル水熱法によるチタン酸塩の薄膜作製
3.8.4 水溶性チタン化合物の水熱分解によるTiO2ナノ微粒子合成
3.8.5 おわりに
3.9 水熱ホットプレス法による成形体の作製 柳澤和道
3.10 ナノバイオへの展開 阿尻雅文,高見誠一,梅津光央,大原 智
3.10.1 はじめに
3.10.2 DNA高次構造を利用したナノ粒子アセンブリとアドレッシング
3.10.3 特異的結合力を持つペプチドを用いたナノ粒子パターニング
3.10.4 ナノバイオへ向けた超臨界技術の展望
3.11 その他の技術動向 後藤元信
3.11.1 ナノシート(層状物質の剥離)およびポリマーとの複合体
3.11.2 超臨界プレーティングによるナノ構造
3.11.3 ナノ粒子の固定法
第5章 超臨界流体材料合成プロセスの設計
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・263 福里隆一
2.超臨界プロセスの設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265 福里隆一
2.1 プロセス基本設計および経済性評価
2.1.1 超臨界二酸化炭素抽出基本プロセス
2.1.2 基本プロセス設計手順
2.1.3 抽出器基本仕様の検討
2.2 超臨界流体プロセス詳細設計
2.3 おわりに
3.超臨界プロセスの材料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・274 渡辺 豊
3.1 はじめに
3.2 腐食環境としての超臨界水の特異性
3.3 超臨界・亜臨界水環境での金属材料の腐食挙動
3.3.1 超臨界・亜臨界水腐食における水の物性の重要性
3.3.2 酸化剤濃度の効果と電位-pH図の有効性
3.3.3 合金成分,耐食性,皮膜(スケール)構成酸化物の関係
3.4 おわりに
4.超臨界流体を利用した材料製造プロセスの数値シュミレーション ・・・283 塚田隆夫,阿尻雅文
4.1 はじめに
4.2 超臨界熱流体解析に関する最近の研究
4.2.1 ピストン効果
4.2.2 超臨界水酸化プロセス
4.3 超臨界流体を利用した粒子製造プロセスシュミレーション
4.3.1 超臨界熱流体解析
4.3.2 粒子生成・成長解析
4.3.3 熱物性値
4.3.4 解析例
4.4 おわりに
おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・293
索引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・294
用途別索引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・297
--------------------------------------------------------------------------------
目次
第1章 超臨界流体技術(超臨界流体とは;超臨界流体の特性 ほか)
第2章 ナノテクノロジーの最近の動向(ナノテクノロジーの動向;ナノ粒子の合成技術 ほか)
第3章 ナノ粒子合成(超臨界流体を利用したナノ微粒子創製;超臨界流体による微粒子製造法 ほか)
第4章 ナノ構造制御(超臨界ナノ構造制御法;応用技術 ほか)
第5章 超臨界流体材料合成プロセスの設計(超臨界流体プロセスの設計;超臨界流体プロセスの材料 ほか)
著者等紹介
阿尻雅文[アジリタダフミ]
東北大学多元物質科学研究所教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。