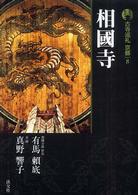内容説明
日本では、火山がうめたてた土地の上に、多くの人々がくらしています。ドンと大砲をうつような爆発、何日もふりつづく軽石、火口からながれだす溶岩、すべてを瞬時にのみこむ火砕流、そして…。ひとつの火山が2万5000年間に見せた、さまざまなめざめを描きました。
著者等紹介
はぎわらふぐ[ハギワラフグ]
1968年千葉県生まれ。武蔵野美術短大卒業後、(株)チューブグラフィックスで木村博之氏に学び、同社で20年以上にわたり地図とインフォグラフィックス制作に従事する。現在はフリーランスとして独立
早川由紀夫[ハヤカワユキオ]
群馬大学教育学部教授。1956年千葉県生まれ。東京大学理学博士(地質学)。1980年代から浅間山の地質を調べ始め、「史料に書かれた浅間山の噴火と災害」などを発表した。ドローンによる空中撮影が得意(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Aya Murakami
94
他館図書館本。 昭和の登山者はキモが座っている!噴石で火を起こしてお茶を飲むなんて…(汗)ブルカノ式だそうです。江戸時代のプリニー式噴火は日本史の教科書でおなじみですね。平安時代の火砕流はダンテズピークやポンペイでおなじみのスフリエール式だと思う。2万5000年前の山体崩壊なんてあったのですね。山体崩壊でそれ以前の地学的データはないそう。姉君富士山に負けないくらいの噴火のデパート。ますます浅間山が好きになる。2024/07/07
♡ぷらだ♡お休み中😌🌃💤
46
読友さんのレビューを見て手にとった1冊。長野県と群馬県にまたがる浅間山がこの本のモデル。昭和、江戸、平安、2万5000年前の4つの噴火を取り上げている。火山の噴火は恐ろしいものだが、自然の営みのひとつ。共存していかないといけない。「火山がめをさますのはほんのひとときだけ」「ゆげは火山のあくびのようなもの」など、浅間山やその地質を研究している作者だけにやさしい表現がいっぱい。その浅間山が昨日小規模噴火。早く沈静化したらいいなあ。2019/08/08
たまきら
39
富士山の噴火について娘さんが何度も聞いてきたころがありました。トンガの噴火でまた心配になったみたいで火山の話を何度も蒸し返すので、読み友さんの感想を読んで「これだっ!」と借りてきました。はい、食いつきました。まだ何も言ってきませんが、じっくり読んでいるようです。これで質問は減るのか、それとも増えるのか…。2022/01/31
みさどん
25
科学絵本のようで迫力ある一冊。絵本になっていると子どもも手をのばしやすい。熊本は阿蘇という活火山があるので、火口や煙の様子がよくわかる。うちから長崎の普賢岳の火砕流が見えたのを思い出した。鹿児島では桜島の煤の雨をくらった。永い年月の地球の様子を見せてもらった感じ。人間なんてちっぽけに思える。2022/02/23
ぼりちゃん
25
あいかわらず『ジュラシックワールド』つながりで火山に興味があるようだ。浅間山が昭和時代、江戸時代、平安時代、2万5000年前それぞれの噴火の様子を逆にたどるように描かれている科学絵本。1つの火山で1つの噴火様式だと思っていたけど、そうじゃなかった。浅間山だけでもブルカノ式爆発、ブリニー式噴火、それぞれを繰り返していたのは初めて知ったなぁ。レゴ遊びやお絵かきにも火山が登場している息子。そこまで身近に感じているのなら、火山見学に連れて行きたいなぁ🙄5歳6か月2020/09/09