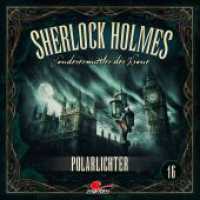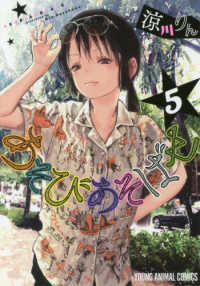出版社内容情報
★ 高分子合成化学の進歩に重要な役割をはたす添加剤の最新開発動向を網羅
★ 化学構造から見た、高分子添加剤の機能の詳説!
★ 添加剤を分かり易く機能別に分類!!
★ 環境問題への取り組みとして、分析方法、法規制等も解説!!!
【執筆者一覧(執筆順)】
大勝 靖一 工学院大学 工学部 応用化学科 教授
飛田 悦男 旭電化工業(株) 樹脂添加剤開発研究所 添加剤研究室 室長
児島 史利 住友化学工業(株) 有機合成研究所 主席研究員
石井 玉樹 シプロ化成(株) 営業部 部長
根岸 由典 旭電化工業(株) 樹脂添加剤開発研究所 添加剤研究室
中村 浩司 チバ・スペシャルティ・ケミカルズ(株) プラスチック添加剤セグメント ポリマープロダクト ビジネスライン 統括マ
ネジャー
秋葉 光雄 アキバリサーチ 所長
木村 健治 住友化学工業(株) 有機合成研究所 主任研究員
福島 充 旭電化工業(株) 樹脂添加剤開発研究所 添加剤研究室
原田 昌史 旭電化工業(株) 樹脂添加剤開発研究所 安定剤研究室 主任研究員
杉浦 基之 日本油脂(株) 化成品研究所 グループリーダー
指田 和幸 理研ビタミン(株) 大阪工場 技術グループ グループリーダー
高尾 敏智 大塚化学(株) 研究技術センター 主任研究員
野須 勉 協和化学工業(株) 研究開発部
稲木 良昭 大阪大学大学院 工学研究科 物質・生命工学専攻 助教授
白井 正充 大阪府立大学大学院 工学研究科 応用化学分野 教授
角岡 正弘 大阪府立大学 名誉教授
黒田 真一 群馬大学 工学部 材料工学科 助教授
田近 弘 東洋紡績(株) 総合研究所 機能材開発研究所 バイロン開発センター 主幹
落合健一郎 日本油脂(株) 油化学研究所 グループリーダー
五百藏賢一 日本油脂(株) 油化学研究所 主任研究員
木村 凌治 旭電化工業(株) 樹脂添加剤開発研究所 改質剤研究室 室長
野村 泰生 日本ユニカー(株) シリコーン応用研究所 主任研究員
占部 朗 大日本インキ化学工業(株) ポリマ改質剤技術グループ 主任研究員
若松 正志 大日本インキ化学工業(株) ポリマ改質剤技術グループ グループマネージャー
上田 昌哉 三菱エンジニアリングプラスチックス(株) 企画開発室 部長代理
西沢 仁 西沢技術研究所 代表
山野井 博 旭電化工業(株) 樹脂添加剤開発研究所 主任研究員
小出 昌史 東洋インキ製造(株) 色材技術統括部 着色技術部 機能材課 課長
勝川 眞琴 三洋化成工業(株) 高分子薬剤研究部 部長代理
鳥飼 章子 大同工業大学 化学教室 非常勤講師
高山 森 (株)ダイヤ分析センター 技術本部 技師長
北村 卓 大日本インキ化学工業(株) レスポンシブル・ケア部 部長
幸野 俊則 旭電化工業(株) 樹脂添加剤開発研究所 添加剤研究室 主席研究員
【構成および内容】
第1章 総論
1.高分子添加剤概論 大勝靖一
1.1 はじめに
1.2 添加剤の分類
1.3 プラスチックと添加剤
1.3.1 劣化と症状
1.3.2 劣化と添加剤
1.4 酸化防止剤の概略
1.5 添加剤の使用量
1.6 添加剤の現状と将来
1.7 おわりに
2.高分子劣化の本質とその防止の基礎
2.1 はじめに
2.2 劣化の基本
2.2.1 劣化反応
2.2.2 劣化の開始
2.2.3 連鎖担体ラジカルの反応
2.2.4 劣化の防止
2.3 おわりに
3.高分子添加剤の相乗・拮抗作用 飛田悦男
3.1 はじめに
3.2 高分子機能維持剤と高分子機能付与剤との相互作用
3.2.1 高分子物性と高分子機能維持剤
3.2.2 高分子機能付与剤の光遮蔽効果と光安定性
3.2.3 高分子機能付与剤と光安定化剤の移行性
3.2.4 高分子機能付与剤と安定化阻害
3.3 高分子機能維持剤間の相互作用
3.3.1 フェノール系酸化防止剤とイオウ系酸化防止剤
3.3.2 フェノール系酸化防止剤とリン系酸化防止剤
3.3.3 HALSと紫外線吸収剤
3.4 おわりに
第2章 高分子機能維持剤
1.フェノール系添加剤
1.1 ラジカル捕捉剤 児島史利
1.1.1 はじめに
1.1.2 定義
1.1.3 用途と化学構造の特徴
1.1.4 化学構造と機能発現機構
1.1.5 特徴と傾向
1.1.6 環境問題
1.1.7 おわりに
1.2 紫外線吸収剤 石井玉樹
1.2.1 はじめに
1.2.2 光劣化
1.2.3 光安定剤
1.2.4 紫外線吸収剤の製造方法
1.2.5 紫外線吸収剤の日本市場
1.2.6 紫外線吸収剤の開発動向
1.2.7 紫外線吸収剤の選択
1.2.8 おわりに
2.アミン系添加剤
2.1 HALS 根岸由典
2.1.1 はじめに
2.1.2 HALSの機構
2.1.3 光劣化とHALS
2.1.4 熱劣化とHALS
2.1.5 HALSの相乗作用と拮抗作用
2.1.6 環境問題
2.1.7 おわりに
2.2 ヒドロキシルアミン 中村浩司
2.2.1 はじめに
2.2.2 化学構造の特徴と用途
2.2.3 化学構造と作用機構
2.2.4 ヒドロキシルアミンの特徴と性能
2.2.5 今後の傾向と実用例
2.2.6 環境安全性
2.2.7 おわりに
2.3 芳香族アミン 秋葉光雄
2.3.1 はじめに
2.3.2 アミン系老化防止機構
2.3.3 アミン系老化防止剤の特徴
2.3.4 アミン系老化防止剤の選択基準
2.3.5 各種ゴムに対する代表的な老化防止剤
2.3.6 比較的近しい老化防止剤
2.3.7 各種老化防止剤と適用ゴムの例
2.3.8 おわりに
3.イオウ・リン系添加剤 木村健治
3.1 はじめに
3.2 定義
3.3 性能発現機構
3.4 イオウ系添加剤とリン系添加剤の相違点
3.5 イオウ系添加剤の特性
3.6 リン系添加剤の特性
3.7 新しいリン系添加剤
3.8 イオウ系・リン系添加剤と環境対策
3.9 むすび
4.金属捕促剤 福島 充
4.1 はじめに
4.2 金属捕捉剤の作用機構
4.3 金属捕捉剤の実用例
4.4 おわりに
5.熱安定剤 原田昌史
5.1 はじめに
5.2 熱安定剤の種類と特徴
5.2.1 鉛系安定剤
5.2.2 錫系安定剤
5.2.3 複合安定剤
5.3 熱安定剤の環境対策
5.4 環境対策における技術的発展
5.5 現在の環境対策
第3章 高分子機能付与剤
1.加工性
1.1 相溶化剤 杉浦基之
1.1.1 はじめに
1.1.2 ポリマーアロイと相溶化剤の役割
1.1.3 相溶化剤の種類
1.1.4 非反応型相溶化剤
1.1.5 反応型相溶化剤
1.1.6 市販の相溶化剤
1.1.7 環境問題
1.1.8 おわりに
1.2 滑剤 指田和幸
1.2.1 はじめに
1.2.2 滑剤の利用法―実用例の紹介―
1.2.3 今後の動向
1.3 発泡剤 高尾敏智
1.3.1 はじめに
1.3.2 発泡剤の分類と種類
1.3.3 化学発泡剤の使用方法
1.3.4 発泡剤と環境問題
1.3.5 今後の課題と展開
1.4 触媒失活剤(ハイドロタルサイト) 野須 勉
1.4.1 はじめに
1.4.2 化学構造と機能発現の機構
1.4.3 構造と機能発現の機構
1.4.4 DHT-4Aの紹介
1.4.5 安全性
1.4.6 おわりに
2.光化学性
2.1 感光性樹脂添加剤 稲木良昭
2.1.1 はじめに
2.1.2 感光性樹脂の種類
2.1.3 光重合
2.1.4 高分子+感光性化合物
2.1.5 高分子の光反応
2.1.6 添加剤の化学構造
2.1.7 実用例と問題点
2.1.8 おわりに
2.2 光分解性付与剤 白井正充、角岡正弘
2.2.1 はじめに
2.2.2 プラスチックの光分解
2.2.3 ポリエチレンの劣化機構
2.2.4 光分解性付与剤と分解機構
2.2.5 おわりに
2.3 光触媒 黒田真一
2.3.1 光触媒とはなにか
2.3.2 半導体光触媒の作用機構
2.3.3 光触媒による高分子の劣化
2.3.4 光触媒による環境浄化、脱臭、抗菌、防汚効果とその応用
2.4 消光剤(クエンチャー) 角岡正弘
2.4.1 はじめに
2.4.2 光酸化劣化とクエンチング
2.4.3 クエンチャー
2.4.3 おわりに
3.電気性
3.1 導電性付与剤 田近 弘
3.1.1 はじめに
3.1.2 ポリマー型導電性ペースト
3.1.3 ポリアミドイミド系樹脂を用いた導電性ペースト
3.1.4 導電性高分子ポリアニリンを用いた帯電防止処方
3.1.5 おわりに
3.2 帯電防止剤 落合健一郎、五百藏賢一
3.2.1 はじめに
3.2.2 帯電現象と帯電防止
3.2.3 帯電防止剤の種類
3.2.4 帯電防止性の評価方法
3.2.5 帯電防止剤を選定するときのポイント
3.2.6 帯電防止剤の安全性
3.2.7 具体的な帯電防止剤の例
3.2.8 おわりに
4.表面性
4.1 防曇剤 指田和幸
4.1.1 はじめに
4.1.2 防曇性付与方法
4.1.3 プラスチック表面の親水化方法
4.1.4 界面活性剤について―防曇剤としての利用―
4.1.5 防曇剤の構造及び性能
4.1.6 防曇剤の性能
4.1.7 おわりに
4.2 抗菌・防カビ剤 木村凌治
4.2.1 はじめに
4.2.2 高分子と抗菌剤
4.2.3 高分子用抗菌剤、防カビ剤の種類と特徴
4.2.4 抗菌性付与技術と抗菌剤の配合技術
4.2.5 抗菌剤の環境対応法規制
4.2.6 今後の動向
4.3 カップリング剤 野村泰生
4.3.1 はじめに
4.3.2 カップリング剤の種類
4.3.3 シランカップリング剤の構造と特徴
4.3.4 シランカップリング剤の種類と適用範囲
4.3.5 シランカップリング剤の機能
4.3.6 シランカップリング剤の作用機構-加水分解と縮合-
4.3.7 シランカップリング剤の作用機構-無機材料表面との反応―
4.3.8 シランカップリング剤の作用機構―有機高分子との作用―
4.3.9 シランカップリング剤の使用方法
4.3.10 シランカップリング剤の応用例
4.3.11 おわりに
5.バルク性
5.1 可塑剤 占部 朗、若松正志
5.1.1 はじめに
5.1.2 可塑剤の種類と需要動向
5.1.3 可塑剤の基本構造と作用機構
5.1.4 各種可塑剤の技術動向
5.1.5 PVC以外の用途
5.1.6 安全衛生性問題
5.1.7 おわりに
5.2 反可塑剤 上田昌哉
5.2.1 はじめに
5.2.2 定義
5.2.3 過去の研究例
5.2.4 反可塑剤の特徴と機能発現の機構
5.2.5 反可塑剤添加高分子のバルク特性
5.2.6 応用例
5.2.7 反可塑剤添加高分子の粘弾性特性挙動
5.2.8 環境問題
5.2.9 今後の展開
5.2.10 おわりに
5.3 難燃剤 西沢 仁
5.3.1 まえがき
5.3.2 最近の難燃材料の研究動向
5.3.3 難燃剤の種類とその役割
5.3.4 難燃剤の現状と需要量
5.3.5 難燃剤の環境問題
5.3.6 あとがき
5.4 造核剤 山野井博
5.4.1 はじめに
5.4.2 ポリマーの結晶化と核剤
5.4.3 造核剤の効果と種類
5.4.4 造核剤によるポリプロピレンの機能向上
5.4.5 おわりに
5.5 着色剤 小出昌史
5.5.1 はじめに
5.5.2 着色剤の定義
5.5.3 化学構造の特徴と用途
5.5.4 環境問題
5.5.5 おわりに
5.6 高分子分散剤 勝川眞琴
5.6.1 はじめに
5.6.2 高分子添加剤としての分散剤
5.6.3 化学構造の特徴と用途
5.6.4 構造と機能発現の機構
5.6.5 添加剤の特徴
5.6.6 フィラー分散剤としての実用例
5.6.7 高比率木質複合体―環境問題への取り組み-
5.6.8 おわりに
第4章 高分子添加剤と環境対策
1.高分子添加剤の分析
1.1 分析手段と分析の留意点 鳥飼章子
1.1.1 はじめに
1.1.2 劣化の定義と劣化による変化
1.1.3 劣化に影響を与えるファクター
1.1.4 劣化の分析方法
1.1.5 おわりに
1.2 各種高分子に対する分析例 高山 森
1.2.1 はじめに
1.2.2 高温ガスクロによる添加剤分析
1.2.3 液体クロマト/質量分析(LC/MS)の応用
1.2.4 高分子量HALSの分析
1.2.5 変色トラブルの解析例
2.高分子添加剤と環境問題
2.1 添加剤と環境問題の関わりの歴史 北村 卓
2.1.1 はじめに
2.1.2 高分子添加剤と環境問題
2.1.3 内分泌かく乱化学物質
2.1.4 欧州の電気電子業界および自動車業界における規制
2.1.5 廃棄物と高分子添加剤
2.1.6 おわりに
2.2 添加剤と法規制 幸野俊則
2.2.1 はじめに
2.2.2 日本の法規制
2.2.3 世界各地域の化学品法規制
2.2.4 食品容器用途の法規制
2.2.5 環境問題と法規制
2.2.6 おわりに