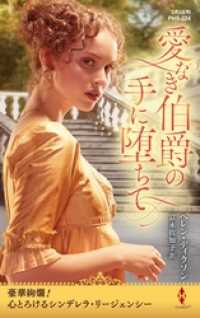出版社内容情報
★ 前書『新農薬の開発展望』から6年!その後の農薬開発の最新動向を解説!
★ ゲノミックス、コンピュータ利用など農薬開発の新しいアプローチも詳述!
★ 世界の農薬市場、米国での農薬規制の動向も紹介!
【はじめに】
農薬科学は安全で有効な農薬を創出することを目的とし,化学,生化学,植物病理学,雑草学,作物学,生態学,毒理学,毒性学,環境化学,バイオテクノロジーなど諸々の学問技術の結集,総合のアンブレアといえる。この半世紀,この分野は素晴らしい発展を遂げ,数々の優れた農薬を生み出してきた,しかし今日の情勢をみるに,先進国では農薬の科学技術は成熟期に入っている一方,社会の農薬忌避への風潮は激しくなり,規制は厳しくなる一方である。こういった情勢に対処するにはどうしたらよいか。農薬への批判ないし無理解は病害虫雑草防除の手段として農薬のみに頼ってきた過去の事実に一部根ざしている。農薬が有力な防除手段であることは否めない事実であり,無農薬というのは非現実的である。しかし農薬オンリーと無農薬とを対峙させるのではなく,できるだけ自然の力を活かすように農薬も含めて各種の防除手段を矛盾のないように組み合わせ,経済的,生態的に均衡のとれた防除を実施する総合防除が今後の方向である。この芳香を進めるとき,農薬の存在理由も他の手段との比較でおのずから明らかとなり,社会的受容がえられるのではないか。
総合防除の本旨に従えば農薬は必ずしも殺生剤(biocides)であることを要しない。そもそも農薬という定義自体がはっきりしない。
農薬登録,無登録農薬,農薬批判,無農薬,農薬の環境問題,農薬残留などをいう場合,法律,行政,国内外,使用面,消費者,研究者などにより意味するところが異なっている。農薬科学を含め防除に関連する諸学に共通する目的は生物機能の理解に基づく病害虫雑草ないし作物,有用生物の制御である。この目的を達成する総合科学は生物制御科学,生物農薬,植物成育調節剤,防菌・防黴剤,衛生・家屋害虫防除剤なども含めた広義の農薬は生物制御剤とでも称すべきであろう。
21世紀は農薬関係者すべてにとって挑戦の時代である。この時代を迎え,生物制御科学を念頭におき,この分野の研究の最新情報を提供し,今後の指針といたすべく,本書を編纂した。殺菌剤,殺虫剤,殺ダニ剤,除草剤に加えて製剤,生物農薬,フェロモン,天然物農薬に触れる。また農薬と競合し,また相補的な組換え作物の動向にも触れる。さらに農薬開発の新しいアプローチとしてゲノミックス,またコンピュータ利用に触れる。これらは総合防除・生物制御という戦略目標に対する戦術手段といえよう。これらの背景として世界の農薬市場の動向,米国での農薬規制の動向を加えた。新農薬の研究開発に活用されれば幸甚である。
2003年5月 山本 出
【執筆者一覧(執筆順)】
山本 出 東京農業大学 名誉教授
三浦一郎 クミアイ化学工業(株) 生物科学研究所
上原正浩 日本農薬(株) 総合研究所
織田雅次 日本農薬(株) 総合研究所
坂田和之 日本農薬(株) 総合研究所
藤岡伸祐 日本農薬(株) 総合研究所
井上公平 日産化学工業(株) 生物科学研究所
平井憲次 (財)相模中央化学研究所
大野竜太 (財)相模中央化学研究所
辻 孝三 製剤技研 代表
和田哲夫 アリスタ・ライフサイエンス(株) アグロフロンティア部
小川欽也 信越化学工業(株) 有機合成事業部
大澤貫寿 東京農業大学 応用生物科学部
吉田存方 三井化学(株) 研究開発部門 バイオ技術推進室
福原信裕 三井化学(株) 研究開発部門 バイオ技術推進室
野田博明 (独)農業生物資源研究所
中山 章 日本曹達(株) 小田原研究所
助川正之 日本曹達(株) 小田原研究所
高山千代蔵 (株)住化技術情報センター
Derek Gammon California EPA, Department of Pesticide Regulation, USA
Luis Ruzo PTRL West, California, USA
【構成および内容】
第1章 農薬研究開発の全般的動向 山本 出
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.農薬をとりまく環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.1 ジェネリック品の登録
2.2 ダイオキシン問題
2.3 外因性内分泌撹乱化学物質(環境ホルモン)
2.4 農薬の生態影響
2.5 農薬取締法の改正
2.6 有機・無農薬栽培、特定農薬
2.7 グリーン・サステナブルケミストリー
3.新しい試み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3.1 合成化合物
3.1.1 雑草害防除
3.1.2 虫害防除
3.1.3 病害防除
3.2 天然物
3.3 バイオテクノロジー
3.4 メソドロジー
第2章 殺菌剤の動向 三浦一郎
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
2.1998年以降の殺菌剤開発の動向と開発薬剤 ・・・・・27
2.1 QoI剤の開発とComplex?V阻害剤の増加
2.2 メラニン生合成阻害剤(シタロン脱水酵素阻害タイプ)の登場
2.3 べと病・疫病防除薬剤の開発
2.4 植物の全身抵抗性賦与剤
2.5 その他の開発剤
3.ターゲット(作用機構)から見た殺菌剤の動向 ・・・・・・35
3.1 呼吸系の阻害剤
3.1.1 Complex?T阻害剤およびComplex?U阻害剤
3.1.2 Complex?V阻害剤
3.1.3 cyazofamidの作用点
3.1.4 その他の阻害剤
3.2 高分子生合成系の阻害剤
3.2.1 DNA、RNA生合成阻害剤
3.2.2 タンパク質生合成阻害剤
3.2.3 細胞壁生合成阻害
3.2.4 開発のポイントと今後の展開
3.3 脂質生合成の阻害剤
3.3.1 ステロール生合成阻害剤(SBI剤)
3.3.2 スクワレンエポキシダーゼ阻害剤
3.3.3 DMI剤
3.3.4 アミン系SBI剤
3.3.5 fenhexamidの作用点
3.3.6 リン脂質生合成阻害剤
3.3.7 その他の阻害剤
3.3.8 開発のポイントと今後の展開
3.4 異化作用および低分子生合成系の阻害剤
3.4.1 トレハラーゼ阻害剤
3.4.2 メラニン生合成阻害剤
3.4.3 メチオニン生合成阻害剤
3.5 細胞膜機能の阻害剤
3.6 微小管動態の阻害剤
3.6.1 開発のポイントと今後の展開
3.7 タンパク質分泌の阻害剤
3.8 浸透圧調整経路の阻害剤
3.9 プラントアクチベーター
3.9.1 開発のポイントと今後の展開
3.10 新しい作用点ターゲット
4.対象病害からみた殺菌剤の開発 ・・・・・・・・・・・61
4.1 イネいもち病防除剤
4.2 べと病・疫病防除剤
4.3 灰色かび病防除剤
4.4 その他の病害
5.混合剤の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
6.今後の開発動向(求められる要件) ・・・・・・・・・・70
第3章 殺虫剤の動向 上原正浩、織田雅次、坂田和之、藤岡伸祐
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
2.ネオニコチノイド系剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
2.1 ネオニコチノイド系剤
2.2 ネオニコチノイド系剤の作用機作
3.トロパン類縁化合物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
4.昆虫生育制御(IGR)剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
4.1 ベンゾイルフェニルウレア(BPU)系剤
4.2 ジベンゾイルヒドラジン(DBH)系剤
4.3 エクダイソン様活性化合物
4.4 ジアリール複素環化合物
5.ピラゾリン系剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
6.ベンズヒドロールピペリジン(BZP)系剤 ・・・・・・・96
7.フェニルピラゾール系剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・97
8.呼吸鎖阻害剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
9.その他の新規剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
10.有機リン系剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
11.天然物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
12.最近の特許情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
第4章 殺ダニ剤の動向 井上公平
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123
2.1990年代に上市された殺ダニ剤 ・・・・・・・・・・123
2.1 呼吸作用性
2.1.1 ミトコンドリア電子伝達系complex?T阻害剤"fenpyroximate","pyridaben","tebufenpyrad","fenazaquin","pyrimidifen"
2.1.2 ミトコンドリア電子伝達系complex?V阻害剤"acequinocyl"
2.2 神経作用性
2.2.1 Cl-チャンネルアクティベーター"milbemectin"
2.3 昆虫生育調節作用(IGR)
2.3.1 脱皮阻害剤"etoxazol"
3.2000年以降に上市された殺ダニ剤 ・・・・・・・・127
3.1 bifenazate
3.2 fluacrypyrim
3.3 アカリタッチR
3.4 粘着くん80R
4.最近の開発剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
4.1 spirodiclofen
4.2 spiromesifen
4.3 CL900167
4.4 ダニサラバ(OK5101)
5.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132
第5章 除草剤・植物成長調節剤の動向 平井憲次、大野竜太
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135
2.アセチルCoAカルボキシラーゼ(ACCase)阻害剤 ・・・・・136
2.1 4-アリールオキシフェノキシプロピオン酸系ACCase阻害剤
2.2 シクロヘキサンジオン系ACCase阻害剤
3.アセト乳酸合成酵素(ALS)阻害剤 ・・・・・・・・・・138
3.1 スルホニルウレア系ALS阻害剤
3.1.1 フェニルスルホニル(トリアジン-2-イル)ウレア系ALS阻害剤
3.1.2 フェニルスルホニル(ピリミジン-2-イル)ウレア系ALS阻害剤
3.1.3 ピリジルスルホニル(ピリミジン-2-イル)ウレア系ALS阻害剤
3.1.4 複素環置換スルホニルウレア系ALS阻害剤
3.1.5 その他のスルホニルウレア系ALS阻害剤
3.2 トリアゾリノン系ALS阻害剤
3.3 トリアゾロピリミジン系ALS阻害剤
3.4 ピリミジニルサリチル酸系ALS阻害剤
3.5 イミダゾリノン系ALS阻害剤
3.6 ALS阻害剤の開発動向
4.プロトポルフィリノーゲン-?\オキシダーゼ(PPO)阻害剤 ・・・149
4.1 第1世代環状イミド系PPO阻害剤
4.2 第2世代環状イミド系PPO阻害剤
4.3 PPO阻害剤の最近の開発動向
4.3.1 第1世代のPPO阻害剤の開発動向
4.3.2 第2世代のPPO阻害剤の開発動向
4.3.3 複素環-複素環型PPO阻害剤の開発動向
5.カロチノイド生合成阻害剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164
5.1 PDS阻害剤
5.2 PDS阻害剤の開発動向
5.3 4-HPPD阻害剤
5.4 4-HPPD阻害剤の開発動向
6.細胞分裂阻害剤 超長鎖脂肪酸(VLCFAs)生合成阻害剤 ・・・174
6.1 超長鎖脂肪酸(VLCFAs)生合成阻害剤
6.2 VLCFAs生合成阻害剤の最近の構造展開
7.その他の阻害剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178
7.1 電子伝達系PS?U阻害剤
7.2 セルロース生合成阻害剤
7.3 脂肪酸伸長阻害剤(非ACCase阻害)
7.4 オーキシン様阻害剤
7.5 オーキシン転流阻害剤
7.6 作用機構未確認の除草剤
7.7 その他の新しい除草剤
8.植物成長調節剤(PGR)の開発動向 ・・・・・・・・・・・・181
9.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183
第6章 製剤の動向 辻 孝三
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190
2.農薬開発の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・190
3.農薬製剤の種類と剤型別生産量の推移 ・・・・・・・191
4.既存製剤の問題点と新規製剤の開発 ・・・・・・・・・194
5.新規製剤の具体例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196
5.1 水性製剤
5.2 顆粒水和剤(ドライフロアブル)
5.3 ジャンボ剤
5.4 1キロ粒剤
5.5 水面展開剤
5.6 マイクロカプセル
5.7 長期残効性箱施用粒剤
5.8 テープ製剤
5.9 農薬入り肥料
5.10 物理的防除法
6.水稲用除草剤の剤型の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・207
7.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・208
第7章 生物農薬の動向 和田哲夫
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
2.登録ガイドライン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
2.1 天敵昆虫登録について
2.2 微生物農薬の登録について
3.生物防除剤の開発における問題点 ・・・・・・・・・・214
3.1 天敵昆虫
3.1.1 開発可能な天敵昆虫種
3.1.2 日本で開発中の天敵昆虫
3.1.3 その他、有望な天敵類
3.2 微生物農薬の開発の問題点と現状
3.2.1 ウィルス剤の現状
3.2.2 糸状菌剤の開発対象菌について
3.2.3 主な登録剤、開発剤
3.2.4 バクテリア剤
3.2.5 その他のバクテリア剤の動向
3.2.6 センチュウ剤
第8章 フェロモンの動向 小川欽也
1.フェロモンとその歴史 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・226
2.フェロモンの利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・227
2.1 モニタリングトラップと大量誘殺法
2.2 交信撹乱法
3.交信撹乱剤の開発 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・231
3.1 フェロモンの同定と合成
3.2 フェロモンの製剤の開発
3.3 フェロモン製剤の登録
4.効果に影響する要因と評価方法 ・・・・・・・・・・・・235
4.1 フェロモン濃度
4.2 良い製剤
4.3 設置時期
4.4 風速
4.5 面積
4.6 その他条件
4.7 天敵
4.7.1 棉
4.7.2 米国の梨、リンゴ
4.7.3 茶
4.8 フェロモンの評価方法
4.8.1 トラップによる交信撹乱率の測定
4.8.2 交尾率測定
4.8.3 被害調査等
4.8.4 ディスペンサーの調査
4.8.5 フェロモン濃度測定
5.フェロモン利用の実例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・244
5.1 棉
5.2 リンゴ(1):コドリンガ
5.3 ブドウ
5.4 モモ
5.5 茶
5.6 リンゴ(2)
5.7 その他
第9章 天然物の動向 山本 出、大澤貫寿
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・257
2.微生物源物質の利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・258
3.植物源物質の利用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・259
3.1 農薬活性植物の探索
3.2 Ryanoids
3.3 Sabadilla
3.4 Azadirachtin
3.5 Rocaglamide
3.6 Acetogenins
3.7 不飽和アミド類
3.8 テルペノイド他
4.抵抗性誘導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
5.化学生態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・265
6.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267
第10章 遺伝子組換え作物の動向 吉田存方、福原信裕
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・274
2.遺伝子組換え作物の普及状況 ・・・・・・・・・・・・・・274
3.研究開発動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・276
3.1 第1世代GM作物開発の状況
3.1.1 除草剤耐性作物
3.1.2 害虫抵抗性作物
3.1.3 ストレス耐性および病害抵抗性作物
3.2 第2・第3世代のGM作物の開発状況
4.開発企業の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・282
5.日本における組換え作物開発の課題 ・・・・・・・・・287
6.今後の展望 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・288
第11章 昆虫ゲノム研究の害虫防除への展望 野田博明
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・293
2.昆虫ゲノム研究の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・293
2.1 全ゲノム解析
2.2 cDNA/EST解析
2.3 昆虫・ダニ関連微生物のゲノム解析
2.4 昆虫ゲノム研究の今後とポストゲノム研究
3.ゲノム創農薬 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・299
3.1 ゲノム研究の成果を利用した農薬開発
3.2 標的分子探索研究
3.3 標的分子のバリデーション
3.4 アッセイ系の構築とリード化合物の探索
3.5 標的分子の高次構造解析と薬剤のデザイン
3.6 殺虫剤の抵抗性問題と安全性
4.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・304
第12章 創薬研究へのコンピュータ利用の動向 中山 章、助川正之
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・307
2.Hansch-Fujita法の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・307
3.3次元構造活性相関の動向 ・・・・・・・・・・・・・・・・308
3.1 CoMFA法の概要
3.2 農薬分野へのCoMFA法の利用
3.3 その他の3D-QSAR
4.作用点タンパクの構造と創薬 ・・・・・・・・・・・・・・・311
5.研究事例にみる農薬のコンピュータ創薬 ・・・・・・314
5.1 アゾール系殺菌剤
5.2 Protox阻害除草剤
5.3 ネオニコチノイド系殺虫剤
6.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・317
第13章 世界の農薬市場の動向 高山千代蔵
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・322
2.農業生産の現状と今後 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・323
2.1 世界の状況
2.1.1 最近の状況
2.1.2 今後の予測
2.2 日本の状況
3.世界の農薬市場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・329
3.1 全般
3.2 薬剤分野別市場
3.2.1 除草剤
3.2.2 殺虫剤
3.2.3 殺菌剤
3.2.4 その他農薬
3.3 地域別・国別市場
3.3.1 全般
3.3.2 米国
3.3.3 日本
3.4 農業バイテク製品市場
4.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・338
第14章 米国の農薬規制の動向(英文) Denek Gammon, Luis Ruzo
1.INTRODUCTION ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・340
2.FOOD QUALITY PROTECTION ACT (FQPA) ・・・341
2.1 INTRODUCTION
2.2 HEALTH-BASED SAFETY STANDARDS FOR PESTICIDE RESIDUES IN FOOD
2.2.1 Aggregate Exposure(s)
2.2.2 Cumulative Exposure(s)
2.2.3 Pre-/Post Natal Sensitivity
2.3 LIMITATIONS ON BENEFITS CONSIDERATIONS
2.4 TOLERANCE RE-EVALUATION
2.5 ENDOCRINE DISRUPTORS
2.5.1 SAB / SAP Input to USEPA
2.5.2 Final Proposal for selection Criteria
2.5.3 Selection Criteria
2.5.4 Estimation of Exposure
2.5.5 Residential use Pathways
2.5.6 Occupational Exposure Pathways
2.6 REGISTRATION OF SAFER PESTICIDES
2.7 PUBLIC HEALTH PESTICIDES
2.8 CANCER-CAUSING PESTICIDES
2.9 DEVELOPMENTAL NEUROTOXICITY (DNT)
2.10 PRESTICIDE TOXICITY IN INFANTS / CHILDREN
2.11 HUMAN TESTING OF PESTICIDES
2.12 HPV / INERT INGREDIENTS
2.13 PESTICIDE AND INERT INGREDIENTS (FORMULATIONS) DATA COMPENSATION
3.CONCLUSIONS ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・366