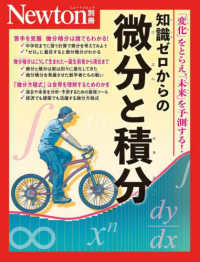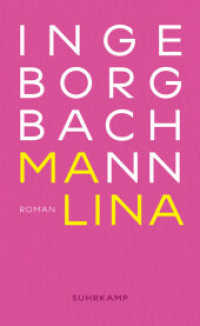出版社内容情報
★ リチウムイオン二次電池が商品化されて、はや10年が経過しようとしている。この間の開発経緯と基本材料を紹介!
★ また、今後の二次電池開発の行方と現在の二次電池最新開発状況を各分野の第一線の執筆陣が詳しく解説!!
【執筆者一覧(執筆順)】
吉野 彰 旭化成㈱ エレクトロニクスカンパニー 電池材料事業開発室 室長
山本 陽久 日本ゼオン㈱ 新事業開発部 部長
高田 和典 (独)物質・材料研究機構 物質研究所 主幹研究員
近藤 繁雄 (独)物質・材料研究機構 物質研究所 特別研究員
渡辺 遵 (独)物質・材料研究機構 物質研究所 所長
武田 保雄 三重大学 工学部 分子素材工学科 教授
佐藤 正春 日本電気㈱ 機能材料研究所 主任研究員
泉 浩人 ステラケミファ㈱ 研究部 サブマネージャー
大野 弘幸 東京農工大学 工学部 教授
藤本 宏之 大阪ガス㈱ 開発研究部 課長
山木 準一 九州大学 先導物質化学研究所 教授
岡田 重人 九州大学 先導物質化学研究所 助教授
山崎 信幸 日本化学工業㈱ 電材研究部 部長
世界 孝二 ソニー㈱ コアテクノロジー&ネットワークカンパニーエナジーカンパニー 開発部門 応用開発部
辻岡 則夫 旭化成㈱ 機能膜事業部 新事業開発グループ グループ長
妻藤 陽子 旭化成㈱ 機能膜事業部 ハイポア技術開発部
荒井 創 NTT先端技術総合研究所 企画部 担当部長
櫻井 庸司 NTTマクロシステムインテグレーション研究所 スマートデバイス研究部 主幹研究員 グループリーダー
直井 勝彦 東京農工大学大学院 工学研究科応用化学専攻 教授
荻原 信宏 東京農工大学大学院 工学研究科応用化学専攻
昆野 昭則 静岡大学 工学部 物質工学科 助教授
藤波 達雄 静岡大学 工学部 物質工学科 教授
吉武 秀哉 宇部興産㈱ 機能材料事業部
西山 利彦 NECトーキン㈱ 技術開発本部 マネージャー
金子志奈子 NECトーキン㈱ 技術開発本部
芳尾 真幸 佐賀大学 機能物質化学科 教授
辰巳 国昭 (独)産業技術総合研究所 関西センター 生活環境系特別研究体 次世代電池研究グループ
竹下 秀夫 インフォメーションテクノロジー総合研究所 副社長
【構成および内容】
第1編 総集編
第1章 リチウム系二次電池の技術と材料 吉野 彰
1.はじめに
2.リチウムイオン二次電池の技術と材料はこのようにして決まってきた―リチウムイオン二次電池の開発経緯―
2.1 なぜ負極に炭素材料が選定されたのか
2.2 負極表面のSEIはなぜ必要だったのか
2.3 なぜ正極はLiCoO2でなければならなかったのか
2.4 電解液はなぜ限定されているのか
2.5 電極構造はどういう理由で決まったのか
2.6 バインダーは特殊なポリマーに限定されるのか
3.まとめ
第2章 リチウム系二次電池の原理と基本材料構成 吉野 彰
1.はじめに
2.リチウムイオン二次電池の原理
3.リチウムイオン二次電池の基本材料構成とこの10年の技術開発の流れ
4.この10年の要素技術別開発の流れ
4.1 正極材料
4.2 負極材料
4.3 正負組合せ
4.4 電解液
4.5 セパレータ
4.6 固体電解質
4.7 バインダー
5.まとめ
第2編 リチウム系二次電池材料
第3章 コバルト系正極材料 山崎信幸
1.はじめに
1.1 コバルト酸リチウム
1.2 コバルト価格の動向
2.コバルト酸リチウムの構造と特徴
2.1 コバルト酸チリウムの結晶構造
2.2 コバルト酸リチウムの電気化学的特徴
3.コバルト酸リチウムの開発と工業生産の経緯
3.1 合成方法の経緯
3.2 工業的製造プロセスとこの10年の流れ
4.コバルト系正極 今後の方向性
4.1 高性能化を目指した方策
5.おわりに
第4章 ニッケル系正極材料 荒井 創,櫻井庸司
1.無置換LiNiO2
2.コバルト置換体
3.コバルト以外の元素置換体
4.LiNiO2系以外のニッケル系電極材料
第5章 マンガン系正極材料 芳尾真幸
第6章 その他の無機系正極材料 山木準一,岡田重人
1.はじめに
2.ポリアニリン系正極活物質群
第7章 有機系正極材料 直井勝彦
1.はじめに
2.有機系正極材料の歴史
3.有機系正極材料のエネルギー貯蔵原理
4.有機系材料と無機系材料の電気化学特性の比較
5.導電性高分子材料
5.1 導電性高分子材料の分類,特性比較
5.2 導電性高分子正極材料の報告例
5.2.1 ポリアニリン
5.2.2 ポリアセン
5.3 導電性高分子材料の問題点
6.有機硫黄系材料
6.1 有機硫黄系材料の分類,特性比較
6.2 有機硫黄系正極材料の報告例
6.2.1 有機ジスルフィド化合物
6.2.2 カーボンスルフィド化合物
6.2.3 単体硫黄
6.3 有機硫黄系材料の問題点
6.4 複素環をベースとした新たな材料・電極設計
6.4.1 高エネルギー密度化の為のアプローチ
6.4.2 高パワー密度化の為のアプローチ
6.4.3 サイクル特性向上の為のアプローチ
6.5 主なLithium Sulfur Battery開発動向及び特性比較
7.有機系材料の新たな展開
8.今後期待される材料・技術
8.1 リチウム二次電池正極材料への応用
8.2 水系レドックスキャパシタ電極材料への応用
第8章 炭素系負極材料 藤本広之
1.はじめに
2.黒鉛系材料
3.低温焼成炭素材料
4.難黒鉛系材料
5.おわりに
第9章 合金系負極材料 辰巳国昭
第10章 その他の非炭素系負極材料 武田保雄
1.はじめに
2.新しい負極探索の流れ-非晶質SnO負極
3.高容量窒化物負極-Li2.6Co0.4N
4.Li2.6Co0.4Nと酸化物(SnOやSiO)の複合負極による初期不可逆容量の低減
5.CoOに代表される非挿入型酸化物負極
第11章 電解液とその材料 吉武秀哉
第12章 電解液溶質材料 泉 浩人
1.はじめに
2.電解液溶質材料
3.LiPF6
3.1 開発初期の状況
3.2 製法
3.3 安定性
3.4 不純物
3.5 LiPF6溶液の物性
4.今後の方向性
第13章 バインダー材料 山本陽久
1.はじめに
2.ゴム系バインダーの性能
3.ゴム系負極バインダー:BM-400B
4.ゴム系正極バインダー:BM-500B
5.おわりに
第14章 ポリマー電解質 世界孝二
1.緒言
2.ポリマー電解質(高分子固体電解質)
2.1 完全固体型(純正;有機溶媒フリー)
2.2 ゲル状ポリマー電解質
3.リチウムイオンポリマー二次電池
第15章 無機固体電解質 高田和典,近藤繁雄,渡辺 遵
1.はじめに
2.リチウムイオン電池の実用化がもたらした変化
3.最近のリチウムイオン伝導性無機固体電解質に関する研究
4.今後の可能性-結びに代えて-
第16章 セパレータ材料 辻岡則夫,妻藤陽子
1.はじめに
2.電池技術の変遷とセパレータ
2.1 セパレータに要求される基本特性
2.2 電池技術変遷とセパレータ
2.2.1 液系LIB
2.2.2 リチウムイオン・ポリマー二次電池(以下LIP)
3.セパレータ製造技術
3.1 多孔化技術
3.1.1 相分離法
3.1.2 延伸開孔法
3.1.3 溶媒膨潤開孔法
3.2 フィルム化技術
3.2.1 フラット延伸
3.2.2 チューブラー延伸
3.2.3 積層微多孔フィルム
4.セパレータ特性
4.1 機械特性
4.2 透過性
4.3 熱特性
5.特許出願からみたセパレータの開発の流れ
5.1 LIB用セパレータへの最近の要求
5.2 セパレータ関連出願件数の推移
5.3 セパレータメーカーからの出願
5.4 電池メーカーからの出願
6.まとめ
第3編 新しい蓄電素子とその材料
第17章プロトン電池とその材料 西山利彦,金子志奈子
1.はじめに
2.電気二重層コンデンサーと電池
2.1 電気二重層
2.2 金属酸化物
2.3 導電性高分子
3.プロトン交換型導電性高分子
4.電池材料の探索
5.電極活物質の安定性
6.インドール系3量体と電子伝導性
7.キノキサリン系ポリマーと電子伝導性
8.電池特性パワー
9.電池特性低温
10.電池特性・サイクル
11.用途
12.おわりに
第18章ラジカル電池とその材料 佐藤正春
1.はじめに
2.ラジカル材料と有機ラジカル電池
3.有機ラジカル電池の試作とその性質
3.1 有機ラジカル化合物PTMAの合成
3.2 有機ラジカル電池の作製
3.3 PTMAの電気化学的性質
3.4 PTMAを正極活物質とする有機ラジカル電池の性質
4.まとめと今後の課題
第19章光二次電池とその材料 昆野昭則,藤波達雄
1.はじめに
2.光二次電池の構造と反応機構
3.有機薄膜光二次電池
4.おわりに
第20章イオン性液体 大野弘幸
1.はじめに
2.イオン性液体とは
3.合成法
3.1 オニウム塩
3.2 モデル系の簡便な合成
4.電解質溶液としての展開
4.1 電解質溶液の代替物
4.2 Zwitterionic liquid
4.3 アルカリ金属イオン性液体
5.高分子ゲル型電解質
6.イオン性液体の高分子化
6.1 ポリカチオン型
6.2 ポリアニオン型
6.3 コポリマー型
7.将来展望
第4編 海外の状況
第21章海外でのLi系二次電池材料の動向 竹下秀夫
1.Liイオン二次電池の世界市場の概要
2.Liイオン二次電池の主要構成材料の世界市場
2.1 正極活物質
2.2 負極活物質
2.3 セパレータ
2.4 電解液
-

- 和書
- 風流べらぼう剣 文春文庫