出版社内容情報
★ PEFCの動向や様々な水素源の燃料電池の進展を詳述!
★ 燃料改質技術,水素透過膜,プロトン伝導膜などの要素技術も網羅!
★ エネルギー技術と燃料電池の関係,マイクロガスタービンと燃料電池のつながりなども解説!
はじめに
1997年11月12日付日本経済新聞朝刊に、全面広告で当時の独ダイムラー・ベンツ社Dr.Ferdinand Panik 副社長が、2005年を目標に燃料電池車の大量生産体制を整え実用化すると発表し、エネルギー関係者に衝撃を与えた。直後に日本のトヨタ,ホンダも2003年には限定的な市場導入を開始すると公表した。他方,松下,三洋電機,東芝などの家電業界も家庭用の燃料電池を2005年に市場に投入するべく,2002年から実際の住宅で運転試験を行うと発表している。
大量生産を得意とする自動車と家電の両業界が,本格的に燃料電池の生産を始めれば価格も急速に低下してゆくことであろう。両業界が開発している燃料電池は固体高分子型と呼ばれる形式のもので大量生産に適している。燃料電池の実用化と普及に向けて2001年3月19日には正会員65社,賛助会員21社が参加して「燃料電池実用化推進協議会」も発足した。
原子力を中心とする大型発電所は,大量の復水器冷却水を必要とするので,日本ではこれまで都市から遠く離れた海岸に立地するのが普通であり,発電所の排熱,即ち温排水を利用することは不可能であった。情報化社会が進展し,且つ快適な生活を望む人々の欲求が増して行くのは当然であり,電力の需要は増大する一方であろうが,その需要に巨大発電のみで対応しようとすれば国全体のエネルギー利用効率は年々低下してゆかざるを得ない。事実,1975年度の国全体のエネルギー効率は37%であったが,1998年には34%に低下している。その理由はひとえに,この間の電力化率,即ち電力をつくるために投入される1次エネルギー量が28%から48%に増え,それに伴って温排水損失が圧倒的に増えてきたからである。つまり現在のままの巨大電力供給システムのみでは,いくら頑張っても省エネルギーは構造的に成り立たないのである。これを抜本的に変革するためには,熱の需要地に近接して発電所を立地させ,発電後の排熱を「熱」として利用する分散小型のコージェネレーションを普及させる以外に方法はない。究極は各家庭で発電し,その排熱で風呂や暖房をする以外に方法はないのである。
原子力を中心とする巨大システムを親亀とすれば,その背中に産業用コージェネレーションやIPPなどのシステムが子亀として乗り,更にその背中に孫亀としてマイクロガスタービンなどを用いた業務用コージェネレーションが乗り,最後に家庭用の燃料電池コージェネレーションが曾孫亀として乗って互いに有機的に連系する。それぞれが作り出す電力と熱の積分量が,日本全体として最小になるようにITを駆使して中央制御すれば,省エネルギーは進み二酸化炭素の発生も大きく抑制できることは間違いない。親亀がこければ皆こけるが,このような「亀の子エネルギー供給システム」の構築が,筆者の多年にわたる夢でだった。これまでは理屈はよくてもハードウェアが伴わず夢にすぎなかったのである。マイクロガスタービンや燃料電池などハードウェアの技術が進展したことによって,孫亀と曾孫亀までのハードが揃い,いよいよ真のエネルギーベストミックスが眼の黒いうちに実現可能となることは筆者の心からの喜びである。
これらの技術も,それを支える燃料の供給が確保されなければ絵に描いた餅に終わってしまう。燃料電池の燃料は水素であり,マイクロガスタービンは天然ガスが主要な燃料であるが,これら燃料の輸送にはパイプラインが必須である。一日も早く,水素の製造,輸送,供給のインフラを構築させることも併せて推進してゆかなければならない。
本書が分散型エネルギーシステムとそれを支える燃料電池技術,さらに燃料としての天然ガス,更には水素の生産・輸送・供給技術の進展に貢献できれば,監修者としての喜び,これにすぐるものはない。
2001年7月 監修:平田 賢
執筆者一覧(執筆順)
平田 賢 芝浦工業大学 システム工学部 教授/東京大学 名誉教授/
日本コージェネレーションセンター 会長/アジアパイプライン研究会 副会長
矢野伸一 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 水素・アルコール・バイオマス技術開発室
主任研究員
田畑 健 大阪ガス(株) 家庭用コージェネレーションプロジェクト部 開発第1チーム マネージャー
ヨハネス・エプナー ダイムラー・クライスラー社 燃料電池プロジェクト部門 ディレクター
森井淺治 日本石油ガス(株) 販売部 技術開発グループ
相澤 智 日本石油ガス(株) 販売部 技術開発グループ
市川 勝 北海道大学 触媒化学研究センター 教授
池松正樹 日石三菱(株) 新エネルギー本部 FC事業本部 部長
堀米 孝 (株)バイオスフィア科学研究所 会長
日比野高士 独立行政法人 産業技術総合研究所 中部センター セラミックス研究部門 主任研究員
岡田 治 大阪ガス(株) 開発研究部 シニアリサーチャー
越後満秋 大阪ガス(株) 家庭用コージェネレーションプロジェクト部 開発第1チーム
幾島賢治 (財)石油産業活性化センター 技術業務部 主任研究員 工学博士
多井 勉 神鋼パンテツク(株) 技術開発本部 主席研究員
関 務 東京ガス(株) 研究開発部 基礎技術研究所 主任研究員
安田 勇 東京ガス(株) 研究開発部 基礎技術研究所 主幹研究員
脇添雅信 旭化成(株) 製品技術研究所
吉武 優 旭硝子(株) 中央研究所 主幹研究員
野上正行 名古屋工業大学 教授
島宗孝之 島宗技術士事務所
石川忠夫 (財)電力中央研究所 需要家システム部 上席研究員
三浦千太郎 東京ガス(株) エネルギーソリューション事業部 エネルギーサービス部部長・理事
鈴木健二郎 京都大学 工学研究科 教授
岩井 裕 京都大学 工学研究科 助手
金 在煥 Seoul National University Turbo and Power Machinery Research Center Research
Scientist
構成および内容
総論編
第1章 21世紀のエネルギー技術 ~「分散型エネルギーシステム」と燃料電池~ 平田 賢
1 地球温暖化抑止とエネルギーの安定供給
2 構造的省エネルギーの実現に向けて
3 熱のシステム利用と分散型エネルギー
4 マイクロコージェネレーションの出現
5 水素の時代へ向けて~インフラ整備の重要性~
6 おわりに~北東アジア・ガスパイプライン網の構築~
燃料電池技術の進展編
第2章 固体高分子形燃料電池 矢野伸一
1.はじめに
2.NEDOにおける平成12年度までの研究開発状況
2.1 概要
2.2 運輸・民生用高効率エネルギーシステム技術開発
2.3 燃料電池実用化のための基盤技術の開発・実証
2.4 燃料電池普及基盤整備事業および高効率燃料電池システム基盤技術開発事業
2.5 高効率燃料電池システム実用化技術開発
3.平成13年度からの研究開発計画
4.おわりに
第3章 家庭用PEFCコージェネレーションシステム 田畑 健
1.はじめに
2.家庭用PEFCコージェネレーションシステムのコンセプト
3.日本市場での家庭用PEFCコージェネレーションシステムの仕様
4.家庭用PEFCコージェネレーションシステムの技術課題
4.1 自動車用との違い
4.2 発電効率
4.3 家庭用PEFCセルスタック
5.現在の技術開発状況
5.1 セルの開発状況
5.2 改質装置及び周辺システムの開発状況
5.3 PEFCシステムの開発状況
6.今後の見通し
第4章 燃料電池自動車 ヨハネス・エプナー
1.はじめに
2.変貌するエネルギー市場
3.輸送用燃料
3.1 現状
3.2 化石燃料
3.3 代替燃料
3.4 メタノールと水素
4.輸送のための燃料電池技術
4.1 NECAR燃料電池乗用車システムの成果
4.2 燃料電池車で使用する燃料:水素,メタノール,ガソリン
4.2.1 水素
4.2.2 メタノール
4.2.3 ガソリン
4.3 燃料電池バス
4.4 XcellsisによるP3バス
4.5 ダイムラー・クライスラー・ヨーロッパ・バス運行テスト(CUTE)
4.6 P9-END
5.アイスランド~世界初の水素社会?(ECTOSプロジェクト)~
6.カリフォルニア燃料電池パートナーシップ
7.日本の燃料電池実証プロジェクト
8.今後の展望
第5章 LPG仕様燃料電池 森井淺治,相澤 智
1.はじめに
2.開発経緯
3.燃料供給フロー
4.富士電機製100kWプロジェクト
4.1 概要
4.2 プラント実証運転
4.2.1 プラント運転状況
4.2.2 低スチームカーボン比特性および抜取触媒評価
5.東芝/ONSI製200kWプロジェクト
5.1 概要
5.2 改質触媒の選定
5.3 プラント実証運転(単管式改質器)
5.3.1 プラント特性評価
5.3.2 プラント運転環境負荷特性評価
5.3.3 抜取触媒評価
5.4 プラント実証運転(新型多管式改質器)
5.4.1 プラント特性評価
5.4.2 低スチームカーボン比特性評価
6.まとめ
第6章 有機ハイドライド水素源燃料電池 市川 勝
1.液体有機ハイドライドの有用性と特性
1.1 燃料電池用の水素燃料の選択
2.液体有機ハイドライドを用いる水素貯蔵・供給システム
2.1 シクロヘキサン水素源の水素コスト、総合エネルギー効率
2.2 有機ハイドライドを利用する高速水素発生装置と触媒開発
2.3 直接シクロヘキサン燃料電池
3.有機ハイドライド利用システムの応用・展開
3.1 シクロヘキサン・デカリンハイウェー
3.2 リニーアブル電力の貯蔵・運搬に応用できる“シクロヘキサン・デカリン水素源燃料電池”
3.3 住宅用水素燃料電池システムのための水素貯蔵・供給インフラ
4.革新的な水素製造技術(直接GTL法)の開発
5.まとめと将来の展望
第7章 ガソリン水素源燃料電池 池松正樹
1.はじめに
2.燃料電池用の原燃料について
3.当社の石油燃料電池システムの開発経緯
4.固体高分子形燃料電池(PEFC)システムの実証試験
5.おわりに
第8章 廃棄物水源燃料電池 堀米 孝
1.燃料電池発電の燃料
2.燃料電池への水素燃料の主な供給方式
3.生ごみなどの有機性廃棄物から水素を作り燃料電池に供給するシステム
4.植物性廃棄物(セルロース)から水素を作り燃料電池に供給するシステム
5.燃料電池発電と高度情報通信技術(IT)を駆使したオンサイト分散型再生可能(自然)エネルギー発電の安定化複合利用システム
第9章 低温固体電解質燃料電池 日比野高士
1.はじめに
2.燃料電池の特徴
3.PEFCの概要
4.SOFCの概要
5.車両搭載用SOFCの開発動向
5.1 安定化ジルコニアの薄膜化による低温作動化
5.2 新規なセルデザインによる耐震性向上とセリア系電解質の使用による低温作動化
6.今後の課題
燃料電池の周辺技術編
第10章 燃料改質技術 田畑 健,岡田 治,越後満秋
1.はじめに
2.PAFC用天然ガス水蒸気改質プロセスの概要
3.大阪ガス式PAFC用天然ガス改質プロセス
4.CO除去技術
5.家庭用PEFCコージェネレーション用改質システム
6.天然ガス以外の炭化水素改質技術の概要と課題
7.メタノール改質技術の概要と課題
8.おわりに
第11章 燃料電池用燃料 幾島賢治
1.背景
2.改質方法
3.燃料電池用の燃料
4.燃料電池用燃料の予想
5.まとめ
第12章 PEM型水電解水素発生装置 多井 勉
1.はじめに
2.PEMによる水電解
2.1水電解の原理
2.2 電解セルの構造
2.3 電解電圧
3. HHOG
3.1 フロー
3.2 制御
3.3 純度
3.4 除湿
4.水素発生単価
5.HHOGの運転特性
5.1 水素発生量
5.2 応答性
5.3 純度
5.4 水分濃度
6.おわりに
第13章 純水素製造用水素透過膜 関 務,安田 勇
1.はじめに
2.水素透過量の算出式
3.金属系水素透過膜の水素透過性能
4.パラジウム合金の薄膜化
5.水素透過膜の応用例
6.今後の展望
第14章 プロトン伝導膜 脇添雅信
1.はじめに
2.開発の歴史
3.膜の役割
4.パーフロロスルホン酸膜
5.旭化成の研究開発状況
6.最近の開発動向
7.おわりに
第15章 イオン交換膜 吉武 優
1.はじめに
2.PEFC発電における膜の役割
3.FlemionR膜のセル特性への影響
4.新規補強膜の開発:フィブリル補強膜
5.おわりに
第16章 プロトン伝導性ガラス 野上正行
1.はじめに
2.プロトン伝導とガラス
3.ソルゲル法で作られるガラスとプロトン伝導
4.高プロトン伝導性ガラスの合成
5.高プロトン伝導性ガラスの応用
6.おわりに
第17章 バイポーラプレート(セパレータ) 島宗孝之
1.はじめに
2.セパレータの役割
3.セパレータ部の電気化学
4.セパレータ技術の現状
4.1 特許技術
4.2 最近のセパレータ技術について
5.今後のセパレータ技術について
6.おわりに
第18章 系統連系技術 石川忠夫
1.はじめに
2.分散型電源の系統連系の形態
3.分散型電源の系統連系に関する技術的課題とその対策
3.1 系統連系の課題
3.2 供給信頼度の確保および分散型電源の安定運転
3.3 電力品質の確保
3.4 安全の確保と設備保全
燃料電池とマイクロガスタービン編
第19章 マイクロタービン 三浦千太郎
1.はじめに
2.登場の背景
3.技術評価
3.1 Capstone
3.2 Honeywell(旧Allied Signal)
3.3 Ebara-Elliott
3.4 Ingersol-Rand Energy Company(IREC)
3.5 Turbec(旧Turbogen)
4.市場性とその発展性
4.1 Capstone
4.2 Honeywell
4.3 国産
5.マイクロタービンのコージェネシステム化への取り組み
5.1 温水回収システム
5.2 蒸気回収システム
5.3 ごみ乾燥機
5.4 排ガス投入型吸収式冷凍機
5.5 追い焚きバーナー付き蒸気回収システム
6.おわりに
第20章 マイクロガスタービンと燃料電池 鈴木健二郎,岩井 裕,金 在煥
1.はじめに
2.マイクロガスタービンの現状
3.固体電解質燃料電池
4.マイクロガスタービン・固体電解質燃料電池ハイブリッドサイクル
5.おわりに
目次
総論編(21世紀のエネルギー技術)
燃料電池技術の進展編(固体高分子形燃料電池;家庭用PEFCコージェネレーションシステム;燃料電池自動車 ほか)
燃料電池の周辺技術編(燃料改質技術;燃料電池用燃料;PEM型水電解水素発生装置 ほか)
燃料電池とマイクロガスタービン編(マイクロタービン;マイクロガスタービンと燃料電池)
著者等紹介
平田賢[ヒラタマサル]
芝浦工業大学システム工学部教授。東京大学名誉教授。日本コージェネレーションセンター会長。アジアパイプライン研究会副会長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
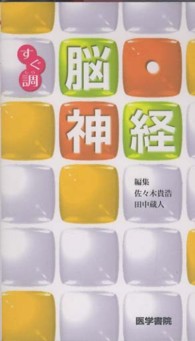
- 和書
- すぐ調 脳・神経






