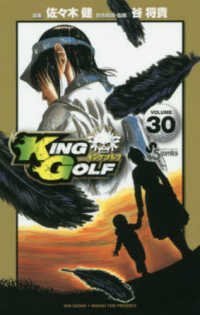出版社内容情報
☆年間10~15%成長、1,800億円市場の産業用酵素
☆新規酵素の発見、組み替えDNAによる大量生産、蛋白質工学による改質などの話題も満載
☆主要な酵素と応用製品の市場も解説
執筆者一覧(執筆順)
一島英治 創価大学 工学部 生物工学科 教授
上島孝之 ノボノルディスクバイオインダストリー(株) 研究開発部 主任研究員
尾崎明夫 協和発酵工業(株) 東京研究所 主任研究員
広原日出男 滋賀県立大学 工学部 教授
山本憲二 京都大学大学院 農学研究科 助教授
相阪和夫 協和発酵工業(株) 東京研究所
猪狩 淳 順天堂大学 医学部 臨床病理学教室 教授
手嶋眞一 東洋紡績(株) 生化学事業部
山本和巳 東洋紡績(株) 敦賀バイオ研究所
西矢芳昭 東洋紡績(株) 敦賀バイオ研究所
中野衛一 キッコーマン(株) 研究本部 副本部長
牛山正志 チッソ(株) 横浜研究所
杉本利行 (株)林原 岡山第二工場 工場長
小林幹彦 秋田県総合食品研究所 所長
田中晴生 味の素(株) 食品総合研究所 油脂・蛋白開発研究所 第2開発室 室長
本木正雄 味の素(株) 食品総合研究所 食品基盤技術研究所 所長
半澤 敏 東ソー(株) 東京研究所
宇山 浩 京都大学大学院 工学研究科 助手
小林四郎 京都大学大学院 工学研究科 教授
石脇尚武 キリンビール(株) 応用開発センター
滝澤 昇 岡山理科大学 工学部 応用化学科 助教授
内容と構成
〈総論編〉
第1章 21世紀の新規産業をつくる産業酵素 一島英治
第2章 産業用酵素の研究開発と用途拡大 上島孝之
1.産業用酵素の市場
2.洗濯用酵素
2.1 プロテアーゼ
2.2 アミラーゼ
2.3 リパーゼ
2.4 セルラーゼ
2.5 ペルオキシダーゼ
3.インディゴ漂白
4.パルプ漂白
5.バイオ精錬
6.製パン用酵素
6.1 ふっくらしたパンを作る
6.1.1 α-アミラーゼ
6.1.2 ヘミセルラーゼ
6.1.3 リパーゼ
6.2 パンの老化防止
7.フィード酵素
8.おわりに
〈医薬編〉
第3章 位置および立体特異的プロリン水酸化酵素 尾崎明夫
1.はじめに
2.HYP分析法の開発
3.プロリン水酸化酵素のスクリーニング
4.プロリン水酸化酵素の性質
5.遺伝子取得と大腸菌での活性発現
6.HYP生産プロセスの確立
6.1 2OG供給リサイクルシステムの確立
6.2 L-Pro分解経路の遮断
6.3 trans-4HYPの生産
7.おわりに
第4章 リパーゼ、エステラーゼを用いるキラルテクノロジー 広原日出男
1.加水分解酵素を用いるキラルテクノロジーの実用化要件
2.リパーゼによるエナンチオ選択反応と立体反転の組み合わせ
3.エステラーゼによる立体選択反応とラセミ化の組み合わせ
4.立体選択性触媒作用機構解明への興味
5.リパーゼの立体選択性触媒作用機構
6.エステラーゼの活性部位と作用機構
第5章 エンドグリコシダーゼの糖転位活性を用いた糖ペプチドの合成 山本憲二
1.はじめに
2.グリコシダーゼの糖転移活性
3.Endo-β-N-acetylglucosaminidaseの糖転移活性
4.Mucor hiemalis由来のEndo-β-N-acetylglucosaminidaseの糖転移反応
5.N-アセチルグルコサミニルペプチド(GlcNAc-ペプチド)の化学合成
6.糖ペプチドの合成
7.ネオ糖ペプチドの合成
8.おわりに
〈診断薬編〉
第6章 検査薬に利用する酵素の進歩 相阪和夫
1.酵素法の始まりと進展
2.微生物の新しい代謝経路の検索
2.1 新しいクレアチニンの代謝酵素
2.2 新しい尿素の代謝酵素
2.3 新しいコレステロールの酸化酵素
3.新しい微生物源の利用
3.1 中程度好熱菌の酵素の利用
3.2 超好熱菌の酵素の利用
4.遺伝子組換え技術の応用
4.1 生産性の改善とコファクター・エンジニアリング
4.2 酵素の安定性の改善
第7章 ヘリコバクターピロリ検査薬の最新動向 猪狩 淳
1.はじめに
2.H.pyloriの細菌学
3.H.pyloriの感染診断法
3.1 侵襲的方法
3.2 非侵襲的方法
4.おわりに
第8章 臨床検査用遺伝子組換え酵素の最新動向 手嶋眞一、山本和巳、西矢芳昭
1.はじめに
2.耐熱性組換えウリカーゼ
2.1 遺伝子組換えウリカーゼの生産
2.2 遺伝子組換えウリカーゼの特性
3.ウレアアミドリアーゼの生産性向上
3.1 ウレアアミドリアーゼ遺伝子のクローニング
3.2 ウレアアミドリアーゼ遺伝子のDAN配列およびアミノ酸配列
3.3 ウレアアミドリアーゼの発現
4.変異型サルコシンオキシダーゼ
4.1 サルコシンオキシダーゼ遺伝子のクローニング
4.2 サルコシンオキシダーゼ遺伝子のSitedirected mutagenesis
1.3 改革サルコシンオキシダーゼの特性
5.おわりに
第9章 蛍のルシフェラーゼ 中野衛一
1.はじめに
2.蛍の発光反応
3.ホタル・ルシフェラーゼファミリー
4.進化するルシフェラーゼ
5.清浄度検査
6.微生物汚染度の測定
7.特定菌の検査
8.生物発光酵素免疫測定法
9.光の利用
10.おわりに
第10章 食品検査キットの最新動向 牛山正志
1.はじめに
2.微生物検査キット
3.トキシン類
4.農薬・環境汚染物質
5.抗菌性物質・薬剤
6.その他
7.おわりに
〈食品編〉
第11章 マルトオリゴシルトレハロース生成酵素、トレハロース遊離酵素とトレハロース製造への応用
杉本利行
1.はじめに
2.トレハロース生産菌の検索と酵素の精製
3.マルトオリゴシルトレハロース生成酵素(MTSase)の性質
4.トレハロース遊離酵素(MTHase)の性質
5.デンプンからのトレハロース製造への応用
6.おわりに
第12章 サイクロデキストラン合成酵素 小林幹彦
1.サイクロデキストラン合成酵素
2.サイクロデキストラン
3.CIの応用研究
第13章 トランスグルタミナーゼとその食品加工への応用 田中晴生、本木正雄
1.はじめに
2.TGaseの性質
2.1 反応メカニズム
2.2 TGaseの自然界における分布
2.3 微生物由来TGaseの発見
2.4 TGaseの酵素化学的性質
2.5 一次構造,活性中心
2.6 TGaseによる蛋白質ゲル化とその特徴
2.7 ε‐(γ‐Glu)Lys結合の測定
3. TGase製剤「アクティバ」
3.1 畜肉加工
3.2 水産練り製品
3.3 接着製剤
3.4 麺用製剤
3.5 豆腐
4.おわりに
第14章 酵素法によるアスパルテームの生産 半澤 敏
1.はじめに
2.酵素法によるAPMの合成
3.サーモライシンの改良
3.1 サーモライシン
3.2 変異導入のストラテジーと変異の導入
3.3 変異体酵素の活性評価
4.縮合反応系の改良
4.1 基質濃度比の最適化
4.2 溶媒添加
5.おわりに
第15章 ペルオキシダーゼ触媒による新規ポリフェノールの合成 宇山 浩、小林四郎
1.はじめに
2.ペルオキシダーゼ
3.フェノール類の酵素触媒重合
4.可溶性ポリフェノールの合成
5.ポリ(フェニレンオキシド)の合成
6.メタクリル基含有ポリフェノールの合成
7.新しい重合システムの構築
8.おわりに
第16章 酵母の有効活用技術の多様性 石脇尚武
1.はじめに
1.1 分類上の位置づけ
1.2 酵母の恩恵
2.酵母の食品・飼料用途の概括論
2.1 副生されるビール酵母
2.2 食品としての生理的意義
2.3 飼料としての生理的意義
3.4 食品における物性的機能
3.酵母マイクロカプセルについて
3.1 序論
3.2 製法
3.3 酵母マイクロカプセルの特性
3.4 水産飼料への応用
3.5 ノーカーボン紙への応用
4.おわりに
第17章 畜産飼料添加酵素フィターゼ 滝澤 昇
1.はじめに
2.フィターゼとは
3.フィターゼ処理による飼料中のフィチン態リンの有効利用
3.1 フィターゼの飼料添加効果
3.2 麹菌発酵処理飼料の効果
4.遺伝子組み換え技術とフィターゼ
5.おわりに
〈市場編〉
第18章 産業用酵素の市場動向
<酵素>
カタラーゼ
SOD
リパーゼ
ペクチナーゼ
ラクターゼ
α-グルコシダーゼ
ジアスターゼ
グルコアミラーゼ
セルラーゼ
ヘミセルラーゼ
アルカリプロテアーゼ
パパイン
キモシン
トランスグルタミナーゼ
<応用製品>
トレハロース
ルチン
グルカゴン
グルタチオン
L-トリプトファン
プロスタグランジン
5-アミノレブリン酸
ポリ乳酸
カルタミン
加水分解シルク
コラーゲン
エリスリトール
ステビア甘味料
アスタキサンチン
キシリトール
酵母エキス
ポリデキストロース
L-グルタミン酸ナトリウム
乳酸菌
-

- 電子書籍
- 銀牙伝説ノア 9