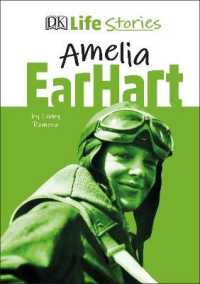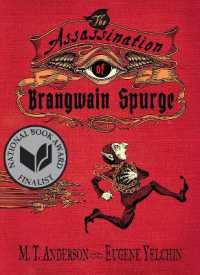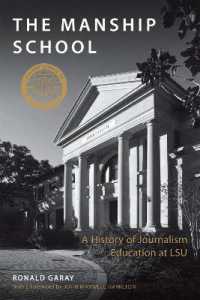出版社内容情報
構成および内容
第1章 総論 高分子環境情報研究所 草川 紀久
1 自動車と高分子材料の世紀-発展の経緯と構造変化
1・1はじめに
2 自動車産業の発展とその環境変化
2・1 20世紀-自動車と高分子材料の世紀
2・2 自動車産業の発展経緯
2・3 日本の自動車産業の発展経緯
2・4 我が国の自動車産業の現状と今後の展望
3 高分子材料の興隆と自動車用途の現状
3・1 高分子材料の開発経緯
3・2 自動車のプラスチック化の進展
3・3 高分子材料の自動車用途の現状
3.3.1内装材料
3.3.2外装・外板材料
3.3.3機能・構造部品材料
4 自動車用高分子材料の今後の展望
第2章 樹脂・エラストマー材料
1 樹脂材料の自動車用途の現状と将来動向 高分子環境情報研究所 草川 紀久
1・1はじめに
1・2樹脂材料の分類と特徴
1・3樹脂材料の自動車用途の需要推定
1・4樹脂別自動車用途概観
1・4・1汎用熱可塑性樹脂
(1)ポリエチレン(PE)
(2)ポリプロピレン(PP)
(3)ポリ塩化ビニル(PVC)
(4)スチレン系樹脂(PS,AS,ABS)
(5)メタクリル樹脂(PMMA)
1・4・2汎用エンプラ(汎用エンジニアリングプラスチック)
(1)ポリアミド(PA)
(2)ポリアセタール(ポリオキシメチレン;POM)
(3)ポリカーボネート(PC)
(4)変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)
(5)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
1・4・3特殊エンプラ
(1)ポリフェニレンスルフィド(PPS)
(2)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
(3)ポリアリレート(PAR)
(4)ポリエーテルイミド(PEI)
(5)ポリアミドイミド(PAI)
(6)その他
1・4・4今後の展望
1・4・5熱硬化性樹脂
(1)フェノール樹脂(PF)
(2)ポリウレタン(PUR)
(3)不飽和ポリエステル樹脂(UP)
1・4・6自動車の樹脂化の今後の展望と課題
2 エラストマー材料の自動車用途の現状と将来動向 日本ゼオン 相村 義昭
2・1はじめに
2・2自動車用ゴム部品の現状と材料動向
2・2・1タイヤ用材料
2・2・2外装・内装・窓枠材料
2・2・3空気・水・ブレーキ系材料
2・2・4潤滑油系
2・2・5燃料系ゴム材料
2・2・6防振用材料
2・2・7ブーツ用材料
2・2・8エアコンディショニング系材料
2・2・9ベルト用材料
2・3まとめと今後の動向
3 自動車のPP化と材料統合 日産自動車 田代 寛
4 自動車とプラスチック いすゞ自動車 河西 純一
4・1自動車の市場動向とプラスチック化動向
4・2環境保護(リサイクル、省資源と有害物質排出量削減)と自動車のプラスチック化
4・3永遠の課題(軽量化、低コスト化、プラスアルファ)と自動車のプラスチック化
第3章 材料別開発動向
1 汎用樹脂 チッソ 森 欣弥
1・1はじめに
1・2自動車部品における汎用樹脂の使用
1・3自動車部品用大型汎用樹脂の特長
1・3・1ポリプロピレン樹脂(PP)
1・3・2ABS樹脂(ABS)
1・3・3塩ビコンパウンド
1・4外装部品用材料の開発
1・4・1バンパー用材料
1・4・2その他の外装部品用材料
1・5内装部品用材料の開発
1・5・1インストルメントパネルおよび関連部品材料
1・5・2その他の内装用部品材料
1・6機能部品用材料の開発
1・7PVCコンパウンドからの材料転換
1・8今後
1・8・1アロイ化技術の追求
1・8・2メタロセン系エラストマーおよびプラスチックスの登場
1・8・3新規のPP系コンパウンド
1・8・4リサイクル材料技術
1・9おわりに
2 汎用エンプラ 帝人 弘中 克彦
2・1はじめに
2・2ポリアミド(PA)
2・3ポリカーボネート(PC)
2・4ポリアセタール(POM)
2・5変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)
2・6ポリブチレンテレフタレート(PBT)
2・7おわりに
3 特殊エンプラ その1 東レ(株)樹脂研 石王 敦
3・1まえがき
3・2PPS樹脂の自動車分野への適用例
3・3自動車用グレード開発
(1)高接着性グレード
(2)ブロー成形グレード
(3)高靱性グレード
3・4その他特殊エンプラの動向
3・5今後
4 特殊エンプラ その2 出光マテリアル 加来 祐二
4・1はじめに
4・2ポリフェニレンサルファイド(PPS)
4・2・1 PPSの特徴
4・2・2自動車分野の用途例
4・2・3材料開発動向
4・2・4今後の課題・展望
4・3ポリエーテルニトリル(PEN)
4・3・1PENの特徴
4・3・2自動車分野の用途例
4・3・3材料開発動向
4・3・4今後の課題・展望
4・4おわりに
4 熱可塑性エラストマー JSR 竹村 泰彦
5 天然ゴム・合成ゴム ブリヂストン 上嶋 祥元
5・1はじめに 鍬本 賢二
5・2天然ゴム
5・2・1天然ゴムと防振ゴム
5・2・2防振ゴムの種類とその要求特性
(1)エンジンマウント
(2)サスペンションブッシュ
(3)トーショナルダンパー
(4)センターベアリングサポート
5・2・3防振ゴムにおけるNRの活用状況
(1)エンジンマウント用ゴムの耐熱性向上
(2)エンジンマウント用ゴムの高ロス低動倍化
(3)サスペンションブッシュ用ゴムの低動倍率化
(4)ビスカスラバーダンパー用ゴムのシリコンオイルとの相互作用
(5)センターベアリングサポート用ゴムの耐オゾン性向上
5・2・4今後の課題
5・3合成ゴム
5・3・1各種合成ゴムの性質
5・3・2自動車用ホースへの用途開発動向
(1)燃料系
(2)潤滑油系
(3)空気、水、ブレーキ系
(4)フレオン系
5・3・3まとめと今後の展望
6 ポリマーアロイ 工学院大学 伊澤 慎一
6・1はじめに
6・2樹脂材料の複合化による高性能化高機能化の流れ
6・3ポリマーアロイ化技術のこれまでと今後
6・4自動車用途向け高性能化・高機能付与とアロイ化技術
(1)耐薬品性
(2)強度特性
(3)耐熱性
(4)耐衝撃性
(5)難燃性
(6)制電性
6・5今後の展開
第1章 総論 高分子環境情報研究所 草川 紀久
1 自動車と高分子材料の世紀-発展の経緯と構造変化
1・1はじめに
2 自動車産業の発展とその環境変化
2・1 20世紀-自動車と高分子材料の世紀
2・2 自動車産業の発展経緯
2・3 日本の自動車産業の発展経緯
2・4 我が国の自動車産業の現状と今後の展望
3 高分子材料の興隆と自動車用途の現状
3・1 高分子材料の開発経緯
3・2 自動車のプラスチック化の進展
3・3 高分子材料の自動車用途の現状
3.3.1内装材料
3.3.2外装・外板材料
3.3.3機能・構造部品材料
4 自動車用高分子材料の今後の展望
第2章 樹脂・エラストマー材料
1 樹脂材料の自動車用途の現状と将来動向 高分子環境情報研究所 草川 紀久
1・1はじめに
1・2樹脂材料の分類と特徴
1・3樹脂材料の自動車用途の需要推定
1・4樹脂別自動車用途概観
1・4・1汎用熱可塑性樹脂
(1)ポリエチレン(PE)
(2)ポリプロピレン(PP)
(3)ポリ塩化ビニル(PVC)
(4)スチレン系樹脂(PS,AS,ABS)
(5)メタクリル樹脂(PMMA)
1・4・2汎用エンプラ(汎用エンジニアリングプラスチック)
(1)ポリアミド(PA)
(2)ポリアセタール(ポリオキシメチレン;POM)
(3)ポリカーボネート(PC)
(4)変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)
(5)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
1・4・3特殊エンプラ
(1)ポリフェニレンスルフィド(PPS)
(2)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
(3)ポリアリレート(PAR)
(4)ポリエーテルイミド(PEI)
(5)ポリアミドイミド(PAI)
(6)その他
1・4・4今後の展望
1・4・5熱硬化性樹脂
(1)フェノール樹脂(PF)
(2)ポリウレタン(PUR)
(3)不飽和ポリエステル樹脂(UP)
1・4・6自動車の樹脂化の今後の展望と課題
2 エラストマー材料の自動車用途の現状と将来動向 日本ゼオン 相村 義昭
2・1はじめに
2・2自動車用ゴム部品の現状と材料動向
2・2・1タイヤ用材料
2・2・2外装・内装・窓枠材料
2・2・3空気・水・ブレーキ系材料
2・2・4潤滑油系
2・2・5燃料系ゴム材料
2・2・6防振用材料
2・2・7ブーツ用材料
2・2・8エアコンディショニング系材料
2・2・9ベルト用材料
2・3まとめと今後の動向
3 自動車のPP化と材料統合 日産自動車 田代 寛
4 自動車とプラスチック いすゞ自動車 河西 純一
4・1自動車の市場動向とプラスチック化動向
4・2環境保護(リサイクル、省資源と有害物質排出量削減)と自動車のプラスチック化
4・3永遠の課題(軽量化、低コスト化、プラスアルファ)と自動車のプラスチック化
第3章 材料別開発動向
1 汎用樹脂 チッソ 森 欣弥
1・1はじめに
1・2自動車部品における汎用樹脂の使用
1・3自動車部品用大型汎用樹脂の特長
1・3・1ポリプロピレン樹脂(PP)
1・3・2ABS樹脂(ABS)
1・3・3塩ビコンパウンド
1・4外装部品用材料の開発
1・4・1バンパー用材料
1・4・2その他の外装部品用材料
1・5内装部品用材料の開発
1・5・1インストルメントパネルおよび関連部品材料
1・5・2その他の内装用部品材料
1・6機能部品用材料の開発
1・7PVCコンパウンドからの材料転換
1・8今後
1・8・1アロイ化技術の追求
1・8・2メタロセン系エラストマーおよびプラスチックスの登場
1・8・3新規のPP系コンパウンド
1・8・4リサイクル材料技術
1・9おわりに
2 汎用エンプラ 帝人 弘中 克彦
2・1はじめに
2・2ポリアミド(PA)
2・3ポリカーボネート(PC)
2・4ポリアセタール(POM)
2・5変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE)
2・6ポリブチレンテレフタレート(PBT)
2・7おわりに
3 特殊エンプラ その1 東レ(株)樹脂研 石王 敦
3・1まえがき
3・2PPS樹脂の自動車分野への適用例
3・3自動車用グレード開発
(1)高接着性グレード
(2)ブロー成形グレード
(3)高靱性グレード
3・4その他特殊エンプラの動向
3・5今後
4 特殊エンプラ その2 出光マテリアル 加来 祐二
4・1はじめに
4・2ポリフェニレンサルファイド(PPS)
4・2・1 PPSの特徴
4・2・2自動車分野の用途例
4・2・3材料開発動向
4・2・4今後の課題・展望
4・3ポリエーテルニトリル(PEN)
4・3・1PENの特徴
4・3・2自動車分野の用途例
4・3・3材料開発動向
4・3・4今後の課題・展望
4・4おわりに
4 熱可塑性エラストマー JSR 竹村 泰彦
5 天然ゴム・合成ゴム ブリヂストン 上嶋 祥元
5・1はじめに 鍬本 賢二
5・2天然ゴム
5・2・1天然ゴムと防振ゴム
5・2・2防振ゴムの種類とその要求特性
(1)エンジンマウント
(2)サスペンションブッシュ
(3)トーショナルダンパー
(4)センターベアリングサポート
5・2・3防振ゴムにおけるNRの活用状況
(1)エンジンマウント用ゴムの耐熱性向上
(2)エンジンマウント用ゴムの高ロス低動倍化
(3)サスペンションブッシュ用ゴムの低動倍率化
(4)ビスカスラバーダンパー用ゴムのシリコンオイルとの相互作用
(5)センターベアリングサポート用ゴムの耐オゾン性向上
5・2・4今後の課題
5・3合成ゴム
5・3・1各種合成ゴムの性質
5・3・2自動車用ホースへの用途開発動向
(1)燃料系
(2)潤滑油系
(3)空気、水、ブレーキ系
(4)フレオン系
5・3・3まとめと今後の展望
6 ポリマーアロイ 工学院大学 伊澤 慎一
6・1はじめに
6・2樹脂材料の複合化による高性能化高機能化の流れ
6・3ポリマーアロイ化技術のこれまでと今後
6・4自動車用途向け高性能化・高機能付与とアロイ化技術
(1)耐薬品性
(2)強度特性
(3)耐熱性
(4)耐衝撃性
(5)難燃性
(6)制電性
6・5今後の展開
7 複合材料 いすゞ自動車 河西 純一
7・1炭素繊維強化プラスチックのトラック荷台への適用、およびガラス繊維強化プラスチック
7・2ガラス長繊維強化PPの強度部材への適用
7・3定着しつつあるアンダーフードのプラスチック化
7・3・1ナイロン系複合材料
7・3・2フェノール樹脂系複合材料
7・3・3ポリエステル樹脂系複合材料
7・4人工木材
第4章 部材別開発動向
1 外装・外板材料 いすゞ自動車 河西 純一
1・1永遠の課題(軽量化、低コスト化、プラスアルファ)解決に向けて
1・1・1外板パネルのプラスチック化
(1)熱可塑性プラスチック
(2)熱硬化性プラスチック
1・1・2サンドイッチ射出成形(エアダム、バンパ)
1・1・3フィルム・インサート射出成形(塗装・めっき代替フィルム)
1・1・4押出成形
1・1・5ブロー成形
1・2衝撃吸収材料
1・3おわりに
2 内装材料 三菱プラ 池田 詔郎
3 エンジン周り材料 富士重工業 福島 守
3・1吸気系部品
3・1・1射出成形部品-エアクリーナーケース
3・1・2ブロー成形-吸気ダクト
3・2インテークマニホールド
3・2・1射出成形
3・2・3 2Shell法(=2部品溶着法)
3・2・4ブロー射出成形
3・3オイル・ブローバイ系部品
3・3・1射出成形-オイルセパレターカバー-
3・3・2ブロー成形-ブローバイコネクター-
3・3・3ガス射出成形-オイルフィラーダクト-
3・4カム駆動系
3・4・1熱硬化性プラスチック-カムスプロケット-
3・4・2ゴム・プラスチックの一体成形-タイミングベルトカバー-
3・5まとめ
4 自動車用防音材料 日本自動車研究所 井上 茂
4・1はじめに
4・2 自動車用防音材料
4・2・1吸音材料
4・2・2遮音材料
4・2・3制振材料
(1)アスファルト系制振材料
(2)鋼板拘束型制振材料
(3)樹脂拘束型制振材料
(4)吹付型制振材料
(5)高減衰性接着剤
(6)制振鋼板
4・2・4防振材料
4・3防音材料の自動車への適用例
(1)フロア
(2)ダッシュ
(3)ホイールハウス
(4)ルーフ
4・4おわりに
5 構造用材料 日本発条 田部 隆幸
5・1はじめに
5・2材料の選択と成形方法
5・2・1強化材料
5・2・2マトリックス樹脂
5・2・3成形方法
5・3GFRPの基本特性
5・4GFRP板ばねの設計
5・4・1板ばねの設計
(1)ばね特性の計算式
(2)GFRP板ばねと金属ばねのメリット比較
(3)設計上の留意点
(4)取付部品の軽量化
(5)ワインドアップ振動と剛性試験
(6)横剛性試験
5・5自動車用サスペンション用ばねへの応用
5・6GFRP板ばねのリサイクルについて
5・6・1熱硬化性GFRP板ばねのリサイクル法
(1)粉砕法
?@カッタ粉砕法
?Aひき臼式粉砕法
?B熱分解法
5・7おわりに
6 タイヤ用材料 ブリヂストン 毛利 浩
6・1はじめに
6・2イヤトレッドに求められる要求特性
6・3低燃費タイヤトレッド用材料
6・3・1タイヤの転がり抵抗が燃費に及ぼす影響
6・3・2召?蠶餽海肇肇譽奪疋乾倏潅得?隆愀?
6・4新しい材料の開発
6・4・1溶液重合SBRの末端変性技術
6・4・2シリカ補強技術
6・4・3LLカーボンブラック
6・5タイヤ耐久性の向上
6・6今後の展望
第5章 次世代型自動車と機能性材料 本田技研 佐藤 登
1 はじめに
2 電気自動車用電池と機能性材料
2・1 高性能電池とセパレーター材料
2・1・1 自己放電対策と親水性付与
2・1・2 シャットダウン効果
2・2 高性能電池と電槽材料
3 高機能型エネルギー貯蔵システムとポリマー材料
4 燃料電池自動車と高分子材料
5 おわりに
第6章 自動車用塗料 日本油脂 柴藤 岸夫
1 自動車用塗料の現状と展望
1・1 自動車塗膜の構成
1・2 各種構成塗膜の現状と展望
1・2・1 下塗り(電着塗料)
1・2・2 中塗り
(1)水系中塗塗料
(2)粉体中塗塗料
1・2・3 ベースコート
(1)水系ベースコート
1・2・4 クリヤーコート
(1)水系クリヤー
(2)粉体クリヤー
1・2・5 プラスチック用塗料
2 自動車用補修塗料
2・1 自動車用補修塗料の現状
2・2 自動車用補修塗料の課題
3 塗装工程の省エネルギー
3・1 塗装工程のエネルギー試算
3・2 省エネルギーの展望
第7章 自動車用接着剤 サンスター技研 大栗 靖弘
1 はじめに
2 自動車用接着剤の概要
2・1 接着剤市場
2・2 自動車用接着剤の種類
3 自動車用接着剤の今後の動向
3・1 プレセット型ヘミング用接着剤
3・2 高剛性発泡充填剤(キャビティーフィラー)
3・3 機械発泡型不定形ガスケット
4 おわりに
第8章 自動車用高分子材料と成形加工 工学院大学 関口 勇
1 はじめに
2 自動車部品用プラスチック材料
2・1外装主要部品
1)バンパー
2)ガーニッシュ
3)サイドモール
4)ホイールカバー
5)ラジエータグリル
6)外板部品
2・2内装主要部品
1)インストルメントパネル
2)ドアトリム
3)コンソールボックス
4)ステアリングホイール
5)エアバックドア
2・3パワートレイン部品
1)インテークマニホールド
2)シリンダーヘッドカバー
3)エンジンマウント
4)シフトレバーハウジング
5)ターボチャージャーインペラ
2・4燃料系部品
1)燃料タンク
2)燃料キヤップ
2・5機能部品
2・6ランプ
3成形加工法
3・1射出成形法
3・1・1低圧成形
(1)射出圧縮成形
(2)射出プレス成形
(3)ガスアシスト射出成形
(4)型内圧低減成形
(5)低圧高速充填成形法
3・1・2射出中空部成形法
(1)ガスアシスト射出成形
(2)H2M成形
(3)2シェル成形
3・1・3ハイブリッド成形
3・1・4配向制御成形
3・1・5その他の成形法
(1)CFIプロセス成形
(2)サーモジェクト成形
(3)IMC成形
(4)超音波射出成形
(5)直接射出成形
3・2ブロー成形法
(1)三次元ブロー成形
(2)ダブル(二重壁)ブロー成形
(3)多層ブロー成形
4 注目される成形加工技術
(1)RTM法
(2)抄紙法スタンパブルシート成形
(3)外皮付き発泡成形
(4)CSEモール法
第9章 環境問題とリサイクル
1 日本の廃車リサイクル事情 草川 紀久
1・1はじめに
1・2廃車処理とリサイクルの現状
1・3「使用済み自動車リサイクル・イニシャティブ」と「自主行動計画」
1・4シュレッダーダストの処理の現状
1・5自動車用プラスチック部品のリサイクル
1・6バンパーリサイクルの現状と課題
1・7おわりに
2 アメリカでのリサイクル事情 草川 紀久
2・1はじめに
2・2米国の都市固形廃棄物の現状
2・3固形廃棄物の法的規制と政府の対応
2・4米国プラスチック産業の対応
2・5廃車リサイクリングの現状
2・6廃車リサイクリングの手法
2・7APCにおける廃車リサイクルの検討
2・8プラスチックの環境性向上のためのエンジニアリング・イニシアチブ
2・9おわりに
3 ヨーロッパでのリサイクル事情 日本自動車研究所 沼尻 到
3・1まえがき
3・2自動車のリサイクル手法
3・3ドイツの法制化の動き
3・4ドイツ自動車業界のリサイクルへの取り組み
3・4・1ELVの引き取り
3・4・2部品再利用
3・4・3BMW車へのリサイクル・プラスチックの使用
3・4・4BMWリサイクル性向上例
(1)フロントグリル
(2)床の断熱パーツ
(3)5シリーズのダッシュボード
(4)The-SMC-Sheet-Moulding-Compound
(5)BMW社リサイクル可能率評価基準
3・5おわりに
7 複合材料 いすゞ自動車 河西 純一
7・1炭素繊維強化プラスチックのトラック荷台への適用、およびガラス繊維強化プラスチック
7・2ガラス長繊維強化PPの強度部材への適用
7・3定着しつつあるアンダーフードのプラスチック化
7・3・1ナイロン系複合材料
7・3・2フェノール樹脂系複合材料
7・3・3ポリエステル樹脂系複合材料
7・4人工木材
第4章 部材別開発動向
1 外装・外板材料 いすゞ自動車 河西 純一
1・1永遠の課題(軽量化、低コスト化、プラスアルファ)解決に向けて
1・1・1外板パネルのプラスチック化
(1)熱可塑性プラスチック
(2)熱硬化性プラスチック
1・1・2サンドイッチ射出成形(エアダム、バンパ)
1・1・3フィルム・インサート射出成形(塗装・めっき代替フィルム)
1・1・4押出成形
1・1・5ブロー成形
1・2衝撃吸収材料
1・3おわりに
2 内装材料 三菱プラ 池田 詔郎
3 エンジン周り材料 富士重工業 福島 守
3・1吸気系部品
3・1・1射出成形部品-エアクリーナーケース
3・1・2ブロー成形-吸気ダクト
3・2インテークマニホールド
3・2・1射出成形
3・2・3 2Shell法(=2部品溶着法)
3・2・4ブロー射出成形
3・3オイル・ブローバイ系部品
3・3・1射出成形-オイルセパレターカバー-
3・3・2ブロー成形-ブローバイコネクター-
3・3・3ガス射出成形-オイルフィラーダクト-
3・4カム駆動系
3・4・1熱硬化性プラスチック-カムスプロケット-
3・4・2ゴム・プラスチックの一体成形-タイミングベルトカバー-
3・5まとめ
4 自動車用防音材料 日本自動車研究所 井上 茂
4・1はじめに
4・2 自動車用防音材料
4・2・1吸音材料
4・2・2遮音材料
4・2・3制振材料
(1)アスファルト系制振材料
(2)鋼板拘束型制振材料
(3)樹脂拘束型制振材料
(4)吹付型制振材料
(5)高減衰性接着剤
(6)制振鋼板
4・2・4防振材料
4・3防音材料の自動車への適用例
(1)フロア
(2)ダッシュ
(3)ホイールハウス
(4)ルーフ
4・4おわりに
5 構造用材料 日本発条 田部 隆幸
5・1はじめに
5・2材料の選択と成形方法
5・2・1強化材料
5・2・2マトリックス樹脂
5・2・3成形方法
5・3GFRPの基本特性
5・4GFRP板ばねの設計
5・4・1板ばねの設計
(1)ばね特性の計算式
(2)GFRP板ばねと金属ばねのメリット比較
(3)設計上の留意点
(4)取付部品の軽量化
(5)ワインドアップ振動と剛性試験
(6)横剛性試験
5・5自動車用サスペンション用ばねへの応用
5・6GFRP板ばねのリサイクルについて
5・6・1熱硬化性GFRP板ばねのリサイクル法
(1)粉砕法
?@カッタ粉砕法
?Aひき臼式粉砕法
?B熱分解法
5・7おわりに
6 タイヤ用材料 ブリヂストン 毛利 浩
6・1はじめに
6・2イヤトレッドに求められる要求特性
6・3低燃費タイヤトレッド用材料
6・3・1タイヤの転がり抵抗が燃費に及ぼす影響
6・3・2転がり抵抗とトレッドゴム粘弾性の関係
6・4新しい材料の開発
6・4・1溶液重合SBRの末端変性技術
6・4・2シリカ補強技術
6・4・3LLカーボンブラック
6・5タイヤ耐久性の向上
6・6今後の展望
第5章 次世代型自動車と機能性材料 本田技研 佐藤 登
1 はじめに
2 電気自動車用電池と機能性材料
2・1 高性能電池とセパレーター材料
2・1・1 自己放電対策と親水性付与
2・1・2 シャットダウン効果
2・2 高性能電池と電槽材料
3 高機能型エネルギー貯蔵システムとポリマー材料
4 燃料電池自動車と高分子材料
5 おわりに
第6章 自動車用塗料 日本油脂 柴藤 岸夫
1 自動車用塗料の現状と展望
1・1 自動車塗膜の構成
1・2 各種構成塗膜の現状と展望
1・2・1 下塗り(電着塗料)
1・2・2 中塗り
(1)水系中塗塗料
(2)粉体中塗塗料
1・2・3 ベースコート
(1)水系ベースコート
1・2・4 クリヤーコート
(1)水系クリヤー
(2)粉体クリヤー
1・2・5 プラスチック用塗料
2 自動車用補修塗料
2・1 自動車用補修塗料の現状
2・2 自動車用補修塗料の課題
3 塗装工程の省エネルギー
3・1 塗装工程のエネルギー試算
3・2 省エネルギーの展望
第7章 自動車用接着剤 サンスター技研 大栗 靖弘
1 はじめに
2 自動車用接着剤の概要
2・1 接着剤市場
2・2 自動車用接着剤の種類
3 自動車用接着剤の今後の動向
3・1 プレセット型ヘミング用接着剤
3・2 高剛性発泡充填剤(キャビティーフィラー)
3・3 機械発泡型不定形ガスケット
4 おわりに
第8章 自動車用高分子材料と成形加工 工学院大学 関口 勇
1 はじめに
2 自動車部品用プラスチック材料
2・1外装主要部品
1)バンパー
2)ガーニッシュ
3)サイドモール
4)ホイールカバー
5)ラジエータグリル
6)外板部品
2・2内装主要部品
1)インストルメントパネル
2)ドアトリム
3)コンソールボックス
4)ステアリングホイール
5)エアバックドア
2・3パワートレイン部品
1)インテークマニホールド
2)シリンダーヘッドカバー
3)エンジンマウント
4)シフトレバーハウジング
5)ターボチャージャーインペラ
2・4燃料系部品
1)燃料タンク
2)燃料キヤップ
2・5機能部品
2・6ランプ
3 成形加工法
3・1射出成形法
3・1・1低圧成形
(1)射出圧縮成形
(2)射出プレス成形
(3)ガスアシスト射出成形
(4)型内圧低減成形
(5)低圧高速充填成形法
3・1・2射出中空部成形法
(1)ガスアシスト射出成形
(2)H2M成形
(3)2シェル成形
3・1・3ハイブリッド成形
3・1・4配向制御成形
3・1・5その他の成形法
(1)CFIプロセス成形
(2)サーモジェクト成形
(3)IMC成形
(4)超音波射出成形
(5)直接射出成形
3・2ブロー成形法
(1)三次元ブロー成形
(2)ダブル(二重壁)ブロー成形
(3)多層ブロー成形
4 注目される成形加工技術
(1)RTM法
(2)抄紙法スタンパブルシート成形
(3)外皮付き発泡成形
(4)CSEモール法
第9章 環境問題とリサイクル
1 日本の廃車リサイクル事情 草川 紀久
1・1はじめに
1・2廃車処理とリサイクルの現状
1・3「使用済み自動車リサイクル・イニシャティブ」と「自主行動計画」
1・4シュレッダーダストの処理の現状
1・5自動車用プラスチック部品のリサイクル
1・6バンパーリサイクルの現状と課題
1・7おわりに
2 アメリカでのリサイクル事情 草川 紀久
2・1はじめに
2・2米国の都市固形廃棄物の現状
2・3固形廃棄物の法的規制と政府の対応
2・4米国プラスチック産業の対応
2・5廃車リサイクリングの現状
2・6廃車リサイクリングの手法
2・7APCにおける廃車リサイクルの検討
2・8プラスチックの環境性向上のためのエンジニアリング・イニシアチブ
2・9おわりに
3 ヨーロッパでのリサイクル事情 日本自動車研究所 沼尻 到
3・1まえがき
3・2自動車のリサイクル手法
3・3ドイツの法制化の動き
3・4ドイツ自動車業界のリサイクルへの取り組み
3・4・1ELVの引き取り
3・4・2部品再利用
3・4・3BMW車へのリサイクル・プラスチックの使用
3・4・4BMWリサイクル性向上例
(1)フロントグリル
(2)床の断熱パーツ
(3)5シリーズのダッシュボード
(4)The-SMC-Sheet-Moulding-Compound
(5)BMW社リサイクル可能率評価基準
3・5おわりに
-
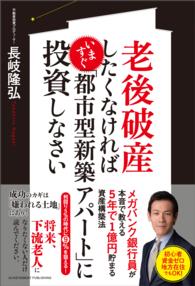
- 電子書籍
- 老後破産したくなければいますぐ「都市型…