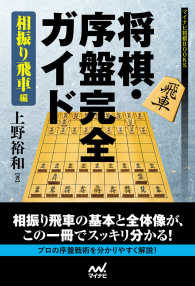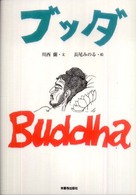出版社内容情報
執筆者一覧(執筆順)
所属は1989年5月時点。( )内は2000年10月現在
烏羽山 満 職業訓練大学校(現・職業能力開発総合大学校 造形工学科)
井出 正 富士重工(株) 材料研究部(現在 同社退職)
岡 襄二 新日本製鐵(株) 表面処理研究センター
松井 逸史 新日本ペイント(株) 自動車塗装部(現・日本テストパネル㈱)
木下 啓吾 長島特殊塗料(株) 技術本部(現・長島特殊塗料(株) 技術本部 技術最高顧問)
吉井 孝志 日本ペイント(株) 第一塗料事業部(現・日本ペイント(株) サーフ事業部)
柳原 徹雄 日本ペイント(株) 第一塗料事業部
柿沼 和夫 日本油脂(株) 戸塚工場 技術部(現・日本油脂BASFコーティングス(株) 財務・管理本部)
名倉 修 日本油脂(株) 戸塚工場 技術部(現・日本油脂BASFコーティングス(株) 研究開発本部)
安田 一美 大橋化学工業(株) 研究開発部
田中 信博 カシュー(株) 技術部(現・カシュー(株) 塗料第一事業部)
柳瀬 徹夫 (財)日本色彩研究所(現・(株)イード RAグループ)
中畑 顯雅 関西ペイント(株) 自動車塗料研究部
稲村 恵三 桐生技術士事務所
有本 邦夫 石原薬品(株) 研究部
笠松 寛 桐生工業(株)(現・ジーテック)
荻野 芳夫 友和塗料(株)(現・近代化成(有)
佐藤 昭 パーカー・アレスター(株)
田中 丈之 日本油脂(株) 塗料研究所(現・(有)かきとう 湘南事務所)
田辺 幸男 本田技研工業(株) 埼玉製作所
構成および内容
第1章 総論 烏羽山 満
1 自動車塗装における技術開発
1.1 環境保全
1.2 省エネルギー
1.3 消費者動向
2 車体構築用素材
3 自動車塗装システム
3.1 素地調整
3.1.1 無機変性塗装(化成処理)
3.1.2 塗装法
3.1.3 鉄および亜鉛フォスフェート塗料の長所
4 下塗り(プライマー)
4.1 溶剤系
4.2 電着プライマー
4.2.1 アニオンEPD
4.2.2 カチオンEPD
4.3 補助プライマー
5 サーフェーサ・フィラー
5.1 溶剤ベースサーフェーサ・フィラー
5.2 水系ディッププライマー・スプレーサーフェーサ
5.3 揮発性有機物低含有サーフェーサ・フィラー
5.4 新規開発
5.4.1 粉体プライマー
5.4.2 電気泳動粉体塗料
6 自動車上塗り
6.1 熱硬化性上塗り
6.1.1 アルキド型
6.1.2 汎用アクリル型
6.1.3 非水アクリル分散(NAD)
6.1.4 ベース・クリアシステム
6.1.5 水系熱硬化性上塗り
6.1.6 ハイソリッド上塗り
6.2 汎用熱可塑性アクリル上塗り
6.2.1 基本配合原理
6.2.2 プロセシングパラメータ
6.3 非水熱可塑分散(NAD)ラッカー
6.4 粉体塗料
6.5 プラスチック部材用塗料
第2章 自動車に対するニーズ 井出正
1 自動車に対する市場の要求
2 自動車と塗装
3 自動車の塗装品質
4 自動車用塗料の変遷
5 材料構成
6 FRP外板と鋼板の塗装外観品質
7 外装部品および機能部品の塗装
8 自動車塗装の課題と将来
8.1 塗装外観品質の向上
8.2 樹脂部品の塗装
8.4 省資源
8.5 公害対策
8.6 省エネルギー化,省力化
第3章 各素材の動向と前処理技術 岡襄二
1 鉄鋼 岡襄二
1.1 はじめに
1.2 構造用材料
1.3 車体用材料
1.3.1 軽量化を目的とした鉄鋼材料
1.3.2 制振鋼板
1.3.3 高鮮映性鋼板
1.3.4 防錆処理鋼板
1.4 燃料タンク用鉄鋼材料
1.5 排気系用鉄鋼材料
2 アルミニウム 松井逸史
2.1 はじめに
2.2 アルミ化の現状
2.2.1 エンジン部品
2.2.2 ホイール
2.2.3 ラジエータ
2.2.4 カーエアコン
2.2.5 トリム,ガーニッシュ
2.2.6 ボディパネル
2.3 今後の動向
2.4 前処理の動向
2.4.1 ホイール
2.4.2 ボディパネル
2.4.3 エバポレータ(カーエアコン)
2.5 おわりに
3 プラスチック 木下啓吾
3.1 はじめに
3.2 プラスチック素材の特異性
3.3 プラスチック素材への塗膜の付着について
3.4 プラスチック素材の表面処理
3.5 プラスチック用塗料について
3.6 おわりに
第4章 コーティング材料開発の動向
1 防錆対策用コーティング材料
1.1 表面処理 吉井孝志
1.1.1 表面処理の役割と歴史
1.1.2 表面処理のメカニズム
1.1.3 フルディップシステム(浸漬法)
1.1.4 カチオン電着用前処理
1.1.5 亜鉛メッキ鋼板用前処理
1.2 カチオン電着 柳原徹雄
1.2.1 電着塗装法の概要
1.2.2 電着塗装発展の歴史
1.2.3 カチオン電着塗装の普及の背景と現状
1.2.4 電着の造膜機構
1.2.5 カチオン電着塗装の特徴
1.2.6 カチオン電着塗料の開発動向とその評価
1.3 ボデー構造部材の防錆 国則武司
1.3.1 はじめに
1.3.2 腐食環境
1.3.3 防錆対策としての塗装
1.3.4 自動車ボデー鋼板の改質
1.4 部品の防錆 国則武司
1.4.1 はじめに
1.4.2 亜鉛メッキ部品用塗料
1.4.3 G材用プライマー
1.4.4 部品用塗料の新しい展開
1.4.5 おわりに
2 樹脂用コーティング材料 柿沼和夫
2.1 はじめに
2.2 コーティング材料
2.2.1 ユニバーサルプライマー
2.2.2 1液低温硬化形上塗塗料
2.2.3 白色導電プライマー
2.2.4 ユニベース,ユニコート
2.3 塗装方法
2.3.1 インモールコート法
2.3.2 モールドコート法
2.4 硬化方法
2.4.1 アミン気相触媒硬化法
2.4.2 紫外線硬化法
2.5 おわりに
3 高鮮映性コーティング材料 名倉修
3.1 はじめに
3.2 鮮映性の評価とその意味
3.3 鮮映性の阻害要因と対策
3.3.1 短波長成分に影響する塗料の性質
3.3.2 中波長成分に影響する塗料の性質
3.3.3 長波長成分に影響する塗料の性質
3.4 タレとレベリングを両立する技術
3.5 おわりに
4 新イメージ用コーティング材料
4.1 スエード調塗料 安田一美
4.1.1 はじめに
4.1.2 技術開発動向
4.1.3 スエード調塗料の特徴
4.1.4 塗料の種類と特性
4.1.5 ポリマービーズ
4.1.6 適応例
4.1.7 おわりに
4.2 皮革調塗料 田中信博
4.2.1 はじめに
4.2.2 皮革調塗料とは
4.2.3 材料
4.2.4 塗膜の特徴
4.2.5 皮革調塗料の今後
5 カラーデータとデザイン 柳瀬徹夫
5.1 調査とデザイン
5.2 製品の色彩の変遷
5.2.1 固有色の時代
5.2.2 カラー化・多色化の時代
5.2.3 カラーコーディネートの時代
5.3 カラーデザインのためのデータ
5.3.1 色彩の視覚効果の利用
5.3.2 カラーイメージの利用
5.4 カラーデザインのためのデータの把握と予測
6 メンテナンスフリー型コーディング材料 中畑顯雅
6.1 メンテナンスフリー塗料のニーズ
6.2 自動車外板塗装におけるメンテナンスフリー性能
6.2.1 超耐候性
6.2.2 ワックスフリー性
6.2.3 耐酸性(化学的安全性)
6.2.4 耐洗車性(擦傷性)
6.3 メンテナンスフリーコーティンング材料
6.3.1 フッ素樹脂系コーティング材料
6.3.2 高撥水コーティング材料
6.4 今後の動向
7 マーキングフィルム 稲村恵三
7.1 はじめに
7.2 マーキングフィルムの主な用途
7.3 マーキングフィルムの種類と構造
7.4 マーキングフィルムの品質
7.4.1 マーキングフィルムの一般的品質
7.4.2 マーキングフィルムの耐候性
7.5 マーキングフィルムの特徴
7.6.1 温度と接着力
7.6.2 貼付後の保持時間と接着力
7.6.3 各種素材に対する接着力
7.6.4 フィルムの寸法安全性
7.7 おわりに
8 補修用コーティング材料 桐生春雄
8.1 はじめに
8.2 発展とその過程
8.3 分類と一般性能
8.4 補修性と性能の関連
8.5 各種補修塗装系と分類および機能
8.5.1 下塗コーティング系
8.5.2 上塗塗料系(トップコート)
8.5.3 ビヒクル(展色剤)による補修用コーティング材料の分類
8.6 補修塗装法
8.6.1 補修塗装の目的
8.6.2 補修部位と補修方法
8.6.3 標準補修塗装法
8.7 補修塗装のレイアウト
8.8 おわりに
9 ワックスおよびコーティング資材 有本邦夫
9.1 はじめに
9.2 カーワックスの役割
9.3 カーワックスの具備すべき条件
9.4 ワックスの種類と特性
9.4.1 固形ワックス
9.4.2 ねりワックス
9.4.3 液状ワックス
9.4.4 スプレーワックス
9.4.5 特殊ワックス
9.5 カーワックスの原料
9.5.1 ワックス
9.5.2 シリコーン
9.5.3 溶剤
9.5.4 研磨材(コンパウンド)
9.5.5 界面活性剤
9.5.6 安定剤
9.5.7 色素
9.5.8 香料
9.5.9 水
9.6 カーワックスの開発動向
9.6.1 文献に見るカーワックスの開発動向
9.6.2 極性基を有するシリコーンの応用
9.6.3 ポリマーの添加(高分子化)
9.6.4 カーワックス用素材の変性
9.6.5 無溶剤化
9.6.6 作業性の向上
9.6.7 プラスチック用ワックス
9.6.8 その他
9.7 カーワックスの問題点と今後の動向
第5章 コーティングエンジニアリング
1 塗装装置 笠松寛
1.1 自動車の塗装
1.2 塗装計画
1.3 塗装装置と塗装機器
1.3.1 主な装置と機器
1.3.2 設備配置
1.4 前処理装置
1.4.1 前処理について
1.4.2 装置例
1.4.3 自動管理について
1.5 塗布機器
1.5.1 吹付け式塗装器
1.5.2 多液塗装機
1.5.3 押出式(マテリアルポンプ&ノズル)
1.5.4 その他の塗布機器,装置
1.5.5 静電塗装器
1.6 自動塗装機
1.6.1 レシプロ型自動塗装機
1.6.2 ベル型自動塗装機
1.6.3 塗装ロボット
1.7 電着塗装装置
1.7.1 電着塗装の設備構成
1.7.2 電極と隔膜
1.7.3 塗料と塗装条件の管理項目
1.8 塗装ブースと空調設備
1.8.1 ブースの形式
1.8.2 ブースの役割
1.9 塗料循環装置
1.9.1 塗料循環装置の役割
1.9.2 装置の種類
1.9.3 管理
1.10 空気圧縮装置
1.10.1 エアコンプレッサーと配管
1.11 搬送装置
1.12 排気,排水処理装置
1.12.1 排気ガス燃料装置
1.12.2 排水処理装置
1.13 乾燥装置(焼付け炉)
2 乾燥装置 荻野芳夫
2.1 はじめに
2.2 自動車用乾燥装置の型式
2.2.1 自動車用塗装乾燥炉の熱伝達型式
2.2.2 塗装乾燥炉熱風方式の種類
2.2.3 自動車塗装乾燥炉の形状
2.3 乗用車用塗装乾燥炉の用途別分類
2.4 乗用車塗装乾燥炉の乾燥温度と時間
2.5 熱風炉の灼熱度について
2.6 塗装乾燥炉のヤニについて
2.7 塗装乾燥熱風炉のハイテク,層流熱風炉について
2.8 塗装乾燥炉の排ガス脱臭装置
2.8.1 再燃焼方式
2.8.2 白金触媒法
2.8.3 湿式化学反応脱臭システム
2.9 おわりに
3 ワークピースの形状検出法 佐藤昭
3.1 概要
3.2 形状検出機器
3.2.1 光電スイッチ
3.2.2 イメージセンサー
3.2.3 CCDカメラ
3.4 自動形状検出装置
3.4.1 光電スイッチの固定式並列配置
3.4.2 光電スイッチの揺動式並列配置
3.4.3 イメージカメラ方式
第6章 周辺技術
1 コーティング材料管理
1.1 塗料管理とは
1.2 塗料管理とポイント
1.2.1 塗料発注時の注意
1.2.2 塗料と製造と出荷
1.2.3 納入塗料の受入れ検査
1.3 塗料管理における試験方法
1.4 おわりに
2 コーティングフィルム管理 田中丈之
2.1 はじめに
2.2 塗膜の管理項目
2.3 塗膜厚の管理
2.4 塗膜の光沢管理
2.5 塗膜の色彩管理
2.6 一般物性の管理
2.6.1 塗膜面の硬度
2.6.2 塗膜の付着性
2.6.3 耐衝撃性
2.6.4 エリクセン
2.6.5 耐汚染性
3 塗装管理における周辺技術 田辺幸男
3.1 はじめに
3.2 自動車塗装工場の生産管理
3.2.1 色変更の頻度とその削減
3.2.2 直行率
3.2.3 ラインペアーシステム
3.3 塗装工程の歩留り管理
3.3.1 無欠点ボディ造りをめざす工程
3.3.2 表面処理鋼板の採用と外観欠点
3.3.3 搬送システムの環境対策
3.3.4 電着槽設計とメンテナンス
3.3.5 メタルフィニッシング
3.3.6 自己ダスト
3.3.7 最大膜厚限界
3.4 市場補修塗装の今日的テーマ
3.5 無人化稼動と休止時対応
3.6 高品質外観塗装への挑戦
3.7 塗着効率と溶剤排出規制
3.8 塗装排水の未来規制対象物質
3.9 おわりに
4 塗膜劣化における周辺技術 田中丈之
4.1 はじめに
4.2 劣化要因
4.2.1 保護機能と劣化要因
4.2.2 外的劣化要因
4.2.3 内的要因
4.3 耐久性評価法
4.4 塗膜の耐久性
4.5 おわりに
内容説明
本書は、急速に発達する自動車塗料技術について、新しい塗装素材の開発動向を中心に、前処理、塗装、乾燥等各レベルでの最新技術動向、及び補修用塗料の動向についてまとめたものである。
目次
第1章 総論
第2章 自動車に対するニーズ
第3章 各素材の動向と前処理技術
第4章 コーティング材料開発の動向
第5章 コーティングエンジニアリング
第6章 周辺技術