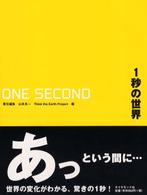出版社内容情報
執筆者一覧
(所属は1989年1月時点。カッコ内は2000年6月現在)
福沢敬司 福沢技術士事務所
西田幸平 STR (現・恵比寿化成(株) 技術開発室)
宮崎正常 積水化学工業(株) 工業資材部門 (現・(財)科学技術戦略推進機構 戦略推進部)
一角泰彦 (株)一カク工業 開発研究部(現・代表取締役 社長)
柴野富四 創研化工(株) 技術部
三谷恵敏 (株)ヒラノテクシード 商品開発室
上北廣一 (株)ヒラノテクシード 商品開発室
森本雄一 日東電工(株) 粘着剤研究所 (現・テープマテリアル事業部門 粘着テープ開発センター 主任研究員)
半田浩一 日産自動車(株) 中央研究所
芦田 正 日産自動車(株) 中央研究所
奈良正人 大正製薬(株) 総合研究所(現・生産事業計画部)
片山 明 FSK(株) 研究本部
大町芳章 菅原工業(株)(現・スリオンテック)開発部
山下弘二 (株)ニトムズ 販売促進グループ
加藤三省 住友スリーエム(株) デコラティブ・グラフィックス事業部
三上喜勝 日立化成工業(株) 五所宮工場
檜森宏次 日立化成工業(株) 五所宮工場
岡本高男 菊水テープ(株) 研究室
上坊武夫 住友スリーエム(株) 技術本部
構成および内容
第1章 総 論 福沢敬司
1 はじめに
2 各国の粘着事情
2.1 日本
2.2 韓国
2.3 台湾
2.4 中国
2.5 東南アジア
2.6 ヨーロッパ
2.7 米国
3 粘着技術の動向
3.1 粘着剤
3.1.1 溶剤型
3.1.2 水系
3.1.3 カレンダー用
3.1.4 ホットメルト型
3.1.5 液状硬化型
3.1.6 その他の粘着剤
3.2 粘着製品
4 粘着理論の動向
4.1 レオロジカルな挙動
4.2 界面接着仕事
4.3 形態学的研究
4.4 評価方法
5 おわりに
第2章 材料開発の動向
1 粘着製品の材料 西田幸平
1.1 粘着製品の構成
1.1.1 はじめに
1.2 粘着製品の種類
1.3 粘着製品の特性その他
1.3.1 タック
1.3.2 粘着および粘着力
1.3.3 保持力
1.4 粘着製品の構成
1.5 支持体
1.5.1 はじめに
1.5.2 必要とされる性能
1.5.3 種類
1.5.4 粘着物性への影響
1.6 下塗剤
1.6.1 目的
1.6.2 要求される性能
1.6.3 種類
1.7 剥離剤
1.7.1 要求される特性
1.7.2 種類
1.7.3 注意事項
1.8 今後の動向
1.9 おわりに
2 粘着剤 宮崎正常
2.1 ゴム系粘着剤
2.1.1 性能の向上
2.1.2 ラテックス系粘着剤
2.1.3 ブチルゴム系粘着剤
2.1.4 スチレン系ブロック共重合体系における進歩
2.1.5 再剥離型製品へのブロック共重合体の応用
2.1.6 オリゴマーの利用
2.2 アクリル系粘着剤
2.2.1 物性バランスのとり方
2.2.2 経時による粘着力上昇の少ない粘着剤
2.2.3 被着体選択性に関するもの
2.2.4 ブレンドによる機能付加
2.2.5 EB、UVの利用
2.2.6 後硬化反応型粘着剤
2.2.7 固形または無溶剤粘着剤
2.2.8 新しい水系粘着剤
2.2.9 医療用に用いられるアクリル系粘着剤
2.3 含ケイ素系粘着剤
2.3.1 各種の剥離性に関する改質
2.3.2 無溶剤型含ケイ素粘着剤
2.3.3 シリコーン粘着剤の応用
3 下塗剤 一角泰彦
3.1 下塗剤の化学
3.2 ブレンド系下塗剤
3.3 グラフトポリマー系下塗剤
3.4 特許にみられる粘着テープ類の下塗剤
4 剥離剤 柴野富四
4.1 はじめに
4.2 代表的な剥離剤
4.2.1 シリコーン
4.2.2 長鎖アルキル基含有ポリマー
4.3 新しい剥離剤
4.3.1 シリコーン粘着剤用剥離剤
4.3.2 印刷可能な剥離剤
4.3.3 剥離性の改良された長鎖アルキル系剥離剤
4.3.4 中剥離レベルの剥離剤
4.4 おわりに
第3章 塗布技術の最近の進歩 三谷恵敏、上北廣一
1 はじめに
2 水系エマルジョンの特徴およびその塗工装置
2.1 エマルジョン型粘着剤の塗工システムに関する物性
2.2 粘着剤塗工装置
2.2.1 リップコーター
2.2.2 リップコーターによる塗工特性プロファイル
3 最近の製品製造システムとその概説
3.1 最近の製品製造システム
3.1.1 多目的塗工装置概要
3.1.2 原反巻出ユニット
3.1.3 塗工部の制御関係
3.2 乾燥装置
3.2.1 乾燥熱量
3.2.2 ロールサポート式乾燥機
3.2.3 フローティング式乾燥機
3.2.4 クリーンドライヤー
3.2.5 N2ガス置換型乾燥システム
3.3 FLUIDEX
4 おわりに
第4章 粘着製品の応用
1 電気・電子関連用粘着製品 森本雄一
1.1 はじめに
1.2 粘着製品の構成
1.3 電気絶縁用テープ
1.4 電子部品テーピング粘着テープ
1.5 プリント配線板用粘着テープ
1.6 スプライシングテープ
1.7 半導体用粘着テープ
1.8 両面テープ類
1.9 機能部材粘着加工品
1.10 おわりに
2 自動車用粘着製品 半田浩一、芦田 正
2.1 はじめに
2.2 自動車用粘着製品の種類
2.2.1 両面テープ
2.2.2 ブチル系粘着剤
2.2.3 水性接着剤
2.2.4 その他の粘着剤
2.3 粘着剤の評価方法
2.4 今後の動向
2.4.1 構造部材への適用
2.4.2 自動化への対応
2.4.3 材料開発
3 医療関連用粘着製品 奈良正人
3.1 はじめに
3.2 医療用粘着製品の分類
3.3 粘着製剤の構成
3.3.1 剥離紙
3.3.2 粘着剤
3.3.3 下引き剤(アンカーコート剤)
3.3.4 支持体
3.4 各種医療用粘着製品
3.4.1 消炎鎮痛プラスター剤
3.4.2 消炎鎮痛パップ剤
3.4.3 感冒用パップ剤
3.4.4 皮膚疾患用テープ剤
3.4.5 口腔内貼付剤
3.4.6 角質軟化剤
3.4.7 鎮痒パッチ剤
3.4.8 救急絆創膏
3.4.9 外科用粘着テープ(サージカルテープ)
3.4.10 パッチテスト用テープ
3.4.11スポーツテープ
3.5 経皮治療システム(T.T.S)
3.5.1 製剤設計
3.5.2 各種T.T.S製剤の実例
3.6 今後の展望
4 グラフィックアーツ用粘着製品 片山 明
4.1 はじめに
4.2 グラフィックアーツ用粘着製品の性能別分類
4.3 グラフィックアーツ用粘着製品の構成要素
4.3.1 表面基材
4.3.2 粘着剤
4.3.3 剥離紙
4.4 グラフィックアーツ用粘着製品の製造
4.4.1 剥離紙、粘着紙の製造
4.4.2 印刷・ラベル加工
4.5 グラフィックアーツ製品の最近の応用例
4.5.1 情報機器関連ラベル
4.5.2 いたずら防止ラベル
4.5.3 機密を保持できるはがきラベル
4.5.4 メンブレムスイッチ用粘着シート
4.5.5 開閉自由なウェットティッシュ
4.6 粘着ラベルの食品衛生とUL規格
4.6.1 食品衛生
4.6.2 UL規格
4.7 おわりに
5 建築・土木関連粘着製品 大町芳章
5.1 はじめに
5.2 養生用粘着テープ
5.3 床材固定用粘着テープ
5.4 防水テープ
5.4.1 防水シートの接続用テープ
5.4.2 住宅建築用シールテープ
5.4.3 浴室壁の下地防水シート
5.4.4 折板屋根のジョイント部のシール用テープ
5.4.5 その他
5.5 ダクト用粘着テープ
5.5.1 布粘着テープ
5.5.2 アルミクラフト粘着テープ
5.5.3 アルミ粘着テープ
5.6 建具用粘着テープ
5.7 目地処理テープ
5.8 梱包、結束用粘着テープ
5.9 表面保護用粘着テープ
5.10 おわりに
6 家庭用品における粘着製品-新市場の創造 山下弘二
6.1 家庭用粘着製品の市場導入
6.2 家庭・雑貨用粘着製品の商品構成
6.2.1 ケース1:台所用テープ
6.2.2 ケース2:台所用シート
6.2.3 ケース3:すきまテープ
6.2.4 ケース4:補修用テープ
6.2.5 ケース5:手芸用テープ
6.3 素材としての粘着製品の今後の展開
6.4 家庭用粘着応用製品の可能性
7 マーキングフィルム 加藤三省
7.1 はじめに
7.2 マーキングフィルムとは
7.3 マーキングフィルムの用途
7.4 最近の市場の広がり
7.5 マーキングフィルムの種類
7.6 マーキングフィルム用副資材
7.7 スリーエムマッチドコンポーネントシステム
7.8 おわりに
8 表面保護用粘着フィルムの最新応用技術 三上喜勝、桧森宏次
8.1 はじめに
8.2 表面保護用粘着フィルムの特性と用途
8.2.1 製品構成
8.2.2 貼り付け方法
8.2.3 用途
8.2.4 表面保護用粘着フィルムの一般特性
8.3 ステンレス鋼板深絞り加工用表面保護粘着フィルム"ヒタレックス"D-5700シリーズ
8.3.1 粘着剤
8.3.2 基材フィルム
8.3.3 "ヒタレックス"D-5700シリーズの諸特性
8.4 金属板曲げ加工用表面保護粘着フィルム"ヒタレックス"F-600シリーズ
8.4.1 基材フィルム
8.4.2 粘着剤
8.4.3 "ヒタレックス"F-600シリーズの諸特性
8.4.4 耐引っかき傷性
8.5 おわりに
9 路面標示用粘着製品 岡本高男
9.1 はじめに
9.2 路面標示材とは
9.3 種類
9.3.1 常温貼付式(粘着テープ)
9.3.2 加熱接着式
9.4 製造方法
9.5 貼付式路面標示材(粘着製品)の品質
9.5.1 比重
9.5.2 軟化点
9.5.3 塗膜の外観
9.5.4 45度、0度拡散反射率(白色のみ)
9.5.5 黄色度(白色のみ)
9.5.6 耐摩耗性
9.5.7 耐アルカリ性
9.5.8 加熱残分
9.5.9 ガラスビーズ含有量
9.5.10 促進耐候性試験
9.5.11 引張り強さ・伸び
9.5.12 粘着力
9.5.13 すべり抵抗値
9.5.14 再帰反射率
9.6 貼付式路面標示材(粘着製品)の特性
9.7 貼付式路面標示材の施工方法
9.7.1 路面の選定
9.7.2 安全の確保
9.7.3 路面の清掃
9.7.4 作図
9.7.5 プライマーの塗布・乾燥
9.7.6 テープの貼付け
9.7.7 圧着(接着)
9.8 おわりに
10 粘着剤の特殊用途 上坊武夫
10.1 はじめに
10.2 特殊粘着剤
10.2.1 剥離容易な粘着剤
10.2.2 高強度粘着剤
10.3 特殊支持体をもつ粘着剤
10.4 粘着テープの新用途
10.4.1 葉野菜結束テープ
10.4.2 数字印刷テープ
10.5 粘着性をもつ接着剤
10.6 おわりに
内容説明
本書は、電気・電子関連、医療関連、自動車関連などの応用開発の動向を中心として材料開発、塗布技術の進歩についてまとめ記述。
目次
第1章 総論(各国の粘着事情;粘着技術の動向;粘着理論の動向)
第2章 材料開発の動向(粘着製品の材料;粘着剤;下塗剤 ほか)
第3章 塗布技術の最近の進歩(水系エマルジョンの特徴およびその塗工装置;最近の製品製造システムとその概説)
第4章 粘着製品の応用(電気・電子関連用粘着製品;自動車用粘着製品;医療関連用粘着製品 ほか)
著者等紹介
一角泰彦[イッカクヤスヒコ]
(株)一カク工業 開発研究部(現・代表取締役 社長)
宮崎正常[ミヤザキマサツネ]
積水化学工業(株)工業資材部門(現・(財)化学技術戦略推進機構 戦略推進部)
三谷恵敏[ミタニヒロトシ]
(株)ヒラノテクシード商品開発室
柴野富四[シバノトミヨ]
創研化工(株)技術部
西田幸平[ニシダコウヘイ]
STR(現・恵比寿化成(株)技術開発室)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。