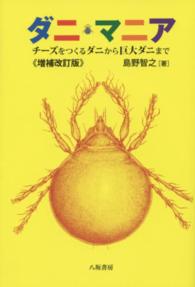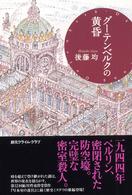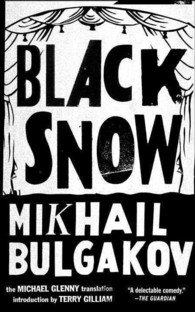出版社内容情報
構成および内容
第1章 序論
1 はじめに
2 DNAプローブの優秀性――その理論的背景――
3 DNAプローブ技術の現状
第2章 総論
1 核酸ハイブリダイゼーションの原理
1.1 原理
1.2 実際上の問題
2 プローブの作成
3 核酸ハイブリダイゼーション法による検査の利点と欠点
3.1 利点
3.2 欠点
4 おわりに
第3章 DNAプローブによる感染症の診断
1 臨床微生物
1.1 健康人体にみられる各種微生物(常在微生物叢)
1.2 各種感染症の細菌学的診断
2 感染症の診断の主力となるアッセイ方法
2.1 ドットハイブリダイゼーション法(スポットハイブリダイゼーション法)
2.2 コロニーハイブリダイゼーション法
2.3 In situハイブリダイゼーション法
2.4 核酸サンドウィッチハイブリゼーション法
2.5 展望
2.6 時間解析蛍光測定法
3 細菌感染症の診断
3.1 ブドウ容菌
3.2 連鎖球菌
3.3 マイコバクテリウム
3.4 淋菌(Neisseria gonorrhoeae)
3.5 サルモネラ菌
3.6 シュードモナス
3.7 キャンピロバクター
3.8 レジオネラ菌
3.9 病原性大腸菌(Pathogenic Escherichia coli)
3.10 コレラ菌とエロモナス菌
3.11 クラミジヤ(Chlamydia)
3.12 マイコプラズマ
3.13 梅毒トレポネーマ
4 ウイルス感染症の診断
4.1 ウイルス(総論)
4.2 最近のウイルス分離・同定法
4.3 肝炎ウイルス
4.4 EBウイルス(Epstein-Barrウイルス;EBV)
4.5 サイトメガロウイルス(Cytomegalovirus;CMV)
4.6 単純疱疹ウイルス(Herpes simplex virus;HSV)
4.7 後天性免疫不全症候群(Aquired immune deficiency syndrome;AIDS)
4.8 スローウイルス感染症
4.9 パルボウイルス(Parvovirus)
4.10 パピローマウイルス
4.11 ウイロイド
5 寄生虫感染症の診断
5.1 寄生虫感染におけるDNAプローブの利用
5.2 リーシュマニア症
5.3 マラリア
5.4 他の寄生虫感染症に対するDNAプローブの利用
5.5 DNAプローブの応用性
6 抗生物質耐性遺伝子の検出
6.1 新しい耐性遺伝子の識別
6.2 院内感染の研究
6.3 無差別伝播因子に関する研究
6.4 感受性の研究
6.5 おわりに
7 親和性に基づいた核酸ハイブリッド回収法(affinity-based nucleic acid collection
第4章 DNAプローブによるヒトの遺伝子診断
1 はじめに――遺伝病とは――
2 遺伝病の定義と特徴
2.1 染色体異常による遺伝病
2.2 単一遺伝子の突然変異による遺伝病
2.3 X連鎖疾患
2.4 多因性遺伝疾患
3 最近の遺伝病診断方法
3.1 臨床症状の観察
3.2 生化学的なマーカーの測定
3.3 染色体分析
4 遺伝病に対する出生前の診断
4.1 出生前診断の必要性
4.2 最近の診断法
5 DNAプローブの遺伝病診断への応用性
5.1 直接検定法
5.2 合成DNAプローブ法
5.3 RFLPプローブ法
5.4 おわりに
6 出生前診断におけるDNAプローブ法の利点と欠点
6.1 DNAプローブ法の利点
6.2 DNAプローブ法の欠点
7 遺伝病の治療
第5章 DNAプローブによるガン診断の可能性
1 ガン遺伝子
1.1 活性化の定義と様式
1.2 レトロウイルスのガン遺伝子
1.3 DNAウイルスのガン遺伝子
1.4 プロトオンコ遺伝子
2 ガンの診断技術
2.1 観血的技術
2.2 直接診断機器(非観血的技術)
3 DNAプローブによるガン診断の可能性
3.1 ガン診断におけるガン遺伝子
3.2 金焦遺伝子産物の検定
3.3 DNAプローブによるガン診断
3.4 おわりに
4 DNAプローブ利用の新しい試み
4.1 腫瘍の分類――腫瘍の異種性(heterogeneity)に対する分子論的基礎――
4.2 リンパ系新生物のDNA再編成と診断への応用性
5 参考
第6章 遺伝子診断に関連した諸技術
1 フローサイトメトリーの利用
1.1 染色体の分類と精製
1.2 フローカリオタイピング(Flow Karyotyping)
1.3 ソーティング(Sorting)
1.4 染色体のin situハイブリダゼーション
2 電気泳動による巨大DNA分子の分類
2.1 はじめに
2.2 パルスフィールドゲル電気泳動法(PFGE)
2.3 市販のPFGE装置
3 PFGEによる制限酵素切断地図の作成
3.1 はじめに
3.2 巨大DNA分子の操作法
3.3 大型制限酵素切断地図を作成する技術
3.4 大型制限酵素切断地図作成技術の応用性
4 巨大DNA分子のin vitroおよびin vivoでの取り扱い
4.1 巨大DNA分子丸in vitroでの取り扱い
4.2 巨大DNA分子のin vivoでの取り扱い
5 DNAプローブによる転写タンパク因子の同定と精製
5.1 はじめに
5.2 ビオチン標識アフィニティークロマトグラフィー法
5.3 合成オリゴヌクレオチドを用いた紫外線クロスリンキング法
5.4 オリゴヌクレオチドと転写因子との複合体の性状
5.5 おわりに
6 酵素的増幅法を利用した特異的塩基配列の遺伝子解析
6.1 はじめに
6.2 Polymerase chain reaction(PCR)法によるDNA断片の増幅
6.3 PCR法によるクローニングと直接的な塩基配列の決定
6.4 対立遺伝子に特異的なオリゴヌクレオチブプローブを使ったPCR法増幅DNAの解析
7 電顕レベルでのin situハイブリダイゼーション
7.1 はじめに
7.2 原理徳実験の概略
7.3 各ステップの操作手順
7.4 検出の実例
7.5 応用性
7.6 プローブ 検出系の改良
8 DNA鎖の一塩基変化を検出する方法
8.1 はじめに――一塩基突然変異の重要性――
8.2 RFLP法と合成DNAプローブ法
8.3 新しい一塩基変化検出法
8.4 応用性
9 DNA鎖置換検定法
9.1 はじめに
9.2 DNA鎖置換検定法の原理
9.3 DNA鎖置換検定法の特徴
9.4 ホモローガスな塩基配列に対する要求性
9.5 ReaAや反応効率促進剤を使ったDNA鎖置換検定法
9.6 DNA鎖置換検定法の意義
10 antisense RNA法
10.1 はじめに
10.2 antisense RNA
10.3 antisense RNA法の意義
第7章 非放射性ハイブリダイゼーションプローブの開発
1 はじめに
2 Bio-probe法
2.1 原理
2.2 実際の操作について
2.3 実験例
3 Photobiotin法
3.1 原理
3.2 操作
3.3 実験例
4 Blu GENE法
5 Chemiprobe法
5.1 原理
5.2 実験例
6 Labezyme-POD法
7 まとめ
8 検出のための発色反応
8.1 ペルオキシダーゼ系
8.2 アルカリウォスファターゼ系
8.3 今後の展望
9 StrAviGenキットの利用
9.1 プローブ検出への利用
9.2 実験例――BluGENE法との比較――
10 市販のビオチン標識DNAプローブ
10.1 Patho-Geneキット
10.2 deoxy Bio-ProbeTM(標識プローブ)
11 ビオチン化ヌクレオチド
11.1 ビオチン化ヌクレオチドとその利用
11.2 ビオチン化ヌクレオチドの製品管理
11.3 ビオチン化ヌクレオチドを利用した末端標識法とBio-Bridge標識法
12 RNAの非放射性標識
第8章 合成オリゴヌクレオチドプローブ
1 合成オリゴヌクレオチドの応用性
1.1 リンカーとアダプター
1.2 プライマー
1.3 プローブ
1.4 部位特異的突然変異の誘発
1.5 市販の標識合成オリゴヌクレオチドプローブ
2 一塩基だけ異なるDNAを識別するためのオリゴヌクレオチドプローブ
2.1 合成オリゴデオキシリボヌクレオチド
2.2 一塩基だけ異なるRNAの識別
2.3 合成オリゴヌクレオチドプローブの応用性
第9章 展望
1 はじめに
2 今後の課題
2.1 特異的核酸プローブの開発
2.2 核酸プローブ増幅法の開発
2.3 標識法の開発
2.4 検出系の開発
2.5 ハイブリダイゼーション法の検討
2.6 検体処理方法の開発
3 現状と将来への期待
内容説明
本書はDNAプローブ利用技術の基礎から応用までを、周辺技術を含めて一冊にまとめた。またDNAプローブの普及の鍵を握ると思われる非放射性プローブの開発については、特に一章を設けて詳説した。
目次
第1章 序論
第2章 総論
第3章 DNAプローブによる感染症の診断
第4章 DNAプローブによるヒトの遺伝子診断
第5章 DNAプローブによるガン診断の可能性
第6章 遺伝子診断に関連した諸技術
第7章 非放射性ハイブリダイゼーションプローブの開発
第8章 合成オリゴヌクレオチドプローブ
第9章 展望
著者等紹介
高橋豊三[タカハシトヨゾウ]
1948年神奈川県に生まれる。1972年横浜市立大学医学部助手。1974年横浜中央病院付属高等看護学校非常勤講師。1982年医学博士号取得(横浜市立大学300号)。1982年スイス国バーゼル免疫学研究所に留学。1982年米国カルフォルニア大学バークレー校に留学。1984年横浜市立大学医学部付属高等看護学校非常勤講師。1984年横浜市立大学医学部助教授(細菌学教室)。1987年横浜市立大学医学部付属高等看護学校運営役員。著書に「細菌のL型菌と臨床医学との関連性」最新医学、35,1855-1861(1980)。「ファージベクターによるクローニングI.ベクター両腕の調整法」、“免疫実験操作法XIII”、(日本免疫学会編)(1984)。「ファージベクターによるクローニングII.Packaging mixtureの調整法」、“免疫実験操作法XIII”、(日本免疫学会編)(1984)。「ファージベクターによるクローニングIII.Ligation反応とIn vitroPackaging」、“免疫実験操作法XIII”、(日本免疫学会編)(1984)。「感染-体液性免疫の役割」、“細菌学はここまで進んだ”、(日本細菌学会編)、菜根出版(1
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

![おおきな森のどうぶつしょうぎ [バラエティ] (新装版)](../images/goods/ar2/web/imgdata2/40994/4099416607.jpg)