内容説明
心理と社会の双の視座から日本人の「生き心地」を学者・論客、現役大学生らがいま、熱く両断する。
目次
第1章 生きるのがしんどい、と言う若者たち(香山リカ)(生存を維持するということ;傷つきやすい若者のこころ ほか)
第2章 ネオリベ改革がもたらしたもの(上野千鶴子)(心理学と社会学の違い;心と社会の変化のシンクロ ほか)
第3章 シンポジウム 生きづらさのゆくえ(無条件の存在承認;豊かさゆえの生きづらさ ほか)
第4章 座談会 私たちの生きづらさ(つながりにおける依存と恐怖;距離感という問題 ほか)
第5章 生きづらさを超えて(嶋根克己)(「生きづらさのゆくえ」から;「生きづらさ」について考えることが生きづらい ほか)
著者等紹介
香山リカ[カヤマリカ]
1960年北海道札幌市生まれ。東京医科大学卒。現在、立教大学現代心理学部映像身体学科教授。臨床経験を生かして、新聞、雑誌で社会批評、文化批評、書評なども手がけ、現代人の“心の病”について洞察を続けている。専門は精神病理学だが、テレビゲームなどのサブカルチャーにも関心を持つ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
コットン
66
近そうで遠い心理学と社会学はとらえ方が同じなら、個人からと社会からのアプローチが違うものの本質が同じ場合もあるのが分かった。それにしても生きづらい時代なのは情報化社会の影響もあるのでは…。2013/11/30
ネギっ子gen
65
平成21年の専修大学創立130年記念シンポジウムを新書化。日本人の「生きづらさ」について香山リカや上野千鶴子や大学教員らが討論。前半の講演では、<現在多くの人が感じている「生きづらさ」を、香山さんは私たちの内なる「こころ」の問題として、上野さんは私たちを取り巻く「社会」の問題として明快に解き>ほぐす。80年代以降ネオリベや少子化が日本を大きく変えていったと言われるが、この社会は何処へ行きつくのか――。帯に、<心理と社会の双の視座から日本人の「生きづらさ」を学者・論客、現役大学生らが今、熱く両断する>と。⇒2021/04/21
Tadashi_N
16
二元論的に考えると、息詰まる。2016/06/17
ERIN
8
現代の「生きづらさ」について香山氏、上野氏をはじめとする大学教員・専大生らが討論。心理学(内なるこころの問題)と社会学(私達を取り巻く社会=人間の外側の問題)その仲介に哲学・倫理学を据え、それぞれの専門分野から紐解いていこうとする点が興味深かった。特に、本書で取り上げられていた“自己実現へのプレッシャー”は、無意識のうちに刷り込まれやすいものだと感じる。SNS上の煌びやかな写真や動画、可視化されるいいねや閲覧数などは、いつの間にか不安を煽る材料になってしまった。接触機会の多いコンテンツ上なら、なおさら。2022/05/08
shishi
6
[A]精神科医の香山さんと社会学者の上野さんを招いての専修大学での講演内容を含んだ新書。ネオリベラリズムと境界性パーソナリティなどの概念を中心に、現代の「生きづらさ」を考察。過剰な自己実現欲求や達成目標と、低い自己肯定感のギャップ、全能感と無力感、社会(大人)の幼児化など、よく言われる指摘だが、腑に落ちる説明がされていた。特にパネルディスカッションでの上野さんの「幼児性のある大人や老人は仕方ない。そういう人をどのように社会政策で包括していくかが問題」という切返しにはびっくり。そう来たか。2013/09/12
-
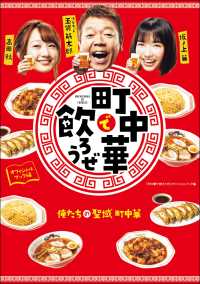
- 電子書籍
- 「町中華で飲ろうぜ」オフィシャルブック編
-
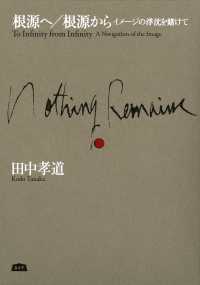
- 電子書籍
- 根源へ/根源から イメージの浮沈を賭け…
-

- 電子書籍
- セゾン・ド・エリコ Vol.9 扶桑社…
-

- 電子書籍
- 少年探偵・岬一郎短編集
-

- 電子書籍
- へびおばさん




