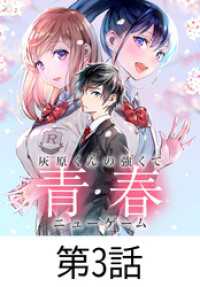出版社内容情報
さらば!ウソ八百の薩長史観!!
薩長による京都での倒幕活動ばかりが有名である。それが血なまぐさい幕末の中心である、と考えられている。刀を抜いて人を殺しに行った者は自分もやがて殺される。この人間世界を貫く冷酷な法則を無視して、英雄物語のロマン主義ばかりで幕末維新の体制変動を語る時代は終わった。薩長中心史観は見直される時期が到来したのである。
のちに維新の元勲として称賛される薩長の頭目たちには西洋近代学問の知識が無かった。全く無かったわけではないが、刀を抜くこともあった政争(政治権力闘争)に明け暮れたら、勉強(学問、研究)などしている暇がない。だから当時の天才級の頭脳をした日本人の多くは譜代の幕臣たちである。その人々について細かく調べたのが本書である。
[目次]
(まえがき)天才級の頭脳が集まった「蕃書調所」
(第1章)「尊王攘夷」から「開国和親」へ―その歴史の秘密
(第2章)明治の国家運営を担った旧幕臣たちの数学者たち
(第3章)蕃書調所の前身蕃書和解御用と初期蘭学者たち
(第4章)幕末の科学研究所・蕃書調所で起きていた権力闘争
(第5章)「二尺三寸が武士の刀」―幕末の剣術道場
(第6章)東京大学の原型・「蕃書調所」をつくった勝海舟
(第7章)大隈重信の旧幕府と新政府反主流派にまたがる人脈
(まえがき)天才級の頭脳が集まった「蕃書調所」
(第1章)「尊王攘夷」から「開国和親」へ―その歴史の秘密
(第2章)明治の国家運営を担った旧幕臣たちの数学者たち
(第3章)蕃書調所の前身蕃書和解御用と初期蘭学者たち
(第4章)幕末の科学研究所・蕃書調所で起きていた権力闘争
(第5章)「二尺三寸が武士の刀」―幕末の剣術道場
(第6章)東京大学の原型・「蕃書調所」をつくった勝海舟
(第7章)大隈重信の旧幕府と新政府反主流派にまたがる人脈
副島 隆彦[ソエジマタカヒコ]
1953年、福岡市生まれ。早稲田大学法学部卒。外資系銀行員、予備校講師、常葉学園大学教授などを歴任。政治思想、法制度、金融・経済、社会時事評論の分野で画期的な研究と評論活動を展開。副島国家戦略研究所(SNSI)を主宰し、日本人初の「民間人国家戦略家」として執筆・講演活動を続けている。
SNSI副島国家戦略研究所[エスエヌエスアイソエジマコッカセンリャクケンキュウジョ]
日本が生き延びてゆくための国家戦略を研究する民間シンクタンク。副島隆彦を研究所長に2000年4月に発足した。世界の諸政治思想の輸入、日本の政治・軍事分析、経済・金融分析等を主たる研究領域とする。若くて優秀な研究者の集団として注目を集めている。本書は『最高支配層だけが知っている日本の真実』『エコロジーという洗脳』『フリーメイソン=ユニテリアン教会が明治日本を動かした』(いずれも小社刊)等に次ぐ第8論文集となる。
内容説明
のちに維新の元勲と称讃される薩長の頭目たちには西洋近代学問の知識が無かった。全く無かったわけではないが、刀を抜くこともあった政争(政治権力闘争)に明け暮れたら、勉強(学問、研究)などしている暇がない。だから当時の天才級の頭脳をした日本人の多くは譜代の幕臣たちである。その人々について細かく調べたのが本書である。
目次
第1章 「尊王攘夷」から「開国和親」へ―その歴史の秘密
第2章 明治の国家運営を担った旧幕臣の数学者たち
第3章 蕃書調所の前身・蕃書和解御用と初期蘭学者たち
第4章 幕末の科学研究所・蕃書調所で起きていた権力闘争
第5章 「二尺三寸が武士の刀」―幕末の剣術道場
第6章 東京大学の原型「蕃書調所」をつくった勝海舟
第7章 大隈重信の旧幕府と新政府反主流派にまたがる人脈
著者等紹介
副島隆彦[ソエジマタカヒコ]
1953年、福岡市生まれ。早稲田大学法学部卒。外資系銀行員、予備校講師、常葉学園大学教授などを歴任。政治思想、法制度、金融・経済、社会時事評論の分野で画期的な研究と評論活動を展開。副島国家戦略研究所(SNSI)を主宰し、日本人初の「民間人国家戦略家」として執筆・講演活動を続けている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。