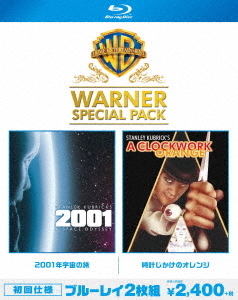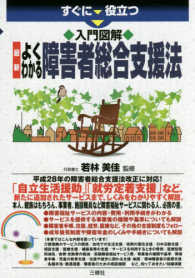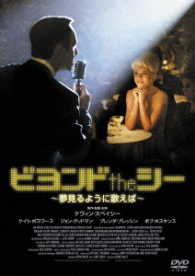出版社内容情報
協働はどうはじめる、共通価値はどう生み出す、そして地域運営をどう変えていくか…。
東日本大震災の被災地を後方から支援した遠野市と、復興支援を継続的な活動として実践する富士ゼロックス(株)が、行政・企業組織の枠組みを超え設立した「遠野みらい創りカレッジ」。
“ふれあうように学ぶ場" を中心に据えた活動は、2015 年度には延べ約5,300 名が訪れ、農家民泊などで2,500 名が宿泊。遠野市の交流人口拡大を支援した。2016 年度は“ 交流"“ 暮らしと文化"“ 産業創造"の基幹プログラムを開講、新事業や雇用のための議論がなされている。
本書は産官学民活動に必要な技術、実際に取り組まれているデザインとプログラム、協働で進められている研究活動と今後の展開を具体的に表し、さらに南足柄市、白老町、壱岐市など地方都市へと広がりつつ ある「みらい創り」の事例を紹介する。
日本全国に広がる地域創生を目指した活動の一助となる1冊。
本書刊行に当たって
序章 地域社会との協働
1章 地域との関係性創りに必要な技術
1 人を中心とした地域との関係性創り
2 コミュニケーション技術とは
3 コミュニケーションの素となる「実践知」
4 コミュニケーションから生み出される「集合知」
5 コミュニケーションの果たす役割
6 「実践知」を集合化するテクニカルプロセス
7 集合化された「実践知」を進化・活性化させるテクニカルプロセス
8 カレッジ設立に必要なコミュニケーション・プロセス
9 「みらい創り」活動に必要不可欠な人々
10 閉校活用とコンセプト創造
2章 関係者の共通価値を創造する「協働的実践プログラム」
1 共通価値とは何か
2 共通価値中心設計とカレッジでの実践的な活動例
・事例1 みんなの未来共創プログラム
・事例2 大学生の主体的な活動を支援するプログラム
・事例3 災害時後方支援拠点研究会を運営するプログラム
3 東京大学との協働的な実践活動
4 共通価値の創造を目指したField Work
5 地域社会との協働的実践活動から生み出される価値
6 TISPと「みらい創り」活動の相互作用
7 TISPと「みらい創りカレッジ」が持つ「場」のちから
3章 遠野から南足柄へ、「みらい創り」活動はこうすすめる
1 新たな災害時後方支援拠点の開発
2 遠野市に習った南足柄での「みらい創り」活動
3 新たな関係性構築の準備
4 始動、南足柄みらい創りプロジェクト
5 コミュニケーション・コーディネーターの実践手順
6 コミュニケーション技術を用いた課題の発見
7 南足柄みらい創りカレッジ開校が作り出す「未来」
8 長崎県壱岐市での「みらい創り」プロジェクト
9 地域コミュニティ形成への応用、宮城県女川町との協働的実践
10 これからの地域創生はこうすすめる
4章 「遠野型エリアマネジメント」の萌芽と期待
1 地域運営を変えなければならい
2 見える箱から見えない価値の創出へ
3 価値を生まない蛸壷型地域づくり
4 エリアマネジメント ‾蛸壷の破壊へ
5 遠野における「絆」
6 地区ごとのソーシャルキャピタルを探る
・事例1 駅前地区??遠野市の顔として
・事例2 宮守地区??グリーンツーリズムの本格展開に向けて
・事例3 上郷地区??進む高齢化と外部人材の活躍
7 タクティカル・アーバニズムの発想から考える遠野駅前地区のエリアマネジメント
8 遠野みらい創りカレッジに期待する役割
5章 信頼資本による「みらい創り」マネジメントの論理と実践
1 カレッジの自走化に向けて
2 カレッジ法人の運営姿勢
3 カレッジ運営モデルと重点事業
4 地域創生を牽引する人材創りが求められる背景
5 人づくり、地域のリーダー創造に向けた課題
6 課題対応に向けた人材創り
7 地域の未来を創造する「みらい創り」マネジメントの構造
8 社会教育プラットフォームを活用した双発的なコミュニティ創り
9 今後の「新・みらい創り」活動 ‾次世代への継承
10 誰も行かなかった道を選ぶ
あとがき
樋口 邦史[ヒグチ クニシ]
1983年成城大学卒業、同年富士ゼロックス?入社、 現在復興推進室室長。 2011 年東京理科大学大学院博士後期課程進学。2014年 3 月単位取得満期退学(技術経営修士)。同年 4 月遠野みらい創りカレッジ設立において中心的な役割を担う。現在、一般社団法人遠野みらい創りカレッジ代表理事
保井 美樹[ヤスイ ミキ]
1991年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。2001‾2004年東京大学先端科学技術研究センター特任助手、東京大学にて博士号取得。法政大学専任講師へて現在法政大学現代福祉学部・人間社会研究科教授。一般社団法人遠野みらい創りカレッジ理事
遠野みらい創りカレッジ[トオノミライヅクリカレッジ]
東日本大震災の復興推進活動をきっかけに、交流を進めてきた遠野市と富士ゼロックス(株)。交流を通じて、被災地の後方支援拠点としての取り組みを進め、市が抱える少子高齢化や、街の活性化といった課題の解決、そして地域と企業とが相互に新たな価値の創造を行っていくことを目的として、2014 年4 月に協定書を交わし、「遠野みらい創りカレッジ」を設立しました。その後2 年間の活動を経て、2016 年より地域に根差した運営母体となるために、「一般社団法人遠野みらい創りカレッジ」として生まれ変わりました。
内容説明
本書で描かれる「人間ネットワーク」の実践モデルは地域の生活者、地域行政、企業・大学などの研究機関との交流、そして交流を通じた学習から共通価値を見いだし、多くの地域リーダーを輩出する可能性を示している。設立過程や利活用した技術、グランドデザインとプログラム、協働活動とさらなる展望を示した。
目次
序章 地域社会との協働
1章 地域との関係性創りに必要な技術
2章 関係者の共通価値を創造する「協働的実践プログラム」
3章 遠野から南足柄へ、「みらい創り」活動はこうすすめる
4章 「遠野型エリアマネジメント」の萌芽と期待
5章 信頼資本による「みらい創り」マネジメントの論理と実践
著者等紹介
樋口邦史[ヒグチクニシ]
1983年成城大学経済学部卒業、同年富士ゼロックス株式会社入社、Global Service営業・企画部門を経て、現在復興推進室室長。2011年3月東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営専攻卒業、同年東京理科大学大学院イノベーション研究科イノベーション専攻博士後期課程へ進学。2014年3月単位取得満期退学(技術経営修士)。同年4月遠野みらい創りカレッジ設立において中心的な役割を担う。現在、一般社団法人遠野みらい創りカレッジ代表理事
保井美樹[ヤスイミキ]
1991年早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。1997年New York University,Robert F.Wagner Graduate School of Public Service,Urban Planning修士課程修了。2001‐2004年東京大学先端科学技術研究センター特任助手。2003年東京大学にて博士号取得2004年法政大学現代福祉学部専任講師。2005年法政大学現代福祉学部・人間社会研究科准教授。2010年London School of Economics(LSE)客員研究員。2012年から現在、法政大学現代福祉学部・人間社会研究科教授。一般社団法人遠野みらい創りカレッジ理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
伊東 和哉
-
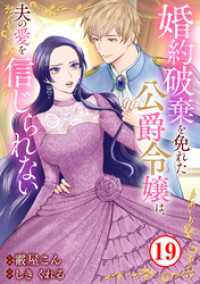
- 電子書籍
- 婚約破棄を免れた公爵令嬢は、夫の愛を信…
-
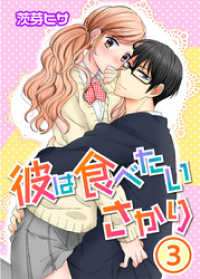
- 電子書籍
- 彼は食べたいさかり 3巻 Comic …