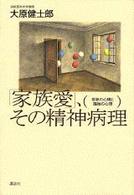出版社内容情報
フィリピンの活気に満ちた現代文化とアートを中心に多様な姿を紹介し、国際文化交流の現場から日系移民らの現在や、国際共同制作による現代演劇、日本のポップカルチャーとの交流など新時代の関係性を模索する。
ネガティブな社会情勢とは裏腹な芸術の宝庫、豊穣の島々・フィリピンからはじまる国際交流。
フィリピンは一般的にネガティブな印象で語られることが多い。不安定な社会や貧困。政治腐敗と治安の悪さ。日本映画で描かれる暗黒世界マニラ……。しかし現実は演劇、映画、社会派アート、フェミニズムアートからゲイカルチャーなど都市部、地方を含め様々な活気のあるパフォーミングアートの宝庫でもある。
本書は第1部でフィリピンの活気に満ちた現代文化とアートを中心に、この国の多様な姿を紹介し、第2部では国際文化交流の現場から、日系移民ら現在とNGOの活動、国際共同制作による現代演劇や日本のポップカルチャーとの新たな交流など、新時代の日本とフィリピンの関係性を模索する。
第一部 フィリピン・アートマネジメント編
第1章 パフォーミングアートの宝庫
第2章 メインストリームを行く社会派アート
第3章 フィリピン映画の過去・現在・未来
第4章 文学・ナショナリズム・デモクラシー
第5章 フィエスタ・キリスト教・フェミニズム・ゲイカルチャー
第6章 豊かな地方文化 ~コルディレラからミンダナオ
第二部 国際文化交流・実践編
第7章 文化交流の領分 ~戦争の記憶への眼差し
第8章 交流の基層となるもの ~日比をつなぐ二つの血
第9章 補助線を引く役割 ~NGO交流の現場
第10章 交流から創造へ ~国際共同制作の試み
第11章 同時代性の力 ~ポップカルチャー交流
第12章 新たな日比関係を求めて
【著者紹介】
国際交流基金、バンコク日本文化センター、アジアセンター知的交流課、ジャカルタ日本文化センター、マニラ事務局長などを歴任。東南アジアでの日本文化の紹介や現地文化財保存プロジェクトなど担当する。 朝日新聞をはじめ週刊エコノミスト誌などへ多数執筆。
内容説明
豊穣の島々から、世界へ。この時代に、この時に、人と人との結びつきを新たに生み出し、紡いでゆくことができれば、そこに生み出される無数の共感が見えてくる。
目次
第1部 フィリピンアート・ガイド編(パフォーミングアートの宝庫;メインストリームを行く社会派アート;フィリピン映画の過去・現在・未来;文学・ナショナリズム・デモクラシー;フィエスタ・キリスト教・フェミニズム・ゲイカルチャー;豊かな地方文化―コルディレラからミンダナオまで)
第2部 国際文化交流・実践編(文化交流の領分―戦争の記憶への眼差し;交流の基層となるもの―日比をつなぐ二つの血;補助線を引く役割―NGO交流の現場;交流から創造へ―国際共同制作の試み;同時代性の力―ポップカルチャー交流;新たな日比関係を求めて)
著者等紹介
鈴木勉[スズキベン]
1963年生まれ。国際交流基金日本語事業グループJF講座チーム長。86年国際交流基金に入社。バンコク日本文化センター、アジアセンター知的交流課、ジャカルタ日本文化センター、2005年より5年間マニラ日本文化センター所長を経て現職。日本と東南アジアとの文化交流や現地文化財保存プロジェクトなど担当。日刊まにら新聞、朝日新聞などへ小論、エッセイ、コラムなど執筆多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

![The Wreath : Or, Thoughts, Foreign and Indigenous, in Verse [by A.J.E. Battersby].](../images/goods/ar/work/imgdatag/11414/1141482916.JPG)