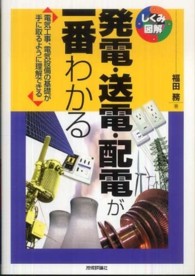内容説明
性の解放は、われわれに何をもたらしてきたのか。感情革命の行く末を問う。
目次
1 日々の実験、関係性、セクシュアリティ
2 フーコーのセクシュアリティ論
3 ロマンティック・ラブ等の愛着
4 愛情、自己投入、純粋な関係性
5 愛情やセックス等にたいする嗜癖
6 共依存の社会学的意味
7 心の迷い、性の悩み
8 純粋な関係性のかかえる諸矛盾
9 セクシュアリティ、抑圧、文明
10 民主制としての親密な関係性
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
27
親密性とくに共依存について、性的嗜癖の問題から詳しく分析されている。社会学の視点から、嗜癖について論じた貴重な本だと思った。性の問題は隠されてきたが、男性と女性との対等で正常な関係性のなかで性の問題からとらえられたとき、人びとのアイデンティティにとっても大きな意味を持つものだと思う。それが歪むと支配関係に陥っていく。自分に振り返りながら考えることもできた。2020/04/04
白義
18
再帰的な社会では、かつてステレオタイプな秩序に支配されていた性愛や婚姻の在り方もその前提が失われ、改めて個人が問うていくものになっていく。昔は女は貞淑さを割り振られ、男は女を複数囲うのもよしとされてきたが、今は周知の通り、女もそのような一方的な押し付けには否を問い、自分たちでそれぞれの関係性や性愛のスタイルを形成、模索しているし、男性社会の側もそれに反応する形で変容しつつある。性愛を物語化することで自分たちの存在を基礎づけるからこそ、時に恋愛や結婚が自己実現と見なされることもあるのだ2015/01/10
ぷほは
6
抑圧/解放という、十九世紀このかたの政治的区別から出発し、フーコーからフロイト→ライヒ→マルクーゼと逆行しつつ、再びフーコーの批判へと戻る。代理母出産や人工授精等の倫理問題ではなく(民主的な)政治の問題として論じられるため、古臭さは拭えないが、中盤の自己をめぐる精神理論や共依存に関してはザクザクきた。性愛パートナーがいない人でも両親との過去や現在を無視することはできないのであり、その業をここまでフラットに語りきるギデンズの文体は、もはや良識さというよりもAIの如き淡々とした無慈悲ささえ感じられるのだった。2018/02/12
富士さん
5
やっぱりこの人、あまり好きになれない。男女の関係が、公的で形式的だった時代から、近代になって私的で本質志向になったというのはとても魅力的な着想なのですが、その議論の仕方が実例より理論に偏り過ぎているように思います。特に精神分析的世界観がさも当然存在しているかのような議論は、フェミニズムに影響されない”ふつう”の女性を対象にすると言いながら、”ふつう”の女性が精神分析には影響されていると前提にするようで気持ち悪い。この時代のイギリス人的感覚はそうなのかもしれませんが、なら、ローカルな議論にすぎる気がします。2021/03/16
りっけんばうあー
5
セクシュアリティは我々一人ひとりが自由に塑型できるものに変容し、それは個人の「固有特性」となった。自己が再帰的自己自覚的達成目標となっている現代において、セクシュアリティを選び、育むことはある種アイデンティティの表明とも言える行為である。このことを前提にして人々は「純粋な関係性」を志向し始めた。その維持のためには自己投入が必要であるが、当然、関係の解消時には大きな精神的打撃が伴う。そのような矛盾をはらみつつも、純粋な関係性がもつ特性は近代の民主制に適合しうるものであるとギデンズは考えている。2016/01/05