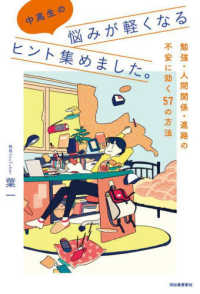内容説明
馬路村では、今日もゆずと森が育っています。
目次
第1章 「ゆず」のがんばりを村中のがんばりに(馬路村=“絶滅危惧種”は残った;雇用を増やして自立をめざす;馬路村が誇るゆず産業;森を売り森を循環させる=「エコアス馬路村」の戦略;馬路村が考える観光とは? ほか)
第2章 中山間地の側から生きかたを提案する馬路村(ゆずの村はなぜ成功したか?;村ぐるみ、行政ぐるみという発想;馬路村を広げる;馬路村の宿題)
著者等紹介
上治堂司[カミジタカシ]
馬路村村長。昭和29(1954)年、馬路村生まれ。昭和48(1973)年、馬路村役場に入職、平成10(1998)年、同村長に当選、現在3期目
竹下登志成[タケシタトシナリ]
自治体問題研究所事務局長。昭和24(1949)年、千葉市生まれ。昭和49(1974)年、自治体問題研究所に入職、平成13(2001)年から現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふさたろう
0
何事も良い面と悪い面があり、馬路村では普通は悪いと捉えられること(例えば国道が通っていないこと)を逆転の発想でプラスに持っていく。何よりも、発想の中心に「村民」有りきなのがよい。何のために行政があるのか、この小さな村が身体を張って教えてくれる。何にもないけれど、きっと笑顔が一杯の村なのだろうな。2010/06/21
とっきー
0
「中山間地」の村として生き残るために何をすべきで何をしてきたか、その奮闘がよく分かった。馬路村だけの問題では無く、日本の中山間地全体に言える問題の核心を突いている気がする。都市に暮らす者としては知らない世界で勉強になった。2018/08/07
-
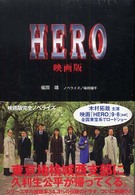
- 和書
- Hero映画版