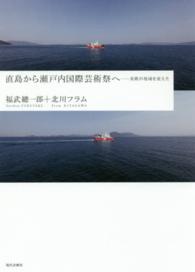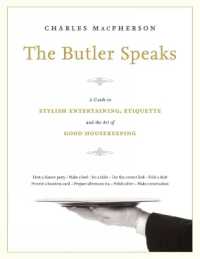- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > 海外文学
- > その他ヨーロッパ文学
内容説明
母、祖父母と過ごした少年時代。それは、世界の表層を拒絶し、真実に対峙することを学んでいく日々であった。死後四半世紀を経てなお、多くの読者を魅了する恐るべき作家ベルンハルト、その全作品を解き明かす鍵「自伝」五部作のひとつ。
著者等紹介
ベルンハルト,トーマス[ベルンハルト,トーマス] [Bernhard,Thomas]
1931‐1989。20世紀オーストリアを代表する作家のひとり。私生児として生まれ、貧しい少年時代を過ごしたが、無名の作家であった祖父から決定的感化を受ける。死の病から生還したあと、音楽と演劇学を修めつつ創作をはじめ、1963年に発表した『凍え』によってオーストリア国家賞を受賞。一躍文名を高める一方で、オーストリアへの挑発的言辞ゆえに衆目を集めた。以後、小説・劇作を数多く発表。1989年、58歳で病死
今井敦[イマイアツシ]
1965年生まれ。中央大学文学部卒業、中央大学大学院文学研究科単位取得満期退学。インスブルック大学留学、同大学にて哲学博士(Ph.D.)取得。現在、龍谷大学経済学部教授。専攻は現代ドイツ文学、とくにオーストリアのチロル地方の文学を専門とする(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
かふ
21
自伝五部作の最後の自伝。最初に戻って(翻訳ではこれが最初に出したのはわかりやすく、五部作で巡回していく形になるとか)子供時代の自伝なのだが、絶望的状況の中にも子供時代は幸福に感じることもあったのだ。その思い出は心温まる話が罵詈雑言の中で光っていた。そこがいい。作家である祖父の影響を受け、田舎(農場)での暮らしとかで知り合った友達とか。ベルンハルトにも友達がいたのだ。その家庭的な雰囲気もいい。その後ナチス政権になってとんでもない矯正学校に入れられたりするのだが。2025/02/07
内島菫
20
著者の祖父は「学校に子供を連れて行くことで、我々は、自分の子供を、日々町で出食わす大人と同様の不快な人間に、つまり屑にしているのだ」と言っており、「学校とは洗脳だ」と子供に言っている私は、僭越ながらベルンハルトの一家を同類のように感じながら読んだ。そして多くの人が、著者の母親のように、折り合いをつけるのは表面的でいいはずの世間に、自分を捨ててまで折り合いをつけようとするがために大切なものを見失ってゆく。けれども著者は当然ながら、母の愛情もちゃんと分かっている。親とは、子供に無条件に愛されている存在なのだ。2016/07/14
ソングライン
14
8歳、初めて自転車に乗れた日、30キロ離れたザルツブルグの叔母の家を尋ねようとする冒険から始まるオーストリアを代表する作家の少年期の自伝です。貧困のための引っ越し、子育てに疲れた母親の癇癪、学校でのいじめ、そして少年の心のより所であり、その才能を信じる偏屈でプライドの高い作家の祖父。ナチスドイツによるオーストリア併合が行われ、第2次世界大戦勃発の直前が時代背景です。2019/07/03
jamko
10
「自伝」五部作のうちの最後の作品であり時系列的には一番初めとなる著者の幼年期を描いた作品。「後見人」の自転車を勝手に試し乗りしそのまま30キロ以上離れた町に住む叔母を訪ねようと、ぐいぐい自転車を漕ぎだす冒頭のシーンとその後の残念な展開は印象的だ。「自伝」であるからもちろん自分の視点のみであるにも関わらず、最後までこの少年がどういう子なのか、どこか掴みきれないまま読み終えたのが新鮮で面白かった。背景となるナチスの台頭や大人たちの変容も興味深い。訳出されてるものは全部読みたいなぁ。2017/06/30
atomos
9
ベルンハルトの諸々は、お祖父ちゃん譲りだったのね、と納得した。自伝五部作の残りもちゃんと翻訳してくれそうな感じだし、楽しみだなあ。読むまでは絶対に死ねん。2016/07/05
-

- 電子書籍
- ホームセンターごと呼び出された私の大迷…