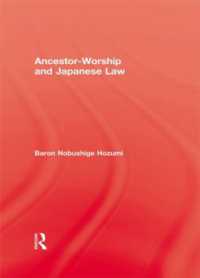出版社内容情報
黒板が日本の学校で使われるようになったのは今から150年ほど前。毎日の授業になくてはならない黒板の歴史から、色について、よい黒板とはどんなものか、やってはいけないこと、そして進化している電子黒板などを解説しています。
内容説明
朝、登校すると、教室でまず向き合うのが黒板です。黒板は、いつ、どこで生まれ、どんな使われ方をしてきたのでしょう。よい黒板、書きやすい黒板とはどんなものでしょう。チョークで上手に文字を書くコツはなんでしょう。「黒」から「緑」になるまでにはどんなできごとがあったのでしょう。さまざまな疑問を、みなさんとともに解き明かしていきます。
目次
第1章 黒板の色のなぞ(はじめは「黒い板」だった;黒板はいつどこで生まれたの? ほか)
第2章 学校と黒板(黒板は“教室の顔”;よい黒板とは ほか)
第3章 黒板のトリセツ(黒板は何からできているの?;黒板を長持ちさせるには? ほか)
第4章 黒板の未来を考える(黒板が進化してきた!;電子黒板で授業が変わる ほか)
著者等紹介
加藤昌男[カトウマサオ]
1966年早稲田大学政治経済学部卒。元NHKアナウンサー。テレビ・ラジオニュース、報道番組の取材・リポート、教育問題などを担当。1999年からNHK放送研修センター日本語センターで「先生のためのことばセミナー」「プレゼンテーション講座」などを担当。現在、NHK財団専門委員。日本国語教育学会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
とよぽん
42
黒板は、学校になくてはならない大切な教育機器。今はほとんどが濃い緑色で、黒い黒板はあまり見かけない。私も教員時代の34年間、ずっとお世話になってきた。この本は、黒板の歴史から、黒板の材料、表面の材質、製作工程や特徴など、必要十分な知識が平易な言葉できちんとまとめられていて、さすが元NHKアナウンサーの著者だと思った。近年はホワイトボードや電子黒板、タブレットなど黒板の短所を補うツールが登場して教育効果を上げているようである。しかし、著者も述べている通り、黒板はまだまだなくならない優れものだと思う。2024/10/22
へくとぱすかる
34
元は黒い石の板でできた石盤だったが、杉板を黒く塗って大量に普及させたのが明治の日本。緑に変わったのは目にやさしいからだと思っていたが、それだけではなかった。わが家にもメモの必要からか、かつて黒くて軽い小黒板があった。昭和期のものだとは思う。黒板の決め手は表面の粗さだそうで、たしかにツルツルではチョークで書けない。さすが職人技だ。本来耐用年数は意外に短いが、たいていの学校でもっと長く取りかえずに使っているかも? ホワイトボードや電子黒板が普及しても、黒板は完全にはなくならないだろう。紙の本も同じだと思う。2025/10/21
asisa
1
#2025第58回夏休みの本緑陰図書小学中学年2025/10/23
-

- 電子書籍
- 200m先の熱 分冊版 79 マーガレ…
-
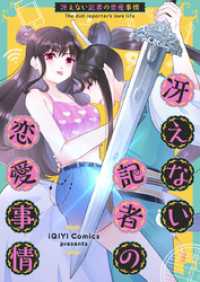
- 電子書籍
- 冴えない記者の恋愛事情【タテヨミ】第4…
-

- 電子書籍
- 【分冊版】すずめくんの声 13 MeD…
-
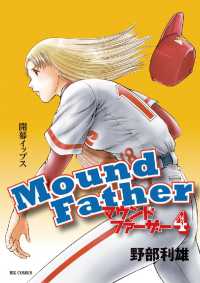
- 電子書籍
- マウンドファーザー(4) ビッグコミッ…