内容説明
オランダ渡りの視覚装置は江戸の人々に科学の視線を与えたか?荒唐無稽な黄表紙や、芝居小屋の覗きからくり、ポルノグラフィーに眼鏡、望遠鏡、顕微鏡があふれ、江戸の人々は今までになかった視覚の世界で戯れた。物を正確に見るための西洋の視覚装置は、目に見える現実のさらに向こうを見せる「心」のレンズと化してしまったのである。ニューアート・ヒストリーの手法で解き明かす江戸視覚文化の新次元。
目次
第1章 十八世紀の貿易と文化
第2章 「バタヴィア気質」で談論風発
第3章 装置と運動
第4章 絵を見せる機械
第5章 中を見る
第6章 レンズこそ眼目
第7章 高みから見る
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
子音はC 母音はA
3
高山宏訳という事で気になって読んでみた。18世紀に絞って(蘭)による科学技術の流入によって庶民の視覚文化が変容していく様を豊富な資料で示す。労作。ニューヴィジュアルスタディーズの知見を江戸文化を対象に繰り広げている。凄まじい程の資料の読み込み。2014/07/06
醗酵
1
読み応えアリアリ。2015/08/08
あかふく
1
江戸の「蘭」(必ずしもオランダとイコールではない)とのかかわり、特に視覚に関わる思想や物品(「奇器」)について見、それが江戸という時代の中でどのように消化されていったかを見る本。元来「影響」を問題にしていたが、実はそれではダメで、「日本人が自前で作り上げたヨーロッパ」を日本がどのように「とりこんだ(cooptation)」かを考えるべきであるという主張がある。著者はアルパースやフーコーの影響下にいる、いわゆる新美術史の人。そして訳者は高山宏と田中優子。これだけでそそられる人はそそられる本。2012/03/03
-
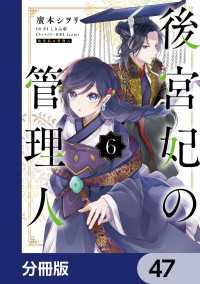
- 電子書籍
- 後宮妃の管理人【分冊版】 47 FLO…
-
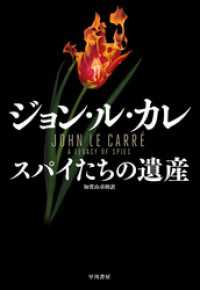
- 電子書籍
- スパイたちの遺産







