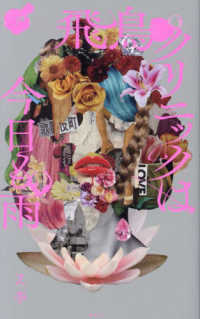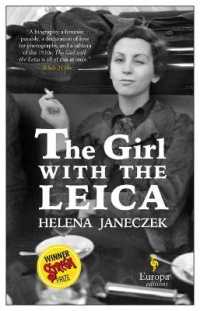出版社内容情報
発達障害者の事件はどのように報道されているのか。またその報道に内在するメディアの問題とは何か。現場の記者、当事者、医師、弁護士がそれぞれの立場からメディアを考える。
まえがき
◎序章◎発達障害とメディア
病歴や障害名はどう報道されているか 野沢和弘(毎日新聞記者)
長崎事件~障害名をめぐるスクープ合戦
1 報道
2 家裁決定 「障害そのものが直接本件非行に結びくものではない」
3 特ダネ競争による記事の落とし穴
豊川事件~発達障害に対する誤った認識
1 報道
2 家裁決定 障害と事件を結びつけた判断
3 「障害=疾患」と見る家裁・メディア
佐世保事件~専門家発言の安易な掲載
1 家裁決定 「障害と診断される程度ではない」
2 決定要旨にはない障害名も報道
横浜事件~読者との〈暗黙の了解〉の是非
1 「知的障害」を報じなかった朝日新聞
2 「開かれた新聞委員会」による検証
3 続報で伝えた朝日
報道の影響~一人歩きを始めたイメージ
1 「犯罪者になってしまうの?」
2 高額訴訟事件
3 過剰な責任追及
◎第一章◎発達障害とメディア
報道の現場から 野沢和弘(毎日新聞記者)
はじめに 発達障害の子をもつ記者として
なぜ障害名を報道するのか
1 ニュースの判断基準
2 捜査当局の影響
3 ワンフレーズ報道への傾斜
知る権利と障害者報道
1 公共空間
2 プライバシー情報はどこまで報じてよいか 松本智津夫氏を例に
これからの報道に向けて
◎第二章◎発達障害とメディア
当事者の立場から
【座談会】ニキリンコ×秋桜×野沢和弘
「ただいま」と「お帰り」の使い分け
「私は身勝手?」
発言が誘導されることもある
移動もたいへん
メディアとの付き合い方
障害だけが原因じゃない
長崎事件の報道の受け止め方
発達障害を理解するには
【特別寄稿】森口奈緒美(作家)
悪いことだけでなく、良いことも報道して欲しい
◎第三章◎発達障害とメディア
司法の現場から 大石剛一郎(弁護士)
はじめに
浅草事件の検証
1 報道
2 捜査
3 本人の法廷供述
4 公判における、メディアの報道内容に関する主張立証
5 第一審判決
報道がもたらす影響
1 事件発生から公判に至るあらまし
2 なぜ厳罰化するのか
精神鑑定は信じられるのか?
メディアに期待すること
【参考】刑事事件における精神鑑定
◎第四章◎発達障害とメディア
医療の現場から 市川宏伸(医師)
はじめに
医療とメディアとの接点
1 記者と話していて感じること
2 プライバシーとメディア
3 テレビ取材
4 医師側の問題
メディアが報じることの意味
研究段階における報道の類型
1 原因によるもの
2 効果ある薬物にもとづくもの
3 最近の話題
おわりに~慎重さとバランス感覚を
◎第五章◎発達障害とメディア
家族の立場から 氏田照子(社団法人日本自閉症協会副会長)
はじめに
これまで「自閉症」はどのように報道されてきたか
日本自閉症協会から見た今のメディアのありよう
1 治療教育に関する報道
2 事件とからめた報道
キーワードは「普段から」
◎終章◎発達障害とメディア
受け手の叱咤激励(メディアリテラシー)がメディアを変える 北村肇( 「週刊金曜日」編集長)
報道の前に人権なし
二つのタブー
高見に立ったジャーナリスト
消極的人権擁護と積極的人権擁護
発達障害の基礎知識 市川宏伸(医師)
はじめに
発達障害の概念
代表的な軽度の発達障害
発達障害と医療
発達障害と福祉
発達障害と教育
おわりに
コラム1 ハリウッド映画には自閉症がいっぱい
コラム2 障害者と文明
コラム3 「自閉隊」発言
コラム4 風の精
コラム5 親
執筆者紹介
まえがき
ちょっと変わったオジサンが人々を騒動に巻き込むイギリスの人気テレビ番組「ミスター・ビーン」を見たことがあるだろうか。ローワン・アトキンソンの絶妙な演技が世界に笑いを巻き起こしたコメディである。ふつうの人が考えないようなことを考え、ふつうの人がやらないようなことをやる。いったいビーンの思考回路はどうなってるの? 笑いをこらえ切れずにテレビ画面に見とれた経験のある人は多いと思う。
そのミスター・ビーンは、アスペルガー症候群という発達障害の人の行動をモデルにしてキャラクター化したと言われている。
たしかにアスペルガー症候群の人はちょっと変わっている。「猫の手も借りたいようだわ」とお母さんがつぶやくのを聞いて、本気で猫を探しに行った……というのはアスペルガー症候群を紹介するハンドブックに登場する典型的なエピソードである。「ふつう」の人とは少し変わったところがあるけれど、デリケートで、傷つきやすくて、やさしい人も多い。
ところが、殺人など重大事件を起こした子どもが精神鑑定でアスペルガー症候群などの発達障害と診断される例がこの数年いくつか重なり、〈アスペルガー症候群=危険〉という認識が世間に流布しようとしている。
そうした空気の醸成は、メディアによる報道が大きな原因とも言われている。実際、子どもの事件が起きると、メディア各社は精神鑑定に注目し、〈一般の子とは違う素因〉を他社より早くつかんで報道しようとする。
しかし、アスペルガー症候群などの発達障害が犯罪を直接引き起こしているわけではない。それは精神鑑定をした医師も念を押すように指摘し、多くの専門家の共通認識でもある。メディアも「発達障害そのものが犯罪を起こしているのではない」と記事の中では書いている。それでも子どもの事件が起きると、障害名の報道に血道を上げる傾向はあまり変わらない。それはなぜなのか。
メディアが事件の原因を〈一般の子とは違う素因=障害〉に求めて報道することが、障害児やその家族をますます追いつめ、社会との軋轢を生みやすい状況をつくることに一役買っている、という批判もある。もしもそうだとすると、メディアが事件を起こさせやすい状況をつくっているということになるのではないか。
では、こうした事件の際、障害名は一切報道すべきではないのだろうか。もしも、メディアが障害名をまったく報道しなくなったとしたら、どんな世の中になっていくのか。
このような数々の疑問に答え、自閉症やアスペルガー症候群というユニークな個性をもった人々が社会に温かく迎えられるためにはどうすればいいか。メディアの現場で働く記者や編集者、弁護士、医師、親などが議論を重ねる中から生まれたのが本書である(発達障害について詳しく知りたい方は、巻末の「発達障害の基礎知識」をご覧いただきたい)。
ミスター・ビーンを心やさしい愉快な隣人と見るか、相手の気持ちがわからない気味の悪い男と見るか──。私たちが暮らしている社会の質そのものが問われているのである。
内容説明
事件・事故が起きたとき、高機能自閉症・アスペルガー症候群などの発達障害をメディアはどう報道すべきか?読者・視聴者はニュースをどのように受け取ればよいか?報道の問題とその克服、さらには発達障害の人とともに生きる社会について、発達障害の当事者、家族、医師、弁護士、そして現役記者・編集者がそれぞれの立場からアプローチする。
目次
序章 発達障害とメディア―病歴や障害名はどう報道されているか
第1章 発達障害とメディア―報道の現場から
第2章 発達障害とメディア―当事者の立場から
第3章 発達障害とメディア―司法の現場から
第4章 発達障害とメディア―医療の現場から
第5章 発達障害とメディア―家族の立場から
終章 発達障害とメディア―受け手の叱咤激励がメディアを変える
発達障害の基礎知識
著者等紹介
野沢和弘[ノザワカズヒロ]
1959年生まれ。83年、毎日新聞社入社。厚生省(当時)、薬害エイズ取材班、障害者虐待取材班、児童虐待取材班などを担当。現在は社会部副部長。全日本手をつなぐ育成会理事・権利擁護委員長、千葉県障害者差別をなくす研究会座長などを歴任
北村肇[キタムラハジメ]
1952年生まれ。74年、毎日新聞社に入社。毎日新聞社社会部副部長を経て、日本新聞労働組合連合(新聞労連)の委員長を2期務める。教育・医療問題を中心に取材を重ねる。「サンデー毎日」編集長を経て、04年から「週刊金曜日」編集長に(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
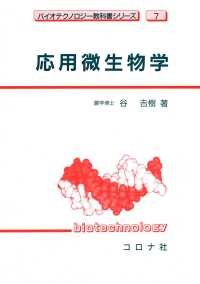
- 電子書籍
- 応用微生物学 バイオテクノロジー教科書…