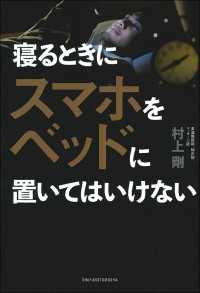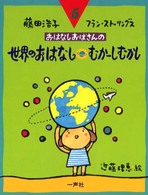出版社内容情報
今さら聞けない疑問から高度な弁護技術まで!刑事弁護の必携書
大阪弁護士会内で行っているメーリングリストに会員から投げられた質問と、それに対する刑事弁護委員会の弁護士や経験者からの回答を収録。実務のかゆいところに手が届く。
1 捜査弁護
1.1 総論
1.1.1 弁護方針
Subject 1:任意出頭に応じるべきか否か
Subject 2:弁護人が検察官に被疑者の居場所を教えないと犯人隠避になるか
Subject 3:受動喫シンナー
Subject 4:抑うつ状態の被疑者の捜査弁護
Subject 5:無罪を争う公務執行妨害罪の初動弁護
1.1.2 扶助事件
Subject 6:扶助の弁護人選任届の扱い
Subject 7:扶助申込について1
Subject 8:扶助申込について2
1.1.3 当番弁護
Subject 9:当番弁護と管轄
Subject 10:当番の受任義務について
1.2 被疑者の身体拘束
1.2.1 逮捕状請求書謄本
Subject 11:逮捕状請求書謄本の謄写請求
1.2.2 接見および接見指定、接見禁止
Subject 12:弁解録取・勾留質問日の接見
Subject 13:接見拒否
Subject 14:接見指定
Subject 15:接見禁止の一部解除に基づく面会時間
Subject 16:接見禁止の一部解除申立と準抗告
Subject 17:接見禁止の一部解除
Subject 18:接見禁止決定の謄本
1.2.3 身体拘束中の暴力等
Subject 19:被疑者が暴行を受けた場合の対応
1.2.4 勾留
Subject 20:勾留理由開示の成果を上げるためには?
Subject 21:勾留執行停止
2.1.1 弁護方針
Subject 32:「やっていないが早く出たいから認める」と言われたら
Subject 33:被告人は否認している、捜査検事は自白していると言う場合
Subject 34:覚せい剤と知って投棄する前に逮捕された場合
Subject 35:「有罪」の被告人が無罪になるよう努力するのは弁護権の濫用か
Subject 36:起訴後不当に勾留されていることを争えないか
Subject 37:勾留・勾留延長と弁護人選任権の告知の争い方
Subject 38:酩酊症について
Subject 39:公訴棄却の申立について
2.1.2 国選弁護と私選弁護
Subject 40:起訴後の扶助申込
Subject 41:国選と私選が併存する場合
Subject 42:国選弁護人を解任して別の弁護士を私選で選任する方法
Subject 43:国選事件受任後、余罪の捜査弁護の必要がある場合
Subject 44:国選で被告人を指定できるか
Subject 45:共犯者2名の国選弁護との利益相反の可能性
Subject 46:国選事件と過払金返還請求
Subject 47:私選の断り方
2.1.3 併合罪
Subject 48:裁判確定前に犯した罪の弁護
Subject 49:別の裁判管轄での追起訴と量刑
2.1.4 責任能力・訴訟能力
Subject 50:精神鑑定か疑うに足る相当な理由」
Subject 62:身元引受人と保釈後の制限住居の関係
Subject 63:身元引受人がいない被告人の保釈請求
Subject 64:弁護人の身元引受
Subject 65:保釈金の相場(初犯の覚せい剤自己使用)
Subject 66:保釈金の相場(業務上横領)
Subject 67:保釈中の旅行の許可
Subject 68:精神病で期日に欠席する被告人の保釈の取消と保証金の没取
Subject 69:保釈金の取戻し
2.2.2 拘置所内における処遇
Subject 70:大阪拘置所での土・日接見
Subject 71:接見の際の被告人の記録の持込みと書込みの可否
Subject 72:拘置所内での処遇について
Subject 73:うつ病の治療について
Subject 74:勾留中の被告人から宅下げをし、別人に差入することの可否
Subject 75:拘置所での「強制買い」
2.2.3 接見・接見禁止
Subject 76:被告人が警察署にいる場合の公判期日前後の裁判所での接見
Subject 77:接見等禁止決定に対する不服申立方法
2.2.4 勾留執行停止
Subject 78:四十九日の法要、納骨に参列するための勾留執行停止
2.3 証拠
2.3.1 証拠開示
Subject 79:検察官手持証拠の証拠調請求
Subject 80:証拠である録音テープの自白の任意性
2.3.6 弁護側立証
Subject 91:被告人の弁解している事実を立証する方法
Subject 92:アリバイ固めのための事情聴取で証拠隠滅の疑いをかけられるか
Subject 93:無罪を立証するための実験の法廷顕出方法
Subject 94:弾劾証拠(328条)の提出時期
Subject 95:被害者・目撃者の不同意・矛盾調書の提出
Subject 96:検察官の電話聴取書について
Subject 97:弁護人作成の内容証明に対する不同意
Subject 98:嘆願書に対する不同意
Subject 99:上申書に対する不同意
Subject 100:陳述書の「活用」について
Subject 101:携帯電話の発信場所の特定
Subject 102:虚偽作出証拠に対する対応
Subject 103:検察官の取調請求証拠採用後の撤回
2.4 量刑
2.4.1 示談
Subject 104:被害弁償の申入の有効性
Subject 105:被害弁償について
Subject 106:一部否認の場合の示談
Subject 107:示談金を受け取らせる方法
Subject 108:性犯罪被害者が示談の接触を拒絶している場合
Subject 109:不当な示談交渉への対応
Subject 110:自称被害者との接触
Subject 111:被害者からの不当な請求への対応
Subject 112:エセ右翼への対応
Sububject 124:公務員の免職規定
2.4.4 その他の情状立証
Subject 125:情状証人から聞くべきこと
Subject 126:幼児虐待のケースでの情状弁護
Subject 127:暴力団の構成員でないことを立証する方法
Subject 128:覚せい剤がやめられない被告人
Subject 129:ダルクとの接触の仕方
Subject 130:医療刑務所収容を望む場合の弁論の方法
Subject 131:ギャンブルをやめさせる方法
Subject 132:性嗜好異常の治療について
Subject 133:住居不定と情状
2.4.5 その他
Subject 134:量刑の見通し
Subject 135:通貨偽造の量刑
Subject 136:覚せい剤取締法違反の量刑
Subject 137:大麻取締法違反の量刑
Subject 138:無免許運転の量刑
Subject 139:著作権法違反の量刑と被害弁償など
Subject 140:痴漢行為の量刑等
2.5 判決手続
2.5.1 判決書
Subject 141:刑事の裁判書はなぜ有料なのか
2.5.2 執行猶予
Subject 142:被告人の責任能力を争うことと執行猶予取消要件
Subject 143:執行猶予の裁量取消
Subject 144:交通事犯における再度の執行猶予
Subject 145:覚せい剤事犯における再度の執行猶予
Subject 146:保護観察処分の取消
荷物の引取先
3 少年事件
3.1 方針
Subject 157:観護状謄本交付請求
Subject 158:留年間近の勾留中の少年
3.2 審判
Subject 159:少年の再犯で保護(試験)観察になる可能性
Subject 160:少年事件での縮小認定
Subject 161:逆送の基準
Subject 162:成人逆送について
Subject 163:少年法55条の家裁移送決定を求める申立
Subject 164:少年事件の抗告
3.3 処遇
Subject 165:少年院収容期間
3.4 その他
Subject 166:少年事件報道について
4 外国人事件
4.1 通訳
Subject 167:扶助事件の通訳人費用と通訳人の同行
Subject 168:法廷通訳費用の概念
4.2 オーバーステイ事案
Subject 169:外国人事件で不起訴・送還の例
Subject 170:判決前に身体の解放を得る方法
Subject 171:出入国管理及び難民認定法70条2項の適用範囲
Subject 172:オーバーステイ事件といえるのかどうか
Subject 173:公判中に在留期限が来るとき
Subject 174:被告人に在留特別許可を申請してほしいと言われた場合
Subject 175:オーバーステイと在留特別許可
Subject 176:強制送還のタイミング
4.3 その他
Subject 177:パスポートの申請ubject 185:控訴審の被告人質問・証人調べ
Subject 186:控訴審での弁論再開申立
Subject 187:控訴審での証拠開示請求の可否
5.6 控訴審における量刑
Subject 188:控訴して執行猶予は付くか
Subject 189:控訴審における量刑
5.7 控訴審・上告審における未決通算
Subject 190:控訴審における未決勾留日数通算1
Subject 191:控訴審における未決勾留日数通算2
Subject 192:上告審における未決勾留日数通算
5.8 その他
Subject 193:被告人と連絡がとれない場合(高裁国選事件)
Subject 194:上告と前刑の執行猶予期間満了との関係
Subject 195:控訴審における保釈
6 行刑
6.1 服役
Subject 196:刑務所の決め方
Subject 197:刑務所から内縁関係の確認
Subject 198:身体障害者の処遇について
Subject 199:生活保護と実刑
Subject 200:受刑者からの面会要求
Subject 201:服役中のアフターケア
6.2 更生保護
Subject 202:被告人所持金ゼロの場合
7 その他
7.1 差押え・領置物の還付および処分
Subject 203:差押え・領置物の判決確定後の還付
Subject 204:被告人の所有物を警察が勝手に処分した場合
7.2 民事との
刑事弁護の最前線から
本書は、2000年3月に、大阪弁護士会の刑事弁護委員会が新規登録弁護士の研修用に開設したメーリングリストでの議論を項目ごとに整理し、集約したものです。
もともとこのメーリングリストは、新人弁護士が、はじめて刑事弁護に取り組むなかで突き当たる初歩的な問題点について質問し、ベテランの弁護士が回答するという形を想定していました。ところが、実際にメーリングリストを開設してみると、投稿される質問の多くは、当初の想定とは異なり、非常に実践的で重要な問題であり、ベテラン弁護士もその回答に思わず頭を抱え込んでしまうようなものだったのです。そして、いつの間にか、このメーリングリストは、新人弁護士に対する研修にとどまらず、ベテラン、若手の枠を越え、刑事弁護人が日々生起し直面するさまざまな難題について、皆で議論し、その解決を目指していくというものになっていきました。現在このメーリングリストには、大阪弁護士会の刑事弁護に関心を持つ会員約300名が参加しています。
このメーリングリストに出されている問題点は、刑事弁護に取り組む弁護士らが、刑事弁護の最前線で、誰もが直面し、悩むようなものばかりです。そこで交わさスタートしますが、刑事司法改革には、取調べの可視化など、なお取り組まなければならない課題があります。まさにその刑事司法改革元年に発行された本書が、これまでのわが国の刑事弁護のひとつの水準・到達点を示し、今後の刑事弁護の道しるべとなることを願っています。
2005年3月
大阪弁護士会刑事弁護委員会
委員長 小坂井 久
-

- 和書
- ロシアの物語空間