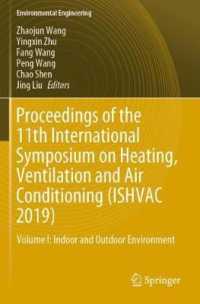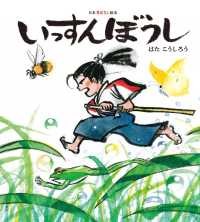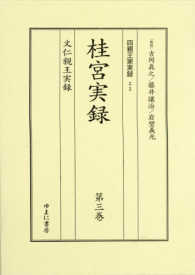内容説明
食卓に向かうときの心の豊かさは、ありふれたものを大事にするところから始まります。米のうまさ、海苔の口どけ、豆腐の甘み、塩のまろやかさ、ごま油の風味…。「暮しの手帖」の人気連載が単行本になりました。手間ひまかけてこしらえた食のドキュメンタリー17篇。
目次
山編(縄文の台所;奇跡の駅弁;みんなのタネ;朝市のお漬物;お乳の壁;覚悟の納豆)
海編(海苔の来た道;鰹節のひみつ;塩とはなにか;手づくりの缶詰)
里編(カリスマ食堂の原価率;旬の野菜と出合う;異色スーパーの補助線;ゴマ油の横顔;お豆腐屋さんの戦い;農家のマヨネーズ;食卓でイネを想う)
著者等紹介
瀬戸山玄[セトヤマフカシ]
1953年鹿児島県生まれ。早稲田大学卒業。WORKSHOP写真学校・荒木経惟教室に入塾後、1978年に入社の映像制作会社を経てフリー。2000年からドキュメンタリスト・記録家として文筆、写真、映像を駆使した活動を開始(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あじ
62
「タネが危ない」という書籍を読んでからというもの、廃れつつある”素材本来の味“を意識するようになった。(❈「タネが危ない」の著者が本書に登場!)日本の食糧事情や私たちの多忙な生活スタイルに合わせた【現代の食文化】に対し、生産者の方がやむなく歩調を合わせているのが現状なのだと思う。昔の手法でワラ苞納豆や一本釣りカツオの鰹節、無添加の漬物といった素材を主体にした生産を続けている人々がいる。全てを本来の食卓の味に近付ける事は難しいかもしれないが、【本物の味】を知っておく事で生存意識の改革が私の中で可動しそうだ。2016/02/17
きりぱい
9
面白かった。縄文の台所話に惹き込まれ、F1種が良いわけではなかったタネの話、え?牛って鳴かないの!と酪農の話など、読み進めるうちに、考えたら自然のまま食べられるものがほとんどないことに気付く。多くの人に安定して届けるはずの企業努力が日本の食糧事情を危機にさらす怖さ。自然なものを食べたいと願うのは簡単だけれど、供給する方は想像以上に手間。まして安易に量産するシステムができ上がっていると。そこを何とかしようと努力する生産者のドキュメンタリー。『暮らしの手帖』の連載だったそうで、身近な食材の話に考えさせられる。2013/05/11
たらこりっぷ
7
食べるものを、ただひたすらに真面目に作っている人たちが次々と登場します。作り手が「これだ」と確信し、その道をまっしぐらに走り続けている姿に何より安心します。どれも食べたくなるものばかりです。まずは、自分で食べて本当に美味しいと感じられるかどうか、確かめてみることから私は始めます。その上で、真っ当な値段を払い買い支えることで応援したいと心から思います。2013/04/06
へへろ~本舗
3
効率化、コスト重視という考えから廃れ失われて行く伝統野菜・伝統食・伝統文化そうそう伝統職も…。綺麗な見栄えのもの、安いもの重視という消費者の考えも変えていかないといけない。F1野菜より伝統野菜を!2022/12/09
おおきなかぶ
2
食べ物を作って下さる方へ、より一層の感謝の気持ちが湧き上がる一冊。2021/01/15