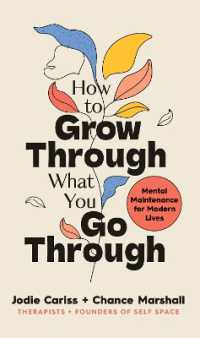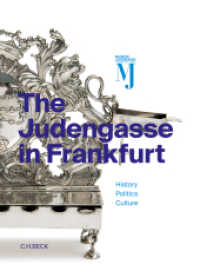内容説明
硬直化する世界の狭間に活きる、制度と実践のダイナミズム。冷戦の終結とグローバリゼーションの進展は、硬直化する国民国家や制度の対極に日常を生きる力としての宗教を生んでいる。近代の識字文化とメディアの言説が世界を色分けする今日、人々が活路を築く「場」を、国境・僧俗・民族アイデンティティの三つの境域から照射。既存の「めがね」の狭間から、大陸部東南アジア地域の現在が見えてくる。
目次
序文 大陸部東南アジア地域の宗教と社会変容
第1部 国家と制度の“境域”(ポル・ポト時代以後のカンボジア仏教における僧と俗;現代ミャンマーにおける仏教の制度化と“境域”の実践 ほか)
第2部 僧界と俗界の“境域”(「開発僧」と社会変容―東北タイの事例研究;出家と在家の境域―カンボジア仏教寺院における俗人女性修行者 ほか)
第3部 アイデンティティの“境域”(仏教国家タイと非仏教系山地民―キリスト教徒ラフおよび伝統派ラフの事例;カレン州パアンにおける仏教徒ポー・カレンの宗教実践 ほか)
付録一 「ラオス・サンガ統治法」および宗教関連資料
付録二 タイ・ムスリム関連資料
著者等紹介
林行夫[ハヤシユキオ]
1955年大阪府生まれ。現職は京都大学地域研究統合情報センター教授、京都大学博士(人間・環境学)。専攻は文化人類学・東南アジア民族誌学。1988年龍谷大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程単位取得退学。国立民族学博物館研究部助手、京都大学東南アジア研究センター(現東南アジア研究所)助教授、同教授を経て2006年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
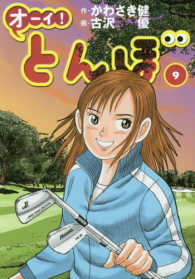
- 和書
- オーイ!とんぼ 〈9〉