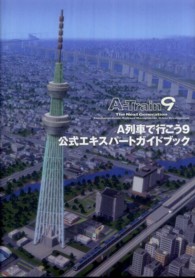内容説明
今は情報化時代と呼ばれています。多くの人たちが今までとは比べものにならないほど多くの情報に日常的に接しています。健康や医療、食品などの情報も例外ではありません。しかしながら、医療に全く素人である大部分の人たちにとって、多くの情報の中から自分にとって必要な情報を取り出すことは次第に難しくなってきています。そこで本書では健康情報をどのように読みとればよいのか、医療に詳しくない方にも分かりやすく解説したつもりです。本書で扱う健康情報の内容はいろいろです。健康食品、健康器具、民間療法、代替医療、栄養や食品と病気の関係、これらの情報を皆含んでいます。それぞれの内容は全く違うようにみえますが、医療・医学という視点で見れば、その見方には共通点があります。私は、その共通する見方について、多くの資料に基づき自分なりに考え、本書にまとめました。
目次
第1章 過ぎ去った「買ってはいけない症候群」は何を意味していたのか?―「買ってはいけない症候群」そこからはなにも生まれない
第2章 なぜ「健康食品」や「民間療法」を問題にしなければならないのか―「健康食品」と「民間療法」をどのようにとらえればよいか?
第3章 嘘とまやかしにあふれた「怪しい表現」を衝く―「怪しい表現」とはどのような表現をいうのか?
第4章 こんな肩書きや数字を信用してはいけない―「怪しい肩書き」や「誇大な数字」の正しい見分け方
第5章 「玉石混淆」のメディア情報の見分け方
メディア情報はどこまで信用できるのか?
第6章 インターネットの健康情報を考える―インターネット情報はどこまで使えるか?
第7章 性懲りもなくなぜ人は信じてしまうのか?―人はどのように騙されていくのか?
著者等紹介
小内亨[オナイトオル]
おない内科クリニック副院長。元桐生厚生総合病院内科診療部長。1959年前橋市に生まれる。84年群馬大学医学部卒業後、群馬大学医学部第一内科勤務を経て、92年より95年まで、アメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュにあるルイジアナ州立大学ベニントン・バイオメディカル・リサーチ・センターにて、肥満の基礎的研究に従事。その後、群馬大学医学部第一内科、公立七日市病院内科、桐生厚生総合病院内科を経て、2000年6月より現職。日常診療の中で患者さんと接しているうちに、民間療法や健康食品についての正しい知識が必要であることを痛感し、97年1月「健康情報の読み方」というホームページを創設。その中で、一般の人たちが巷にあふれる健康関連の情報をどのようにしたらきちんと判断できるかについて考えている。日経BP社の提供する医療関係者向けのホームページにて、コラム「医者も戸惑う健康情報」を担当。その他、法研が出版する「How to 健康管理」という月刊誌にコラム「気になる巷の健康情報」を連載中。医学博士。日本内科学会認定内科専門医。日本糖尿病学会認定医。日本内科学会認定内科指導医(99年~00年)。日本インターネット医療評議会運営委員
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。