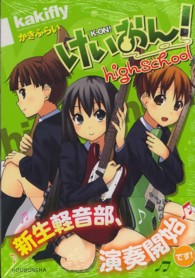内容説明
日本の路面電車は明治28年(1895)の京都電気鉄道の開業によって始まった。今から約110年前のことである。路面電車の歴史はモーター、制御器、台車などの輸入品もあったし、最近では海外の超低床電車に影響されて、日本も超低床電車が各地で登場する時代となる…といったことで、外国との比較を存分に入れて作成。
目次
上野の博覧会に日本最初の電車走る
路面走行鉄道が電車に落ち着くまで
京都に日本最初の営業電気鉄道開業
1900年ごろまでの世界の路面電車
日本各地に電車ブーム
名古屋、東京、大阪の路面電車
発展する電車
バスなどのライバル登場
大正時代の路面電車
低床車への試みと路面電車のバラエティー〔ほか〕
著者等紹介
吉川文夫[ヨシカワフミオ]
昭和7年東京本郷生まれ。日本大学工学部卒業。現在、関東学院大学工学部、神奈川大学工学部の非常勤講師。少年時代より鉄道に興味を持ち、カメラとメモを片手に各地の鉄道を訪ね、今日におよんでいる。現在、鉄道友の会副会長
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
六点
9
アメリカの強い影響を受け、日本の鉄道車両は進歩してきた。技術的には、多大の恩恵を日本は受けてきたのである。が、1960年代以降、アメリカのような自動車化社会を目指すべきだと、どういうわけか思い込んでしまった日本社会により、90年代まで長い逼塞に追い込まれた。この本では90年代の超低床電車までなのであるが、日本は富山や宇都宮のLRTなど、新たな展開を見せている。再び路面電車が技術的進展を見せることができるか。「構造不況業種」である鉄道車両メーカーは欧州の技術をどう取り入れ、超克するか、未来が楽しみである。2020/03/25
えすてい
7
晩年の吉川文夫らしい「集大成的な」著作である。国鉄やJRの車両よりも、地域生活に根差した私鉄車両を好んだ吉川文夫らしく、知人やツテから提供された膨大な資料や写真、そして自分自身の体験談を交えた蘊蓄も込められている。路面電車復権が叫ばれ始めている中で刊行されたが、日本の路面電車市場は構造的にジリ貧であり一両当たりの車両価格は製造数があまりに少ないために非常に高価である。そして大多数の事業者が利用客減少に伴い経営は決して潤沢ではない。吉川文夫は今空の上から日本の路面電車をどう見ているのだろう。
rbyawa
2
e138、さすがに馬車鉄道に関しては触れてないんですが、そこからの転換についての技術の紛糾は扱ってますし、日本の電気の父そのものも結構しっかり語ってくれていて、歴史好きとしてはなかなか満足な内容でした。電気路線開業&普通鉄道の転換60番目までの一覧いいなー(この時期は実際同じ扱いだったらしいんだよね、今は別物みたいに語られてるけど)。集電方式に決まり、それが進化し、前面に窓が作られ、2階建ては止め、と語られているんですがそっからはもう斜陽なんだよね。PCCカーでも路面電車の盛り返しならず、と。切ないよな。2014/05/19