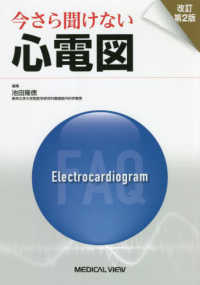内容説明
遺言書をめぐる「一澤帆布事件」、脅迫状がカギを握る「狭山事件」…奇跡の逆転判決を導いた筆跡鑑定の真実とは。驚愕の裁判の裏側を公開。
目次
第1部 ドキュメント 筆跡鑑定(一澤帆布遺言書事件;狭山事件―「脅迫状」の怪;筆跡鑑定がサスペンスに)
第2部 筆跡鑑定のすすめ(筆跡鑑定とは;筆跡鑑定の地位向上にむけて;コンピュータ機能の応用 ほか)
第3部 対談 筆跡鑑定の課題と筆跡学の未来―もう、科捜研にはまかせられない(筆跡学の位置づけと応用を;書道人口の減少と王羲之展の盛況;いいかげんな鑑定人の横行 ほか)
著者等紹介
魚住和晃[ウオズミカズアキ]
1946年三重県生まれ。神戸大学名誉教授、天津大学客員教授、文学博士。六甲筆跡科学研究所所長。神戸連続児童殺傷事件の犯行声明文、一澤帆布事件の遺言書など、数々の裁判で鑑定を手がける、筆跡鑑定学の第一人者。書家としての雅号は卿山(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
in medio tutissimus ibis.
2
筆跡鑑定のテクニカルな面よりも、それにまつわる法や裁判所の取り扱いや捜査システムの整備が発展途上である事への警鐘が主か。流石に筆跡鑑定マシーンみたいなもので一発とまでは思っていなかったけれど、一人の人間の筆跡が時の習得や経年によって変化するのみならず、一つの書類内でも気のゆるみ等で学習したきれいな字体と手癖の字体が混在してしまうとまで言われると、鑑定の難しさには納得しかない。著者は画像解析の手法を導入しようとしているけれど、そのコンピューターの要領のカツカツ差に時代を感じる。今だとAIとか導入するだろうか2019/09/12
waon
1
著者が実際に鑑定した事例がドラマのようで面白かった!筆跡鑑定には資格もなければ定型もなく、科学的な分析とは言えない鑑定が多くなされていることに驚き。筆跡鑑定の地位向上を目指す著者の厳しい言葉に、最後まで興味深く読まされた。2014/02/24
はち子
0
なんとなく自分も筆跡鑑定に夢を見すぎていたことに気付かされた一冊。 丁寧に説明すれば確かになあ…となることなのにね。 実際の裁判例などが載っていて面白かった。2016/03/08
ず
0
有名カバン店の係争の顛末がけっこう詳しく載ってて、こんな本で知るとは思わなかった。2014/05/06
leekpuerro
0
遺言状の筆跡などエピソードはドラマチックで面白い。でも、現代の筆跡鑑定では、参考程度にしかならない。筆跡鑑定のプロでも、素人に筆跡鑑定をし性格を診断してくれと頼まれた時には、文字の丁寧さと崩し具合を少し見る。後はその人の印象を見て鑑定したらしい。プロの鑑定結果でもそういうものだ。人によって結果も変わるなどの筆跡鑑定の限界も書いてあるのが素晴らしい。素人の癖に自分が文字を見ればその人の事がわかると思い上がってる人に読んで欲しい。2014/03/07