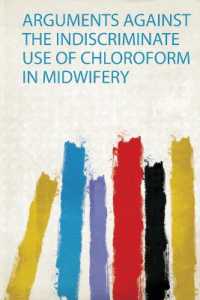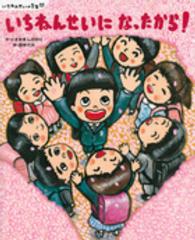内容説明
物語も、日記も、茶の湯も、屏風絵も、信心も、国学も、日本はいつも歌とともにあった。記紀万葉からJ‐POPまで、松岡日本歌謡論をリミックス、歌を忘れた現代人のためのニッポン組曲。
目次
1 うたの苗床―音と声と霊
2 記紀万葉のモダリティ―古代
3 仮名とあわせと無常感―平安
4 百月一首―うたの幕間
5 数寄の周辺―中世
6 道行三百年―近世
7 封印された言葉―近現代
著者等紹介
松岡正剛[マツオカセイゴウ]
1944年1月25日、悉皆屋の長男として京都に誕生。早稲田大学文学部中退後、高校生のための読書誌「ハイスクール・ライフ」編集長となる。1971年、オブジェ・マガジン「遊」創刊とともに、工作舎を設立。80年代初頭より日本美術文化全集「アート・ジャパネスク」(全一八巻)の総合編集を担当(刊行は1982‐84)。1982年に工作舎より独立し、87年、編集工学研究所を設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Tenouji
20
松岡正剛氏の歌について書かれた言葉を再編集した、正に編集工学の成果本。和歌については、知識が乏しく、なかなかどうして読むのに苦労する。が、内容は和歌にとどまらない、声を出す歌など日本文化そのもの。最近読んだ『野生の声音』や『江之浦奇譚』と、強くつながる内容で、このような文化を持つ民が、SNSに浸るとどうなるのか、とあらためて考えてしまった。日本を見直すのに、思想的なガイドとなる書。再読しよう。2021/05/29
冬薔薇
3
知の巨人の歌語り。次々続く言葉の知識の宝庫。最後まで面白く読めた。「春風の花を散らすと見る夢は さめても胸のさわぐなりけり」。2023/05/14
袖崎いたる
2
『万葉集』の編纂した大伴家持が現在でいうところの富山県に国司として就てたってのは意外。万葉心が富山あたりの、きっとたぶん立山連峰の眺めのもとで培われた精神に影響されていたのやろなと想像してまう。その万葉人について、奇物陳思を身の回りにある景物を取り寄せて生け取ると言い、これを「引き寄せ」と名付けているのがおかしい。無論、スピリチュアル系の言い回しを連想してしまうのである。『古今和歌集』にせよ、編集という方法を診てとるまなざしに貫かれている。編集者・松岡正剛その人の方法論探索の旅模様の、さらに編集されたもの2025/05/01
きょ
2
詩歌にまつわる松岡正剛の考え(日本は歌でできている)は、興味を引くと共に、如何にして日本語が成り立っているのか、その思考法に感心した。古事記は稗田阿礼の口移しの習いから太安万侶による文字起こしで音韻で漢字を使う。そして日本独自の仮名を発明するが、音訓読みの意味持たない漢字仮名で、日本書紀、万葉集、和歌等々に使われた。音が聞こえてこない文字は無力と言い切る。日本人は歌と共に暮らし、生活のよりどころとした心のよりどころが「うたかた」であると。日本の詩歌の花鳥風月、雪月花はマルチメディア・システムだ合点する。 2024/07/01
岡本 正行
2
いい本です。この本の茶者は、きっと本、もっといえば日本文学がこころから好きな人だと思います。自分の深淵を論じ立てるわけではない。あれやこれや言うわけでもない。淡々と、文学はどうなのかを語っている。また読み直したい。いろいろな日本文学を、自己流で語っている。2021/03/27
-

- 和書
- 教養の家族社会学