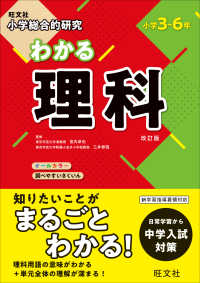出版社内容情報
群馬県の高校生自主活動は、どのように生まれ育ち、何を残したのか?
なぜ県教育委員会は執拗に〝弾圧〟を加え続けたのか?
一人の教師が自らの生い立ちを振り返り、群馬の高校生自主活動の歴史を中間総括する。
内容説明
人は“己の家”の軛からいかにして脱するのか?高校教師となった著者が、自らの生い立ちを振り返り、終生をかけて国・県の教育行政と対峙しつつ、高校生の「自主活動」に寄り添い、育ててきた歴史を中間的に総括する。
目次
序章
第1章 生まれと育ちの意味(1)
第2章 育ち(1)いよいよ群馬・教職・館林へ
第3章 育ち(2)大学を卒業し教員として群馬県へ
第4章 闘いの中で 教師集団と高校生たち
第5章 七〇年代を切り開く力は
第6章 七〇年世代の登場
第7章 地域の発展と高校生活動
第8章 不当配転に至るまで私は館林高校で何をしてきたか
第9章 太田工業高校時代
第10章 総括、四期の高校生活動とつながり
終章 お読みくださった皆様へ
著者等紹介
守隨吾朗[シュズイゴロウ]
1938年静岡県熱海市に生まれる。44年父戦死。熱海小学校入学、2年次に愛知県大山市、49年(5年次)に東京都中野に転校。新宿の中学、都立高校を経て浪人後早稲田大学教育学部入学、児童文化研究会(児研)・近代文学研究会所属。児研での活動で全国を巡回、また東京都桧原村藤原を知る。大学卒業後(62年)群馬県の教師として館林高校板倉分校を経て、本校に赴任し22年。84年「滞貨一掃不等配転」によって、県立太田工業高校に転任させられ、16年、99年定年退職する。その間高校生諸君と「群馬の高校生の自主活動」を共に作り、全国の高校生諸君との連帯を深める。退職後も連帯は続く。在職中・退職後を含めて共同保育所・学童保育所作りを行い、地域の教育の交流組織作りや、平和活動に参加。50回を超える海外旅行・滞在は世界の理解をより深めてくれる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。