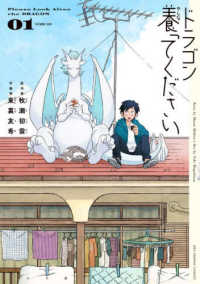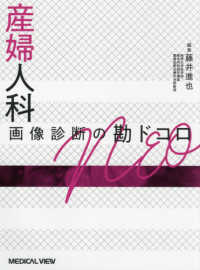内容説明
なぜ、100万人を超えるロヒンギャの人びとがミャンマーから逃れたのか―。ミャンマー社会に見え隠れする差別の実態とは―。軍政時代の潜入取材からおよそ30年にわたって同国を見続けてきたフォトジャーナリストによる、世界最大級の「難民問題」の解説書。
目次
1 ロヒンギャ難民キャンプへ(報道写真の“功罪”;建設中の「国境」;遠いロヒンギャ難民キャンプ ほか)
2 ロヒンギャ問題とは何か(ロヒンギャ報道の変遷;ロヒンギャ問題とは何か;ミャンマーはどのような国・社会か ほか)
3 ロヒンギャ問題を理解するための視点(民族(少数民族・先住民族)と市民権について
ミャンマーという“くに”の成り立ちとその社会の仕組みを読み解く
アウンサンスーチー氏は“政治家”である ほか)
著者等紹介
宇田有三[ウダユウゾウ]
1963年神戸市生まれ。フリーランス・フォトジャーナリスト。90年教員を経て渡米。ボストンにて写真を学んだ後、中米の紛争地エルサルバドルの取材を皮切りに取材活動を開始。軍事政権・先住民族・世界の貧困などを重点取材。95年神戸大学大学院国際協力研究科で国際法を学ぶ。「平和・共同ジャーナリスト基金奨励賞」「黒田清JCJ新人賞」他(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。