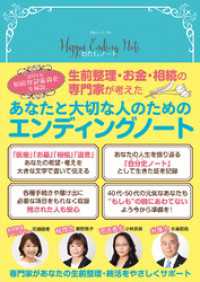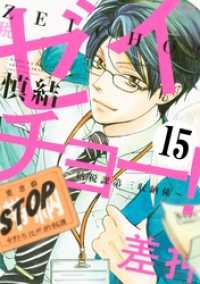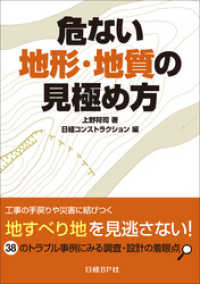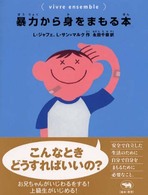内容説明
日本民具学の誕生と航跡の裏舞台を新しい切り口で紹介!民具研究の学史をたどり、日本の博物館学の礎を築いたモースを顕彰し、官の役割を再評価する。
目次
第1部 民具学の歴史(民具学の航跡;民具学の誕生とモース;モース研究の民具学的視点;日本におけるモース・コレクションの研究;モースの民具コレクションの意義;残存民具と残滓民具の迫間―幕末に民具を見据えた三賢;民具研究三五年の動向と展望)
第2部 民具学の方法(民具学の方法(方法論を考える;鎖状連結法;釣鉤の地域差研究)
民具学の構図
民俗学からみた民具学
民具の定義
民具研究と民俗学―北小浦における民具と生活
北小浦民具誌―風土の中の民具伝統
民具展示の今日的意義と構成)
著者等紹介
田辺悟[タナベサトル]
1936年、神奈川県横須賀市生まれ。法政大学社会学部卒業。海村民俗学、民具学、文化史学専攻。横須賀市自然・人文博物館館長、千葉経済大学教授を経て、現在、三浦市文化財保護委員会会長など。文学博士。日本民具学会会長、文化庁文化審議会専門委員を歴任。2008年旭日小綬章受章。著書に『日本蜑人(あま)伝統の研究』(法政大学出版局・第29回柳田國男賞受賞)、『城ヶ島漁村の教育社会学的研究』(平凡社・第2回下中教育奨励賞受賞)、『現代博物館論』(暁印書館・昭和61年度日本博物館協会東海地区業績賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mentyu
2
民具学は名前からして分かるように、対象を民具に限定して学問領域を設定している。それゆえに、まず扱うべき「民具」の定義で頭を悩ませねばならない。加えて人工品の中でも民具しか扱ってはいけないという規制のために、研究手法を確立できるのか怪しい状況にも置かれている。筆者は民具学を独立学問として取り扱う立場であるが、考古学の立場にある自分が読んでいると、かなり厳しいのではないかという感想は否めない。2018/09/24
西野西狸
0
民具研究の歴史を渋沢敬三ではなく、モースの時代まで遡って書かれていて、これまでの民具研究の発展の過程がわかりやすく書いてあってよかった。民具の定義や現状なども書かれていて大変参考になった。2014/12/14