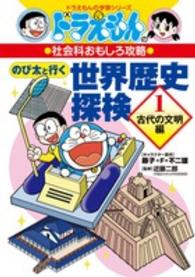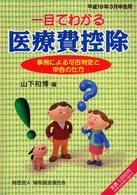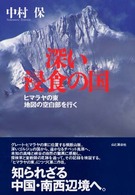出版社内容情報
民俗信仰をはじめ、現代民俗や世相、祭礼、生業、地域社会、博物館等テーマは民俗の変容、生成、再編に関わる問題意識が基調にある松崎憲三先生は、このたび古稀を迎えられ、平成三〇年三月をもって成城大学を定年退職されることとなった。本書は、長きにわたり、成城大学の民俗学を牽引され、民俗研究の広がりと深化に貢献された先生の慶事を喜び祝うとともに、ご学恩に感謝し、それに報いるために編まれた記念論集である。(中略)先生のご功績はアカデミズムの枠内にとどまるものではないが、成城大学に来られてからは、現代民俗や民俗信仰の分野を中心に据えて研究に邁進され、民俗学の新たな地平を切り開らかれた。とくに現代社会に鋭く切り込む視点は、同時代を生きる人々に響き合う多くの研究を生み出してこられた。民俗信仰をはじめとする伝統的なテーマにしても、先生の手にかかると必ず新輝な研究として生まれ変わる。こうした先生の学問に対する姿勢や独自の学風は、常日頃からの問題意識の高さ、着眼と観察力の鋭さ、視野の広さに基づくものであり、なかなか真似できるものではない。このことを十分に認識しつつも、本書では、先生の研究領域を念頭において執筆者それぞれが筆を振い、『民俗的世界の位相─変容・生成・再編─』を書名とする論集として一冊にまとめ、ささやかながら献呈する次第である。なお、松崎先生ご本人からも玉稿をありがたく賜り、本書の巻頭を飾らせていただいた。(前田俊一郎「まえがき」より抜粋)
目 次
まえがき??前田俊一郎
・葬送儀礼、墓制の変貌 ─墓じまいおよび寺院離れを視野に─ 松崎憲三
第一部 民俗信仰の探求
人を神に祀る
・古代の歌人を祀る習俗 ─肥後・細川家との関わりを中心に─ 福西大輔
・義経信仰をめぐる予備的考察? ─北海道平取町の義経神社を事例に─? 及川祥平
・陶磁器産業と職祖信仰 ─愛知県瀬戸市の事例から─ ?木大祐
・佐倉惣五郎観の変遷 ─『日本及日本人 秋季臨時増刊 義民号』の分析を中心に─ 佐山淳史
祈りと願い
・天にて比翼の鳥となる ─比翼塚の民俗学的考察─ 前田俊一郎
・雷電信仰の現在 ─板倉雷電神社の信仰を中心として─ 林 洋平
・見沼地域周辺における弁天信仰の諸相と課題?? 宇田哲雄
・六十六部をめぐる史実と伝承? ─東京都多摩市落合の小林家の事例を中心に 乾賢太郎
・御柱祭における鳥居の建立 ─式年造営の視点からの再考─ 金野啓史
・「めがね弘法」の信仰と目薬 ─その誕生と再編をめぐって─ 越川次郎
第二部 暮らしとまつり
生業の工夫と選択
・遊漁としての釣り文化 ─近代における釣り堀の発展─ ?君 龍
・東京内湾の肥料としての貝《キサゴ》 ??秋山笑子
・描かれた明治期の天蚕飼育 ─京都府大原神社奉納絵馬─ 佐野和子
・「銘菓」のなかの蚕糸業 ─製菓業者の蚕糸業に対するイメージについて─ 吉井勇也
・野菜の品種転換に関する予備的考察? ─江戸川区における小松菜のF1品種化を事例に─ 荒一能
祭事・儀礼の継承
・神楽を演じる地方公務員? ─埼玉県の神楽を事例として 田村明子
・女が創る祭の見せ場 ─千葉県匝瑳市八日市場の八重垣神社祇園祭を事例として─ 菊田祥子
・謡の師匠に伝えられた「小笠原流」の婚姻儀礼?? ─山形県天童市の事例から─ 村尾美江
・「無形文化財」としての古武道の位置づけ ?
─文化財指定への課題─ 小山隆秀
第三部 現代へのまなざし
地域社会との共生
・里山はなぜ桜の山となったのか ─福島市渡利地区の花見山をめぐって─ 金子祥之
・子育てと災害伝承 ─東日本大震災・岩手県宮古市の事例から─ 猿渡土貴
・ある被災地復興のその後? ─玄界島で「暮らしの場を取り戻す」ことを考える─ 中野紀和
・柳田國男の伝承観と自治論?? ─現代民俗論の課題─ 加藤秀雄
民俗学の資料と情報
・四コマ漫画に描かれた世相?? ─麻生豊『ノンキナトウサン』をめぐって─ 菅野剛宏
・英語圏とドイツ語圏における日本民俗学の紹介状況と今後の課題? ?ゲーラット ・クリスチャン
・地方民俗学界の再活性化策を模索する ─岡山・倉敷界隈の状況を通じて─ 吉原睦
・民俗展示の模型が内包する情報?? ─国立歴史民俗博物館「石川県白山麓焼畑出作り環境模型」を事例に─ 松田睦彦
松崎憲三先生略歴・著作
あとがき 猿渡土貴
及川祥平 猿渡土貴 ?木大祐 前田俊一郎 松崎かおり[オイカワショウヘイ サルワタリトキ タカギダイスケ マエダシュンイチロウ マツザキカオリ]
編集
目次
第1部 民俗信仰の探求(人を神に祀る;祈りと願い)
第2部 暮らしとまつり(生業の工夫と選択;祭事・儀礼の継承)
第3部 現代へのまなざし(地域社会との共生;民俗学の資料と情報)