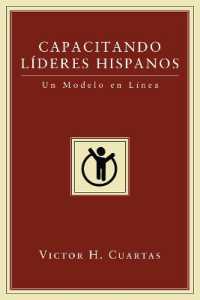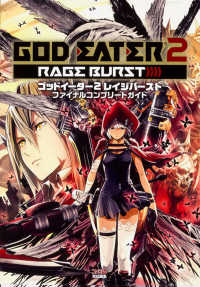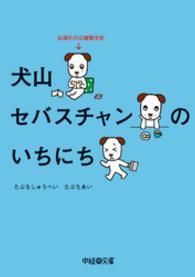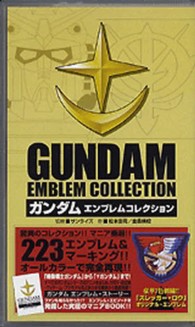内容説明
新潟は北東アジア交流圏の拠点都市として、中国大陸、朝鮮半島、ロシア極東などの地域との経済文化交流を進めている。本書では、韓国・中国・ロシアでの企業活動、ロシアとの市民交流、国際的なボランティア活動、国際援助など、広範な交流の様子をまとめた。それぞれの国に赴任した商社OBやNGOリーダーら、第一線で活躍する人々による現場からの報告から、交流とは何か、その将来はどうあるべきかが見えてくるだろう。
目次
1 国際交流とは何か(国際交流のキー・ワーズ―国際交流、コンピュータ・リテラシィ、グローカライゼーション;言語は国際交流の核となるだろうか―フランコフォニーの形成と多国間国際交流の試み)
2 経済交流の実際(韓国とのつき合い方;中国とのコミュニケーション基礎知識;混迷するロシアでの厳しいビジネス)
3 NGOと国際協力(新潟県の国際交流;ロシア市民との草の根交流;「公」を担うNGO;援助の現在)
著者等紹介
鈴木利久[スズキトシヒサ]
1950年生。広島大学教育学部卒業。広島大学大学院文学研究科修士課程修了。広島大学助手、新潟大学講師、同大学助教授を経て1998年より同大学教授(経済学部)。1996‐7年英国・ブリストル大学社会科学部客員研究員。2002‐3年ロシア・ハバロフスク経済法律アカデミー客員教授。専門は異文化論研究
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。