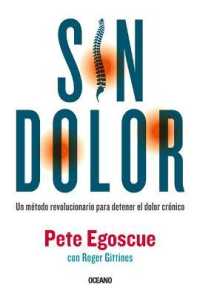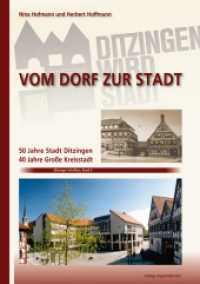内容説明
東京の下町・木挽町生まれの異色のフォーク・シンガーなぎら健壱が、“どうしても書き残しておきたい”と綴った、昭和30年代の下町の小僧たち。縁日、銭湯、貸本屋、駄菓子屋、カタ屋、ベーゴマ、紙芝居屋、と下町の少年達をとりまくすべてが、いきいきよみがえる、あのなつかしい世界。
目次
銀座生まれ
食べ物の思い出1―蕎麦
銀座の思い出1
おもちゃ三種の神器
銀座の思い出2
食ベ物の思い出2―ブルーチーズ
月光仮面
食べ物の思い出3 スパゲッティ・ミートソース
縁日
銭湯〔ほか〕
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
96
著者のなぎらけんいちさんは、昭和30年代を過ごした小学生時代について、住んでいた東京の下町、身の回りの出来事、遊び方、流行したものなどをエッセイとして紹介している。こどもがたくさんいた時代だった頃、私の住んでいたところも子供が各家に2〜3人住んでいた。夕方ともなれば町中は子供の遊び場だった。それが今、近所から子供の声など聞こえてこない。少子化の時代というのはこういうことなのか・・車をみても買い物にいっても私を含め高齢者ばかりだ。未来が見えない日本どうなるにだろう・・・2024/06/20
阿部義彦
15
52年生まれのなぎらさんの昭和30年代を思い起こす下町エッセイ。私は61年生まれで10歳下ですが、私たちの世代でなぎら健壱さんと言えば、何よりも『悲惨な戦い』では無いでしょうか?「♪私はーかつてあの様な悲惨な光景をみた事は無い~」今でもほぼ唄えますね。閑話休題。場所は東京に絞ってますが、10年違いでも、基本的には、体験として重なる事が多く懐かしく楽しめました。インスタント食品の台頭、紙芝居、貸本屋、子供の賭事、切手、駄菓子屋、特に食い物(肝油ドロップ、粉末ジュース、脱脂粉乳)が脳と直結してるなあと。2024/08/28
Yoshiyuki Kobuna
8
昭和63年データハウス刊行、平成6年ちくま文庫化。令和の現在読んでみると、まさに昭和中期、30年代のあれこれがこれでもかというほどに詰め込まれている。自分はこの時代に生まれてはいないけれど、当時のあるいは後の映像作品からうかがい知ったまさに当時の生活の情景は、活き活きと描かれていて圧巻の一言に尽きる。昭和の終わりに記されたこともあり、祭りへの苦言も。そういう時代を経ていまに至っていることを思えば貴重な文化記録であり、もっと単純にはとにかく面白い読み物。読み物と書くのがいいのではなかろうかと思う。2021/02/06
misui
5
このところ東京の下町のあたりをうろつくようになり、特に昭和30年代に興味を持って本書を読んだ。ただこれは子供の文化が中心なので少し目的と外れていた。地方出身の自分の経験と遠くで繋がるようなところもありつつ、やはり東京の異質さが際立つ。2020/10/30
ウチ●
5
なぎらさんの歳は私より一回り程上なので、細部までイロイロと書かれた昭和30年代の事柄は直接目にしてない物事が多い。しかし、なぜか懐かしく面白く読めた。多分、私の黄金時代だった昭和40年代・50年代にも昭和の王道30年代の伏流はあちこちに流れており、思い出したように突然にベーゴマやめんこが流行したり、ということも多かったからか。紙芝居と駄菓子屋は子供たちの正にパラダイスでだったなぁ。(近所の公園には昭和50年代半ばころまで紙芝居のオジサンが来てたんですよ)そうそう、地元では「もんじゃ」ではなく「おべった」。2015/06/24