内容説明
本書は、二十世紀現代文主要作家の作品の教材化の状況とその史的役割を明らかにするとともに、教材発掘の意図を探り、それぞれの教材に即して行われた実践、学習・受容の実態を可能な限り明らかにしようとしたものである。
目次
第1編 現代文教材の進出による教科内容の創成(坪内逍遙作品の教材化の状況とその史的役割;徳富蘆花作品の教材化の状況とその史的役割)
第2編 現代文教材の領域の拡大による教科内容の熟成(島崎藤村作品の教材化の状況とその史的役割;夏目漱石作品の教材化の状況とその史的役割;森鴎外作品の教材化の状況とその史的役割)
第3編 現代文教材の多彩な展開による教科内容の発展(芥川龍之介作品の教材化の状況とその史的役割;寺田寅彦作品の教材化の状況とその史的役割)
第4章 現代文教材の拡充による教科内容の深化(垣内松三編「国文新選」の教材化の特色とその史的役割;垣内松三編「国文鑑」の教材化の特色とその史的役割)
著者等紹介
橋本暢夫[ハシモトノブオ]
1931年(昭和6年)大阪市に生まれた。1954年広島大学教育学部卒業。和歌山県立桐蔭高等学校、広島県下の高等学校教諭を経て、広島県教育委員会指導課指導主事・高等学校教育係長・指導課課長補佐を勤めた。その間10年余広島県立女子大学講師を兼務した。1980(昭和55)年広島県立高等学校教頭から大分大学に転じ、1989(平成1)年から鳴門教育大学教授附属図書館長・評議員等を勤め1997年に退官。現在は徳島文理大学教授。博士(教育学)。1990(平成2)年大村はま賞受賞。専攻は、国語科教育学。国語教育史(国語教材史・国語教育実践史)の研究、及び国語科教育の各領域の実践理論を専門としている。中華人民共和国南開大学客員教授(1987・8‐1988・7)(1998・9‐1998・10)。徳島県NIE推進協議会会長(1996‐現在)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 同居人は秘密のSカレ【マイクロ】(42…
-

- 電子書籍
- 悪役令嬢の追放後! 教会改革ごはんで悠…
-
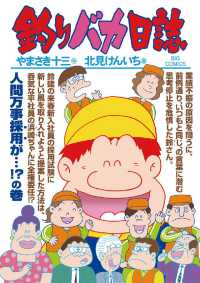
- 電子書籍
- 釣りバカ日誌(85) ビッグコミックス
-
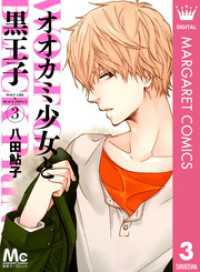
- 電子書籍
- オオカミ少女と黒王子 3 マーガレット…




