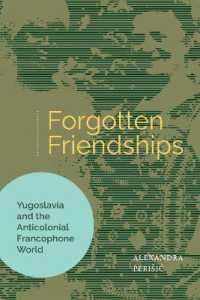出版社内容情報
歴史言語学で伝統的に問われ続けてきたトピックを、認知言語学の視点から捉え直す。「文法化」「(間)主観性」及び新たな仮説から,認知と歴史言語学の融和をめざし,日本語の言語変化の動機付けを考察。講座第1回配本(全7巻)。
歴史言語学で伝統的に問われ続けてきたトピックを、認知言語学の視点からもう一度,捉え直す。「文法化」「(間)主観性」及び新たに提案された仮説から,認知言語学と歴史言語学の融和をめざし,日本語の歴史との「対話」を通じて、言語変化の動機付けを考察する。認知日本語学講座第一回配本(全7巻)。
【認知日本語学講座について】
これまでの認知言語学の入門書や研究書は,英語を中心とする欧米の言語の研究が中心となっており,日本語の分析を中心とする認知言語学の本格的な書籍は出版されていないのが現状と言える。本講座はこの点を考慮し,認知言語学の方法論と研究法を,主に日本語の具体的な分析に適用した研究書のシリーズとして企画した。
第1巻『認知言語学の基礎』第2巻『認知音韻・形態論』(第2回配本予定)第3巻『認知統語論』第4巻『認知意味論』第5巻『認知語用論』第6巻『認知類型論』第7巻『認知歴史言語学』
第1章 日本語存在表現の文法化
―認知言語学と歴史言語学の接点を探る―
1.1 はじめに
1.2 文法化理論から見た存在表現の文法化
1.3 存在表現の歴史的変遷の概要
1.4 存在構文に基づくテイル・テアル構文
1.5 おわりに
第2章 テンス・アスペクトの文法化と類型論
―存在と時間の言語範疇化―
2.1 はじめに
2.2 伝統的日本語研究におけるテンス・アスペクト・モダリティ論
2.3 認知文法から見たテンス・アスペクト・モダリティ
2.4 文法化理論から見たテンス・アスペクトの発展
2.5 東アジア諸言語における存在表現の文法化とテンス・アスペクト
2.6 おわりに
第3章 言語相対的差異と単方向仮説
―可能表現の文法化・(間)主観化―
3.1 はじめに
3.2 主観化と主体化
3.3 言語相対論と文法化
3.4 可能表現の文法化経路
3.5 英語可能表現の文法化
3.6 出来事指向的用法と話者指向的用法
3.7 日本語可能表現の文法化
3.8 日本語における認識的可能用法と許可用法
3.9 日英語に見られる可能表現発達の差異
3.10 おわりに
第4章 節間の結合に関わる文法化・(間)主観化
―複文構造から言いさし構文へ―
4.1 はじめに
4.2 節の融合度
4.3 「ば」の発達―共通参与者項の存在
4.4 トピック性と条件
4.5 節間の意味的依存関係
4.6 対称読み「ば」の発生
4.7 連続性の緩み
4.8 後続節を持たない「ば」
4.9 接続機能の希薄化と(間)主観性
4.10 おわりに
第5章 類似性から派生する(間)主観的用法
―直喩から引用導入機能への文法化―
5.1 はじめに
5.2 直喩から引用導入機能へ―通言語的文法化経路の存在
5.3 新ぼかし表現に対する意識
―陣内(2006)によるアンケート調査から
5.4 直接性の回避とことばの変化
5.5 直喩から引用導入機能へ―「みたいな」とlikeの発達
5.6 Likeが伝達しうる話し手の心的態度
5.7 「みたいな」が表しうる話し手の心的態度
5.8 ヘッジと間主観化
5.9 おわりに
第6章 複合動詞の歴史的拡張
―ポライトネスから文法化へ―
6.1 はじめに
6.2 複合動詞の構成度
6.3 主観性とポライトネス
6.4 主観性の強化による創発
6.5 複合名詞への拡張
6.6 おわりに
第7章 名詞句の語用論的解釈
―主観性の強化が織り成す複合名詞の諸相―
7.1 はじめに
7.2 複合名詞の創発と文法化
7.3 複合名詞のフレーム
7.4 助詞「の」の文法化
7.5 体制化による構成要素の複合
7.6 創発性のダイナミズム
7.7 「計量」表現の認知歴史的変遷
7.8 おわりに
【著者紹介】
[著者紹介]
金杉高雄(かなすぎたかお)
現在,太成学院大学人間学部教授.1997年京都大学大学院人間・環境学研究科共生人間学専攻言語科学講座博士後期課程研究指導認定満期退学.主論文に,「前置詞定位の容認性に関わる関係詞の歴史的発達」『日本認知言語学会論文集』5(日本認知言語学会,2005年),「歴史的機能漂白による関係詞の選択」『言語科学論集』11(京都大学大学院人間・環境学研究科,2005年),「カテゴリー拡張に基づく英語指示代名詞の認知的分析―指示代名詞thatの歴史言語学的考察を中心に―」『認知言語学論考No.8』(ひつじ書房,2009年)などがある。
岡 智之(おかともゆき)
現在,東京学芸大学留学生センター教授。同教育学研究科国語教育専攻日本語教育コース,同教育学部日本語教育選修兼任。2004年大阪外国語大学大学院言語社会研究科言語社会専攻博士後期課程修了。博士(言語文化学)。韓国・湖南大学校日本語学科専任講師などを経て,現職。主論文に,「存在構文に基づくテイル(テアル)構文」『EX ORIENTE Vol.1』(大阪外国語大学言語社会学会(編),嵯峨野書院,1999年),「存在構文に基づく日本語諸構文のネットワーク」『認知言語学論考No.2』(ひつじ書房,2003年)などがある。
米倉よう子(よねくらようこ)
現在,奈良教育大学教育学部准教授。2002年大阪大学大学院文学研究科英文学専攻(英語学分野)博士後期課程単位取得退学。日本学術振興会特別研究員(PD)などを経て,現職。主論文に「認知文法から見たアスペクト的副詞の文法化」(秋元実治(編)『文法化:研究と課題』英潮社,2001年), On ‘Desired Results’ Associated with Over (Studies in Modern English: The Twentieth Anniversary Publication, Eichosha, 2003)などがある。
-

- 電子書籍
- やせたい人は、今夜もビールを飲みなさい